【自主レポート】
茨城県本部/茨城県職員組合 柳田 洋一 |
1. はじめに
女性が漁業を職業として選択することは、極めて稀である。漁業における女性就業者は、その殆どが自営漁業者の妻であり、漁業に従事する男性と結婚をした時点で、家族経営の一環として、漁業に携わることが多い。
このため、それまで全く違う職業に就いていた女性が結婚してから初めて漁業に従事することも少なくない。
一般的に家族経営を主体とした沿岸漁家(以下、「家族経営漁家」という。)において、多くの女性は漁業の陸上作業を担当している。陸上作業には、水揚後の漁獲物の選別、漁具の準備と修理などがある。また、各経営体の帳簿の管理も多くの場合、女性が行っている。
家族経営漁家では、女性が漁家の中で果たす役割は大きく、出漁日数とほぼ同じ日数、陸上作業を行うにも拘らず、この労働については、正当に評価されてこなかったのが現状である。
そこで本レポートでは、筆者が水産業改良普及員として在任した7年間に県中部のある地区を対象に実施した漁家女性の就業に関する実態調査の結果をふまえながら、家族経営漁家における男女共同参画のあり方について考える契機となることを期待して、その問題点と課題を整理したので、報告する。
2. 漁家の構成と調査対象漁家の特徴
(1) 漁家の構成
第9次漁業センサス(1995)によると、当該漁業地区には241軒の漁業世帯がある。この内、159世帯が自営漁業、82世帯が漁業従事者世帯である。
自営漁業の内訳は、図1に示したとおり、専業漁家の69世帯と第一種兼業の75世帯を含めると、自営漁業世帯の9割以上を占め、経済的中心者が漁業を主とする世帯が多いことがわかる。
漁業就業者の年齢別構成をみると、50歳代が最も多く男性109人、女性12人と漁業就業者全体319人の1/3を占めている。また、この世代は漁家世帯員の全ての男性が漁業従事者である。
現在、当該地区の漁家世帯の場合、現時点では20~30歳代は他業種に就いている男性も約半数いるが、50~60歳代では漁業就業者が多くを占めている(表1)。
女性の漁業就業者数は、23人(全体の7.2%)で、当該地区内にある漁協の業務報告書によれば、女性22人が、夫婦2人乗りの乗組員として操業している。
当該地区に限らず、本県の沿岸漁家の大多数の女性は「陸(おか)まわり」と呼ばれる陸上作業に従事しているが、漁業センサスでは漁業従事者を海上作業に従事した者と限定しているため、前述したように統計資料はない。
しかし、平成7年度国勢調査によると、当該地区で漁業に従事している女性は120人となっており、この陸まわりに従事するのは、漁業者の婦人である場合が多い。よって、女性の漁業従事者数は実質、自営漁業従事者と同数以上になるといえる。
(2) 調査対象漁家の特徴
表2は、当該漁協の業務報告書にある160人について、その水揚高を示したものである。これによると、水揚高1,000万円以上が81経営体で水揚のある経営体全体の56%を占め、500万円以上では107経営体(74%)に達している。
第9次漁業センサスによると、全国の個人漁業経営体のうち水揚高1,000万円以上の経営体の占める割合が約14%、また500万円以上でも約30%に過ぎない。
しかし、このように水揚高が高いのは、特に船曳網漁業、貝桁網漁業を行っている経営体に限定されている傾向が強い。この経営体は、5トン未満船を使用しており、乗組員数は2~3人である。
一方、船曳網漁業を営まない経営体では、2トン未満船のみが6割強を占め、乗組員数も1人であることが多い。船曳網を営まない経営体の中には水揚金額が1,000万円を越える経営体もあるが、そのほとんどは遊漁船業を営んでいる経営体である。
表3は、今回の調査対象とした当該地区の代表的な漁業種類である船曳網を中心に営む漁家世帯のうち10軒について概況を示したものである。
A~Dは後継者が確保されている経営体で、乗組員は3~4人、水揚金額も2千万円台後半が多く、当該地区の中でもかなり恵まれた状況にある経営体である。
E~Jは、後継者が確保されていない経営体および夫婦2人操業を行っている経営体である。
3. 家族経営漁家における女性就業と意識状況
(1) 女性の就業実態
① 1日の生活サイクル
本県の沿岸漁業では、水揚の際に、船主や息子の妻など女性が陸まわりとして市場に出ることになっており、各漁船から最低でも1人以上の労働力を提供し、共同作業で行うのが、この地域の原則となっている。
図2にシラスを対象とした船曳網操業時の漁家婦人の1日の生活サイクルを示した。
これを見ると、朝の出港に合わせて、午前4時~4時半に起き、漁に出る男性の弁当を作り、5時には家を出る。自宅から港まで、夫や父親を車で送り、帰って来てから、家の仕事を片付けるが、時化日には朝起きずに寝ていることが多いということである。
11時頃、再び魚市場に来て、水揚げの準備を始める。入札に間に合うように、漁を終えた船が入港すると、カゴに入ったシラスは、女性たちの手に渡される。自分の船だけでなく誰の船のでも共業で市場に揚げる。
シラスをトラックに乗せた後、自分達のカゴを洗って、市場で伝票をもらい、市場を出るのは午後3時頃になる。
夜7時頃には明日の仕度、弁当や朝食の準備が終わると就寝するが、夫婦で船に乗っている女性は8時頃、それ以外の女性は9時頃になることが多い。しかし、テレビを見たり、雑用を済ましていると、つい寝るのが遅くなってしまい、10時~11時といったこともよくある。
冬期は、午前6時に船が出港するのでまだよいが、夏期は午前3時には出港する日が多いので、早朝2時には起きなければならない。漁家婦人が日頃大変であると感じていることの一つに慢性的な睡眠不足があげられ、もう少し睡眠時間がほしいという話しもよく聞かれる。
② 漁家女性の労働
現在のような市場がなかった頃は、魚を揚げる場所が異なり、運ぶのが大変だったため、7~8つで「岸下(かしした)」という班を編成していた。その名残が現在でも残っており、陸上作業は共同で行うが、自分の班の人同士は特に助け合って行っている。
毎日、シラスの入った数十kgもあるカゴを岸壁から移動させたり、使用済みのカゴを中腰の姿勢で冷たい水を使って手作業で洗うなど、不自然な姿勢で作業することが多いため、腰痛や冷え症に悩まされる女性も多い。
以前、カゴをローラーに乗せて運ぶという試みをしたことがあったが、人が運んだ方が速いということで、現在は使われていない。
カゴを仲買業者のトラックに乗せる時、リフトの様なもので一気に運べたらいいという意見もある。
陸上作業を担っている女性にとって、日々の仕事で体を痛めないように、身体に無理のない姿勢で仕事ができるように作業場環境を整えることも必要である。
陸まわりの仕事に就いたのは結婚してからすぐという人もいれば、子供が少し大きくなってからという人もいる。結婚する時はしばらくは陸まわりにでるつもりはなかったのに、状況が変わって嫁いですぐ出ることになった人もいる。
仕事をしている間、小さい子供は親が見ていてくれる家もあれば、保育園に預けている家もある。
当該地区では、漁協の取り決めにより、日曜日と祝祭日が漁休日になっている他、お盆の8月13~17日、正月に市場が休みになる。また、時化の日も、当然、操業は行われていないが、女性が漁業に従事している日数は150~200日が最も多い。
次に、平成6年に茨城県農業技術課が実施した女性漁業者の暮らしぶり・考え方に関するアンケート調査(表4、表5)から漁業における労働時間状況を夫婦間でみると、乗船する男性は5時間以下(約70%)であるのに対し、陸廻りの作業の女性は、5時間以上が逆に75%を占めている。
また、最も忙しい時においても、10時間を超える男性が15%であるのに対し、女性は半数以上(56%)であり、女性の方が労働時間が長い。陸まわりの仕事は、船が入港した時すぐに作業できる体制をとる必要があるため、待機時間も長くなる。
このような労働に対して報酬を支払うべきであるが、給料制や収益に応じた分配を行っている漁家は33.3%である。労働に対する報酬の考え方をもつ漁家は、まだ少ない。
同居の姑が家計を預かっていた頃、「子供が小さくて、いろいろお金がかかるのだけれど、くださいと言いにくくて、やりくりに苦労した」とか、「今は自分が家計を預かっているけど、それでも給料ってわけではない」、「自分の自由になるお金がもらえれば、もっと仕事にはりあいが出る」という意見を持つ漁家女性は多い。
一家の家計を預かる(財布の紐を握る)のは漁家女性であるが、親世代と同居していても、家計がひとつであるため、嫁いでから自分が家計を預かるまでの間はどうしても窮屈な思いをしている。
これは漁家だけでなく、他の同居世帯にも共通する問題ではある。しかし、漁家女性の場合は、労働に対する報酬があいまいなところに問題がある。
③ 漁船に乗る女性たちの実態
前述したように、乗組員として海上作業に従事している女性は22人で、そのほとんどが夫婦操業である。
乗船するようになった契機は、漁家に嫁いだ時からという人はなく、夫の父親が引退したからとか、夫の弟が船に乗れなくなってしまったから、雇いで乗ってくれる人がいないから、息子が乗船してくれるまでのつなぎとしてなどと、やむを得ず自分が乗ることになった人が多く、これはシラス船曳網漁業が2人操業を基本としていることに関係がある。
仮に、単身操業になると、漁業種類を変えなければならず、従前のような水揚金額は期待できなくなるため、誰かが船に乗ることが必要になり、女性たちも船に乗るようになった経緯がある。
15~16年前から船に乗っているある女性は、当時は女性の乗船禁忌も強く、船に乗る時に塩をまかれたりして、昔は、女が船に乗るなんてけしからんという風潮だったから苦労したということである。
仕事は、投網・揚網・漁獲物の処理等男性の乗り子と同質の仕事を行い、女手にはきついところもあり、夫婦船は男性2人乗りよりも仕事量(網入れ回数など)が少なくなるため、水揚も少なめになる。
また、船は出港すると長時間海上で作業することになる。そのため、トイレの有無も問題になる。
現在は、後継者不足など、女性も船に乗らざるを得ない状況が生じ、乗船する女性も以前に比べると増加したため、女性が船に乗るということに対する見方も変わってきたということである。
各漁船から陸まわりの仕事の人を出すというのは、どの船も同じことで、夫婦操業を行っているからといって免除されるわけではない。
夫婦船の漁家女性は、漁船が入港すると、船のことは船主の夫に任し、自分は船から降りて、市場に待機していた女性たちに混じって陸まわりの仕事を行う。つまり海上作業と陸上作業の両方をこなし、その仕事量は2人分になる。もし自分が陸まわりの仕事をしないで、他の人に頼めばその人に給料を払わなければならなくなる。それであれば、自分が陸廻りの仕事もしようという人も多い。
このように乗船して、陸まわりもする女性たちの仕事はかなり大変である。
4. 男女共同参画を推進するには(まとめに代えて)
家族経営漁家における男女共同参画を推進するうえで、重要となるのは、陸まわり作業に対する報酬の検討である。
漁家女性は、出漁日数とほぼ同じ日数を従事しており、陸廻りの女性達の支えが欠かせないものになっているのにも拘らず、通常、作業に対する報酬は支払われず、いわゆるアンペイドワーク(「無償労働」と訳され、賃金や報酬が支払われない働き方や活動を指す)の状態にあることである。対価をもたらさない労働は労働とみなされず、労働統計にも計上されず、「見えない労働」として正当な評価を受けてこなかった。
「陸まわり」の作業を「手伝い」としてではなく、「仕事」として位置付け、ひとつの労働の形態として評価していくことがこれから必要になってくる。ひとりの労働者として評価する、その目に見える形の一つが報酬であり、それが女性の仕事に対する意欲向上にもなり、自分の仕事に対する自信のようなものにつながっていくと考えられる。
また、家族経営漁家では、家計と経営の仕分けがなされずに、丼勘定になっており、家族間で給料を支払うという考え方は、今まで広く浸透していなかったことに問題がある。
このような問題は、農業等の家族経営体で全国的に見られており、農協婦人部や生活改善グループ等の女性組織団体として改善に取り組もうといった動きがみられる。
その一つが家族経営協定を結ぶことであり、結果的に女性の地位確立を図ることにつながり、漁業にも同様な取り組みが必要である。
本県では、農業改良普及センターと連携して、漁家における家族経営協定の締結を促進してきた結果2004年2月に4軒が家族経営協定を結ぶに至った(新聞記事参照)。
今後、この取り組みが本県全域に拡大して行くことを期待している。
1975年の国際女性年をきっかけに、生活のあらゆる領域での女性の労働の価値を再評価し、男女の不均衡な役割分担を見直そうという動きが出てきた。1980年以降、女性のアンペイドワークの貢献度を目に見えるものにすることが不可欠であるという認識から、国連の機関を中心に、その貢献度の測定と評価のためのデータ収集が進められ、日本でも1997年から経済企画庁が「無償労働の貨幣評価」を発表している。
無償労働の範囲は、炊事・洗濯などの家事、介護・看護、育児、買い物、ボランティアなど社会的活動の5項目にしぼられ、それによると、1996年の無償労働の評価額は国内総生産(GDP)の23.2%を占め、その84.5%は女性が担っており、男女の役割不均衡を如実に表す結果となっている。
男女平等社会とは、漁業に限らず男女が有償労働と無償労働をバランス良く担える社会であるということが、いまや世界の共通認識となってきており、国レベルでの支援策のもとに、住み良い社会を目指して私たち一人ひとりの意識改革が必要であると考えている。
|
図1 漁業経営体数 160経営体(うち個人経営体 159軒、共同経営体 1軒)
|
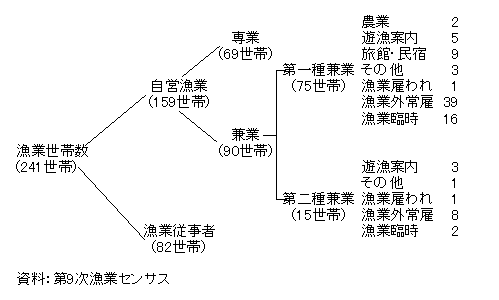 |
|
図2 船曳網を操業する漁家女性の一日の生活サイクル
|
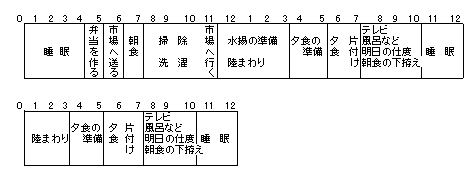 |
|
表1 当該地区の漁業世帯員数と漁業就業者数
|
|
世帯員数
|
漁業就業者数
|
|||
|
男
|
女
|
男
|
女
|
|
|
14歳以下
|
61
|
58
|
|
|
|
15-19
|
25
|
27
|
|
|
|
20-29
|
68
|
60
|
23
|
|
|
30-39
|
69
|
46
|
36
|
|
|
40-49
|
42
|
57
|
39
|
6
|
|
50-59
|
109
|
100
|
109
|
12
|
|
60歳以上
|
102
|
99
|
89
|
5
|
|
計
|
476
|
447
|
296
|
23
|
| 資料:第9次漁業センサス |
|
表2 当該漁協所属船の水揚げ額階層別・乗組員数別経営体数
|
|
水揚額階層別(万円)
|
|||||||||
| 計 | -300 | 300- | 500- | 700- | 1,000- | 1,500- | 2,000- | ||
|
シラス船曳網を行っている経営体
|
|||||||||
|
シラス船曳網漁業中心 乗組員数 |
計
|
71
|
1
|
1
|
3
|
4
|
15
|
11
|
36
|
|
1
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
||
|
2
|
|
1
|
1
|
3
|
3
|
14
|
8
|
12
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
2
|
20
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
シラス船曳網漁業以外中心
|
計
|
16
|
|
1
|
2
|
2
|
6
|
3
|
2
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
1
|
2
|
2
|
6
|
3
|
1
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
シラス船曳網を行っていない経営体
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2トン以上漁船所有
|
計
|
22
|
5
|
6
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
|
1
|
14
|
4
|
6
|
2
|
1
|
1
|
|
|
|
|
2
|
6
|
1
|
|
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
|
3
|
2
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
2トン未満漁船のみ
|
計
|
43
|
26
|
5
|
7
|
4
|
1
|
|
|
|
1
|
36
|
25
|
4
|
3
|
3
|
1
|
|
|
|
|
2
|
7
|
1
|
1
|
4
|
1
|
|
|
|
|
|
合 計
|
152
|
32
|
13
|
14
|
12
|
25
|
16
|
40
|
|
| 水揚のない経営体 |
計
|
8
|
|||||||
|
経営体合計
|
160
|
||||||||
| 資料:漁協資料及び聞き取り調査により作成 |
|
表3 聞き取り調査を行った漁業世帯の概況
|
|
漁家
|
乗組
|
乗 組 員 年 代(*:船主) |
漁船トン数
|
操業日数
|
水 揚 金 額(万円)
|
||||||||||
|
員数
|
父
|
夫
|
妻
|
長男
|
次男
|
弟
|
叔父
|
雇用
|
合計
|
シラス
|
貝桁
|
その他
|
|||
|
A
|
3
|
*60
|
40
|
10
|
|
雇40
|
|
|
4.95
|
177
|
2821
|
2407
|
414
|
0
|
|
|
B
|
3
|
|
*60 |
30
|
30
|
|
|
|
4.8
|
185
|
2568
|
2144
|
414
|
10
|
|
|
C
|
3
|
|
*50 |
|
20
|
雇40
|
|
|
4.97
|
185
|
2722
|
2289
|
414
|
19
|
|
|
D
|
2
|
|
*60 |
|
30
|
|
|
|
4.88
|
166
|
1200
|
847
|
353
|
0
|
|
|
E
|
3
|
|
*50 |
|
|
|
雇60
|
雇60
|
4.97
|
183
|
2609
|
2191
|
414
|
0
|
|
|
F
|
3
|
70
|
*40 |
|
|
40
|
|
|
4.9
|
157
|
2073
|
1610
|
414
|
0
|
|
|
G
|
2
|
*60
|
60
|
|
|
|
|
|
4.91
|
159
|
1278
|
913
|
365
|
0
|
|
|
H
|
2
|
*40
|
40
|
|
|
|
|
|
4.99
|
148
|
1317
|
956
|
354
|
0
|
|
|
I
|
2
|
*50
|
50
|
|
|
|
40
|
|
4.99
|
169
|
2504
|
1978
|
414
|
111
|
|
|
J
|
2
|
*60
|
50
|
|
|
|
|
|
4.9
|
169
|
1151
|
525
|
308
|
318
|
|
|
表4 漁業における労働時間状況(平常期)
|
表5 漁業における労働時間状況(盛漁期) |
|
|
| 資料:女性漁業者のくらしぶり、考え方についての調査(平成6年茨城県) | 資料:女性漁業者のくらしぶり、考え方についての調査(平成6年茨城県) |
| 茨城新聞切り抜き |
 |