【自主レポート】
|
ISO9001:2000 認証取得までの活動レポート 京都府本部/福知山市公営企業労働組合 松本美規夫 |
1. はじめに
2003年4月ガス水道部営業課に配属になり、ガス・水道に関するお客さまとの直接的な接点部分の業務に携わることになりました。
水道事業に関しては、日常業務のほとんどが供給者側の論理による業務の執行。閉塞した行政の独占市場の犠牲者に見えたお客さま。また、ガス事業に関しては、規制緩和、お客さまニーズの多様化などを背景とした他エネルギーとの競合による都市ガスエネルギー市場の縮小。民業圧迫どころか官業圧迫の様相を示している公営ガス事業者の民間ガス事業者へ事業譲渡している現状。今や市場に提供している価値がなくなれば、容赦なく淘汰されてしまう。すなわち市場であるお客さまが私たちを選ぶ、供給者側の論理からお客さま側の論理へと時代は変わっている。行政サービスを提供する現在の行政組織の仕組みやノウハウ、組織文化は、社会の常識やお客さまニーズから大きくかけ離れ、お客さまから徴収した料金に見合う行政価値がほとんど提供できない「過去の遺物」のようになりかけている。
公営のガス事業は、生き残れるのか?
社会経済環境は大きく変化しているのに旧態依然とした前例踏襲、変わらない縦割り行政組織、変わらない職員意識、その「つけ」が、現状を反映していることを日常業務を通じ肌で感じたことであります。
このようなことから2004年度ガス水道部営業課において自主研究グループを結成し、ガス水道事業の公営企業経営のさらなる永続的な発展という視点で、一般職員レベルで何ができるだろうという発想のもと活動をスタートし、まず現行の組織体制からのパラダイムシフトが必要であり、私たちが提供している行政サービスが、お客さまにとって価値あるものであると評価していただける、そんな行政サービスが提供できる仕組みやノウハウの構築が必要であると考えました。そこで「顧客重視」「継続的改善」などの基準を定めているISO9001:2000を社会的変化への対応、すなわち業務改善などの改革のツールとして取得したらどうかということで、ISO9001:2000自体の勉強、また先進自治体の取得状況などの調査研究を進めました。
しかし、他方では、ISOなどの企業経営のシステムが自治体運営に馴染むかどうかという議論もされておりますが、行政運営から行政経営をめざし、改革を行うために、企業経営の持つ成果意識やコスト意識を導入し行政のシステムを変化させようとする行動において、従来型の考え方での対応では、何らの変化をもたらさないと考え、同年度調査研究をまとめ、「お客さまにより満足していただけるガス水道事業をめざして」としてガス水道事業管理者へ業務提案を行いました。
2005年度当初、ガス水道事業管理者からISO9001:2000認証取得に向けてのゴーサインがあり、2005年7月11日、正式に認証取得にむけの取り組みがスタートしました。
2. ISO9001導入の背景
(1) 時代背景による現状認識
1市3町合併をはじめとする地方分権時代の到来、少子高齢化の進展や住民ニーズの多様化など行政サービスに対するニーズが拡大・多様化する一方で、財政事情、地方分権、情報公開など自治体を取り巻く環境は大変厳しい状況にあります。
ガス水道事業においては、ガス水道の普及促進といったガス水道供給施設の面的整備が最重要課題であった時代とは違い、サービス内容や質に対するお客さま意識の高まりやサービスに対するきちんとした説明、意見・要望の反映などが従来にも増して求められており、供給者側の視点でのサービス提供だけでは、お客さまの満足を得ることが難しい状況にあります。
このようなことから、ガス水道の供給という最低限のサービス水準を確保するだけではなく、お客さまの多様なニーズに対応でき、お客さまの視点に立ったサービス提供を行っていくためには、これまでの発想にとらわれない新たな視点で進むべき方向性を切り開いていかなければならないと考えます。
(2) 21世紀を展望したガス水道事業の方向性
私たちのすべての業務は、まずお客さまが満足するものでなくてはなりません。職員全員が確実にかつ公平に対応・判断・行動ができ、分かりやすく業務内容をすべて説明できるものでなくてはならないと考えます。
そのためには、質の高い行政サービスを効果的に効率よく提供できるシステムを創り、組織全体に浸透させ、全職員の行動レベルで現さなければならないと考えます。新たな行政経営スタイルであるNPM(ニュー・パブリック・マネジメント)の視点に基づき、更なるお客さま満足の向上をめざして、ISO9001:2000(品質マネジメントシステム)を一つの手段として導入し、職員の意識改革を図ります。そして、常にお客さま満足の向上という姿勢を追求し、日々の生活に欠くことができないライフラインとしてのガス水道の供給という私たちの使命を礎として、よりお客さまに満足していただけるサービスの提供と経営の効率化をめざすものです。
*1 NPM(ニュー・パブリック・マネジメント)とは、民間企業経営の考え方や手法を可能な限り行政へ導入し、公共部門の革新をめざす考え方です。
(3) 展開の概要
21世紀を展望した中で、NPMの視点に基づきその手法の一つでもあるISO9001:2000を導入し、お客さまに満足していただけるサービスの提供と経営の効率化を図ることができる経営基盤を構築します。(ISO9001:2000の規格の内容説明については、資料で後述しております。)
そして、構築されたその経営基盤の上に、NPMの有効な手法と言われている行政評価などを組み込んでいきます。
既存の枠組みの中に、NPMの手法である行政評価やPFIを導入しても、その新たな手法を受け入れるだけの経営基盤がなければ、本来の機能は発揮できないと言われています。
*2 PFI(Private Finance Initiative)とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい行政運営の手法です。
3. ISO9001認証取得の意義
ISO9001:2000は、お客さま満足、業務の継続的改善といったことを柱に規格が構成されており、お客さまから見て満足するものでなくてはならず、透明性や説明責任が求められるこれからの行政運営に有効な手法です。Plan(計画)・Do(実行)・Check(検証)・Action(改善)というマネジメントサイクル(PDCA)を繰り返すことにより継続的に業務改善することが要求されます。
ISO9001:2000は、行政サービスの供給者側の諸活動を体系化・ルール化し、マニュアルとして整備するものです。お客さまの視点に立った行政サービスを確立していくものであり、職員の意識改革を図りながら、お客さまに満足していただけるサービスの提供と経営の効率化を図ることができる経営基盤を構築するものです。
(ISO9001:2000の具体的な取り組み内容の概要については、資料で後述しております。)
4. 認証取得までの準備体制
(1) 調査研究
① 2004年ガス水道部営業課自主研究グループ4人(主任)による調査研究を実施。
② 先進地視察:すでにISO9001を認証取得している滋賀県栗東市(5人)・鳥取県鳥取市(44人)を視察し、取得に向けての視察研修を行いました。
また、事例研究についても既に認証取得している群馬県太田市、岩手県滝沢村、千葉県東金市、岐阜県美濃加茂市、滋賀県近江八幡市、大阪府枚方市、下関市水道局、福岡県水道サービス公社などの事例を研究材料としました。
(2) 推進体制
ガス水道部長を品質管理責任者とし、2005年6月11日に、認証取得に向けてのプロジェクトチームを立ち上げ、部内の横断組織(諮問機関であり実務機関)とするため、各課(4課)より2人を推進委員として選出し、品質マネジメントシステム構築、運用における各課の推進役として中心的な役割を担ってもらいました。(10人)
また、プロジェクトマネージャー:総務課長、サブマネージャー:営業課長としました。(2006年1月1日に旧3町を編入合併したため、人員変更あり。)また、ISOの取り組みに関する意思決定機関は、部内会議(管理者以下課長級職員の会議)に置きました。
(3) コンサルタント
認証取得においては、特に専門性があることから、民間コンサルタントを活用することとし、過去に自治体に実績経験のあるコンサルタント数社から本市の仕様に基づき企画書を提出してもらい、プロポーザル方式にて決定しました。
対象業者:(株)監査法人トーマツ環境品質研究所、ケイアイエス(株)、NPO法人認証取得支援機構ほか。
決定業者:ケイアイエス(株)
(4) 審査登録機関
日本適合性認定協会(JAB)認定の審査登録機関で、行政サービス、ガス及び水道の供給を審査できるのは、調査の結果、LRQA:ロイド レジスター クオリティー アシュワランスリミテッドと日本適合性認定協会(JAB)の認定はないが、イギリスの認定機関(UKAS)である(株)NQA-JAPANの2者による選考となりました。選定にあたっては、両者の企画書等を参考にし、JABの認定した審査機関であるLRQAに決定しました。
(5) 認証取得範囲の設定
ガス水道部4課の全業務。ただし、2006年1月1日に編入合併した旧3町の水道施設は、除きました。(拡大審査予定)
(6) 研修会等の開催(別紙経緯参照)
① 一般研修:全職員を対象に3回実施。
② 管理職員研修:係長以上を対象に2回実施。
③ 各課研修:随時開催。
④ 内部監査員養成研修(外部研修)3回(9人養成)
5. 品質マネジメントシステムの構築
(1) 品質マニュアル等の文書体系
ISO9001:2000の規格要求事項に品質マネジメントシステムの最上位文書(第1次文書)として、品質マニュアルを作成し、ガス水道部では、その品質マニュアルをFQMSマニュアルとして定めました。また、FQMSマニュアルを補完する文書(第2次文書)として18本の規定を定めました。さらに、第3次文書として、各課の全業務を統一の様式にて、個々のサービス提供のプロセスをフロー図と実施方法などで表した業務手順書(約300本)を作成しました。
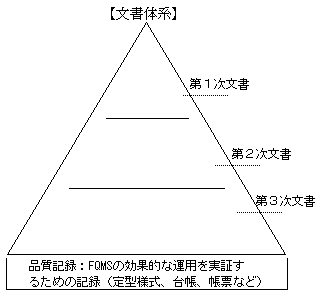 |
|
(2) 品質方針
| 福知山市ガス水道部は、お客さまの生活基盤(ライフライン)であるガス・水道の供給という行政サービスを通じて、お客さまにその価値(満足)を永続的にお届けするために、ここに品質方針を定め、確かなマネジメントシステムを構築し、絶え間なき改善によって「幸せが実感できるまち」の実現に向け全職員一丸となって協働して取り組みます。 1. 法令規則を遵守することはもとより、お客さまニーズを的確に把握し、その実現に向け常にお客さま本意の市政で考えます。 2. お客さまから信頼・期待される組織づくりと人材育成を行います。 3. 安全、安心、安定と安価で良質なガス・水道の供給ができるよう行政サービスの質の向上を目指します。 4. 改善の成果を検証するため具体的な目標を定め、常に業務を見直すことにより、マネジメントシステムの有効性の継続的な改善を行います。 この品質方針は、社会経済環境の変化やお客さまニーズの多様化に対応するため、必要に応じて見直しを行うとともに、全職員に周知徹底し、共有します。 平成17年10月1日 福知山市ガス水道事業管理者 蘆 田 昭 |
6. FQMSの運用
(1) 業務方針・各課品質目標の設定
福知山市ガス水道部業務方針 福知山市ガス水道部は、日常生活に欠くことのできないガス・水道水の供給を通じ、地域の発展と豊かな暮らしを支える公営企業として、公共の福祉の増進に寄与しているところです。 <基 本 姿 勢> 1 お客さま第一主義・現場主義 <業 務 方 針> 次のとおり業務方針を定め、推進します。 (各課において業務目標を定めます。) 1 安全・安心で良質なガスと水を確保します。 平成18年1月27日 福知山市ガス水道部長 岡 田 勝 一 各課品質目標
|
(2) 予備審査(2006年1月23日)
本審査に向けての審査対応のため予備審査を受審しました。文書審査のみではありましたが、重大な不適合はなく、品質マネジメントシステムの構築状況は概ね良好であるとの結果でした。指摘事項2件。
審査員:LRQA主任審査員1人
(3) ステージ1(文書審査)(2006年2月27、28日)
予備審査での指摘事項2件をフォローアップしました。品質マネジメントシステムの構築状況は概ね良好であるとの結果でした。指摘事項2件。
審査員:LRQA主任審査員1人
(4) 内部品質監査
内部品質監査は、ISO9001の要求事項8.2.2項に基づき、品質マネジメントシステムが品質方針、規格要求事項を満たし、効果的に実施、運用されているかを検証するために行うものです。内部品質監査に関する基準、方法等についてはFQMSマニュアルに基づき、内部品質監査規定に具体的に定め、それに基づき内部品質監査が実施される。内部品質監査員は、研修機関(外部)による研修を終了したものの中から、選任しました。
監査にあたっては、品質管理責任者(ガス水道部長)が、主任内部品質監査員1人を任命し、主任内部品質監査員は、監査チームの編成、リーダーの選任など監査全般にわたる指揮統括を行いました。
内部品質監査実施の年間計画では、年2回(9月、3月)の実施となっており、2006年3月13日に4課を対象に、品質マネジメントシステム構築後、はじめての内部品質監査を行い、FQMSの運用状況をチェックしました。今回の内部品質監査については、FQMSの柱でもある各課の品質目標の計画、実施、チェック、改善といったところを中心に監査を進めました。また、品質目標の達成状況、進行管理の状況なども合わせてチェックを行いました。監査結果の詳細については別紙のとおりです。また、指摘事項の概要については、次のとおりです。
|
|
(5) マネジメントレビューの実施
マネジメントレビューは、ISO9001規格要求事項5.6項に基づき、品質マネジメントシステムの適切性、妥当性、有効性を確実にするため、経営者が品質方針、品質目標をはじめとする品質マネジメントシステムの改善や変更の必要性について判断し、その効果を評価するものです。
2006年3月23日にガス水道事業管理者によるマネジメントレビューを実施しました。
☆ マネジメントレビューインプット情報
① 品質方針、品質目標の達成状況 ② 内部監査、外部監査の結果
③ お客さまからのフィードバック ④ プロセスの実施状況及びサービスの適合性
⑤ 予防・是正処置の状況 ⑥ 前回までのマネジメントレビュー結果に対するフォローアップ
⑦ QMSに影響を及ぼす可能性のある変更 ⑧ 改善のための提案に関すること
☆ マネジメントレビューアウトプット情報
(マネジメントレビュー検討表及びマネジメントレビュー見直し事項管理表による)
① QMS及びプロセスの有効性の改善
② お客さま要求事項への適合に必要なサービスの改善
③ 資源の必要性
(6) ステージ2(実地審査)
2006年3月27日~30日までの4日間LRQA主任審査員1人、技術専門家1人の計2人により実施されました。審査は、ガス水道部4課を対象に各係(11係)概ね半日単位の割り当てにより、各課の品質目標を中心に審査が実施されました。審査結果は、重大な不適合、及び軽微な不適合はなく、指摘事項1件でした。
7. 認証取得に要した費用(主なもの)
| ① コンサルタント業務委託料 | 2,625千円 |
|
| ② 審査登録料 | 2,070千円 |
|
| ③ 内部監査員養成研修費用 | 169千円 |
小計4,864千円 |
| *日本ガス協会からの補助金 | 775千円 |
|
| (経営力強化のための財政支援制度) | ||
合計4,089千円 |
8. 認証取得及び取得範囲の拡大
(1) 認証取得について
① 適用規格 :ISO9001:2000・JISQ900:2000
② 認証登録日 :2006年4月5日
③ 有効期限 :2009年4月4日
④ 審査登録機関:LRQA(ロイト・レジスター・クウォリティー・アシュワランスリミテッド)
⑤ 登録範囲 :ガス及び水道の設計・製造及び供給
⑥ 対象施設、人員数:福知山市ガス水道部庁舎・福知山市ガス基地を含むガス供給施設・水道供給施設、78人
⑦ 認定機関 :日本適合性認定協会(JAB)・英国認定機関(UKAS)
(2) 取得範囲の拡大
2006年1月1日に編入合併した旧3町の簡易水道施設についての拡大審査が必要になります。その時期は、6ヶ月ごとに実施される定期審査(サーベイランス)に合わせ拡大を図って行く予定です。
9. 今後の取り組み
2006年度の推進体制は、各課より2人の推進委員を選出し、品質管理責任者を統括責任者としてFQMS運用の推進を図ります。
① 各課における2006年度の品質目標の設定
② FQMSの運用研修の実施
③ 内部品質監査の実施
④ 不適合、是正、予防処置による業務改善
⑤ マネジメントレビューによるFQMSの見直し
⑥ 審査機関による定期審査(サーベイランスの実施)2回
⑦ FQMSへ行政評価システムを組み込んでいくための調査研究
10. おわりに
今、地方自治体は、分権時代の流れの中、自己決定・自己責任の原則により、自立した自治体経営が求められています。本市においても2006年1月1日に周辺3町を編入し合併しました。合併の目的は、社会経済環境の変化に対応するための行政体制の整備であって、財政的な問題は、合併を進めるための住民への説得材料に過ぎないと考えます。しかし、三身一体改革の様々な影響は、人員削減、予算削減などの従来からのその場しのぎに見える短期的な行政改革での対応は、行き詰ってしまう。正にこれまでの枠組みを越えた行政改革が必要であると考えます。
また、地域の自立と自治体間競争が当然のこととなるであろう分権時代では、組織経営はさることながら、地域経営が要求されニューパブリックマネジメントや経営、マーケティング、マネジメント、評価、継続的改善といった経営概念は、21世紀の自治体職員に必要な基本知識の一つになると考えます。
そして、2006年4月5日福知山市ガス水道部は、ISO9001:2000を認証取得しました。(府内の公共機関では初の認証取得)経営というノウハウを持たない行政にとってこのISO9001:2000は、取得の目的を明確にし、全職員一丸となって取り組み運用すれば、大変効果的なマネジメントツールであると考えます。
ISO9001:2000を経営戦略としニューパブリックマネジメントの基幹システムとして経営基盤の構築を図り、お客さまに満足していただける価値ある行政サービスを提供できるような『価値創造公営企業 福知山市ガス水道部』をめざすことが今、私たちに求められており、お客さまのニーズにあった価値ある行政サービスを提供し続けることが、お客さま満足の向上に繋がり、「お客さまにより満足していただけるガス水道事業をめざして」今、そのスタート地点に立ったばかりであります。
【資料】ISO9001:2000について
1) ISO9001:2000とは
ISO9001:2000とは国際機関である「国際標準化機構(International Organization for Standardization)で制定している国際規格の一つで、組織(会社や自治体など)がお客さまに対して、一定の質の製品やサービスを提供するための「仕事のしくみ(システム)」=品質マネジメントシステムを創るためのもととなるルール(規格要求事項による)を定めたものです。改訂前の規格ISO9001:1994(年版)は、物自体の品質をとう品質システムと言われておりました。
改訂後の規格ISO9001:2000(年版)品質マネジメントシステムには、「顧客満足」「継続的改善」「リーダーシップ」「プロセスアプローチ」「マネジメントへのシステムアプローチ」「意思決定の事実に基づくアプローチ」「人々の参画」「供給者との互恵関係」の8つの原則があり、これらを基礎としてPlan(計画) Do(実行) Check(確認) Action(改善)のマネジメントサイクルを繰り返すことにより継続的改善を図り、より効果的なシステムへと向上させることをねらいとしています。
2) ISO9001:2000の考え方
製造過程の品質管理から管理システムの品質保証へ
改訂前ISO9001:1994版では、製品をつくる際に、発注者から要求された仕様・条件を満たしているかを自己チェックできる体制であることを保証する規格でした。
改訂後ISO9001:2000版では、顧客(市民)の満足を継続的に向上させるための計画、実行、確認、対策が確実に実施されているかを審査(プロセスを管理する手法)するものです。
3) ISO9001:2000とは! 具体的に!
ISO9001:2000の規格は、製品やサービスの品質そのものを規定しているものではなく、製品やサービスを提供する企業がお客さまに満足していただける製品やサービスを提供する能力や仕組み、すなわち組織構造、手順、プロセスなどをきちんともっているかを確認するための基準を定めたものです。
この仕組みのことをISOでは、「品質マネジメントシステム」と呼んでいます。
4) ISO9001:2000の活動とは?
会社などの組織がお客さまに提供する製品やサービスの品質を確保することによりお客さまに満足していただこう、また、そのような組織になるために組織を変えていこうという活動です。まず、経営者による経営方針のもと、経営資源を配分し、仕事の進め方を定めます。定めたとおりに仕事がなされたか、また、サービスの提供によりお客さまが満足されたかをチェックし、経営者に報告します。経営者はそれらすべての情報を受け、必要に応じて組織全体を見直し、次の手段を考えます。それを繰り返すことにより組織を継続的に改善進化しようとする活動です。