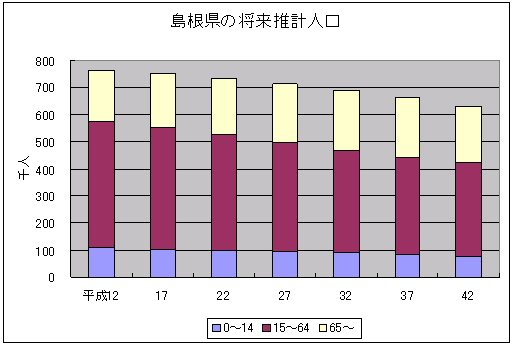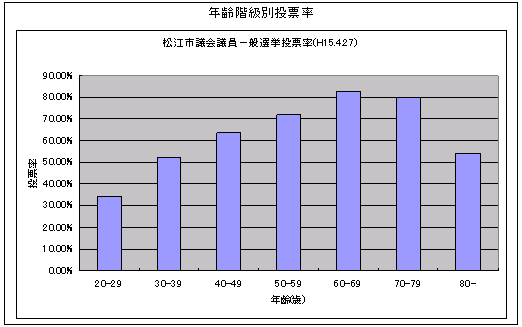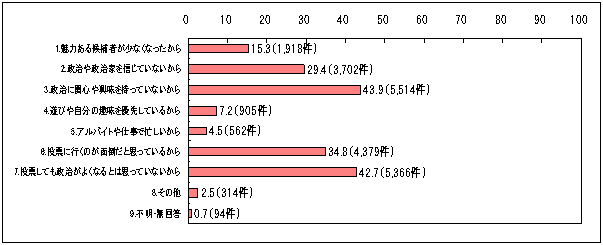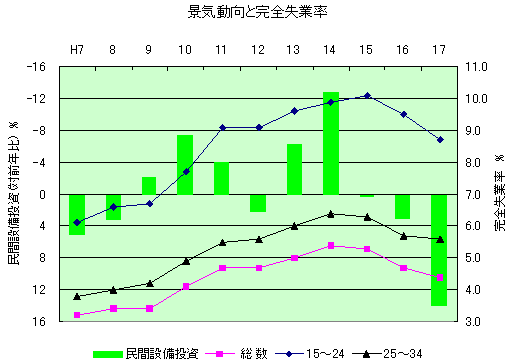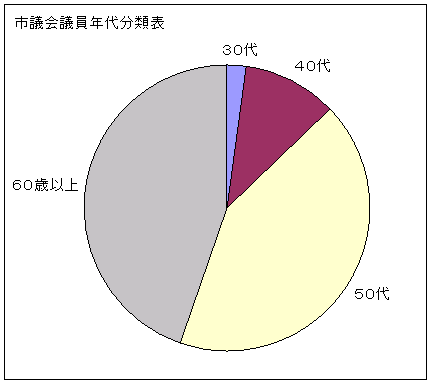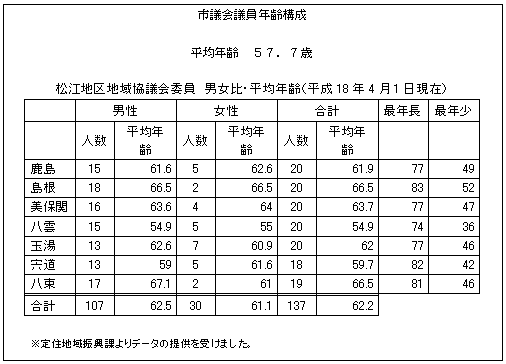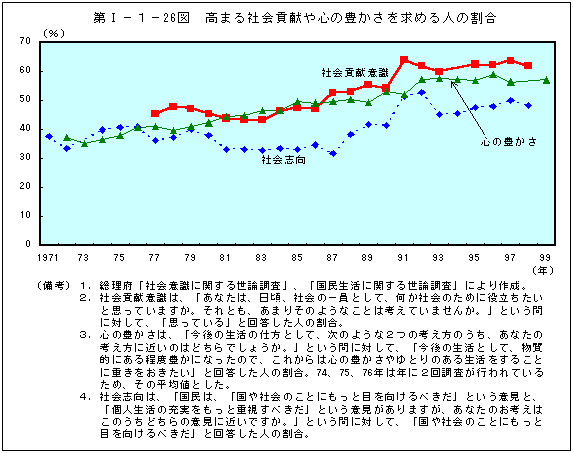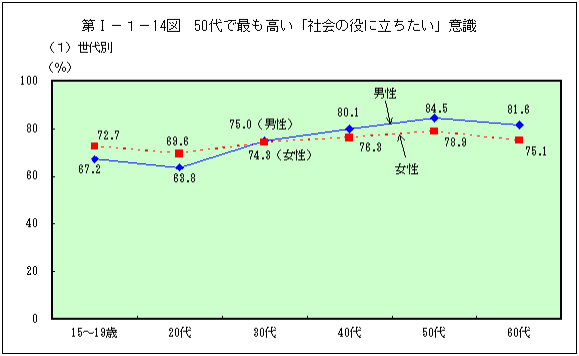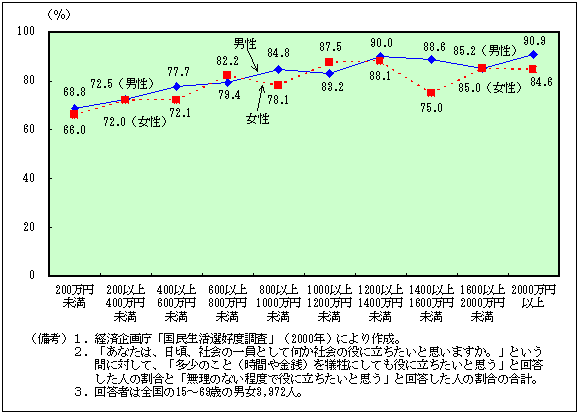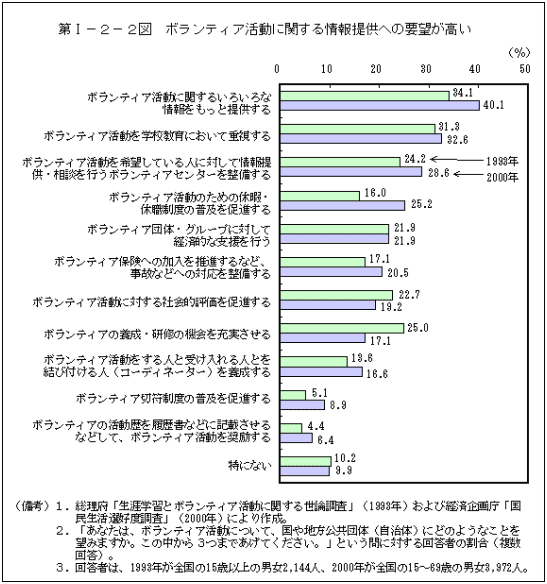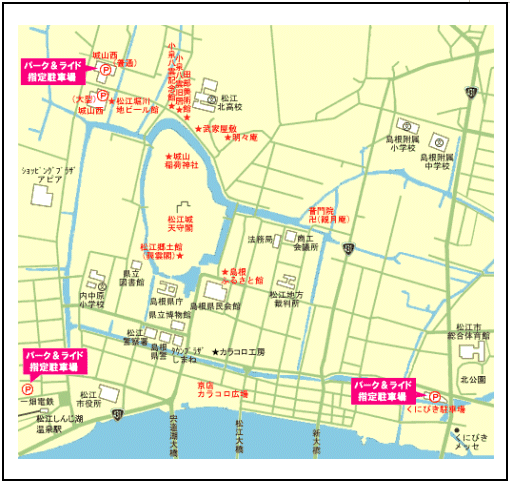つまり、何らかの形で社会の役に立ちたいと思ってはいるが、情報が少ないために、ボランティアに参加するチャンスを失っている状況にあると言える。
これを逆手にとって、市民に十分な情報提供を行い、行政と市民とが協働的にまちづくりを行っていく社会、すなわち「ボランティア都市日本一!!」を提言する。
具体的には、ボランティア活動の募集等の専用ホームページ(サイト)、ボランティア専門冊子の作成、更に広報誌への専門ページの掲載、市報と併せるなどして、全戸に情報が行き渡らせることが必要である。
また、提供した情報に対する活動支援の場として、ボランティアセンターの充実も求められる。
事業内容としては、ボランティアに関する相談、紹介、講座、イベントの実施、活動場所の提供、ネットワーク作り、ボランティア保険、行事保険の取り扱い窓口等が想定され、個々の活動が成熟・専門化してくれば、行政との連携のもとで、高度な次元でまちづくりへの参画も期待できる。
さらに、ボランティアの参加率を上げるために、参加者に対し、ポイントを付与するシステムを導入する。ポイントカードをつくり、貯まったポイントにより、個人レベルではゴミ袋への引き換えを行えたり、団体レベルとなると、遊具との引き換えも可能で、小学校への寄贈などもできるのである。
加えて、貢献度・難易度によって、ポイントに差異をつける。県外の各種活動に参加する場合は、ポイントの距離比較による割増を行う。「旅行のついでにポイントゲットしてきました。」という話にもなる。更には、その場所での交流という副産物も生まれる。
最後に社会に貢献し、関わりたい人たちのボランティア活動を推進することで、ボランティア活動者の心の満足度指数を高めることができ、個人の最低限の支出、各種団体負担費用などを軽減できるシステムを目指すものである。
3. 給食無料化
近年、給食費の滞納が全国的に問題となっている。長引く不況により生活が苦しく、学校給食費が払えない事が大きな原因らしい。
松江市の学校給食でも同じで、滞納が問題になっている。
今の学校給食は、「食べられればいい、おいしければよい。」というだけでなく「食育」として、目の前の給食がどのように作られ、食材それぞれの栄養分などを理解し、どこでどのように作られるかを学んでいる。なるほど、これは立派な教育である。言うまでもなく、給食のある小・中学校は義務教育である。小・中学校で教える「学問」や「社会性」と同じように「食育」も同じ「教育」なのに、授業料は無料、給食費は有料というのはおかしいと思う。
近年、学校内での「いじめ」が大きな問題になっている。
今の日本は、格差社会になってきたと言われており、今後ますます格差は広がっていくと言われている。
「いじめ」の原因の一つが、この格差であると考えられる。家庭の事情でやむを得ず給食費を滞納せざるを得なかった生徒が「いじめ」られるというケースもあるはずだ。本人の問題でなく、家庭の事情で学校生活が辛いものになるのは、とても悲しい事である。
以上のようなことから、「学校給食は教育の一つである。また、すべての生徒は明るい学校生活を送る権利がある」と考えるならば、学校給食費は家庭から徴収するべきではないと考える。
しかし、当然の事だが学校給食費が徴収できなければ、一食あたりの単価が落ちてしまい、質が悪くなってしまう。それでは育ち盛りの子ども達があまりにもかわいそうである。そこで、不足してしまう給食費を補うため、以下のような対策を考えた。
① 各給食センターに一般市民向けの食堂を設置する。
② 今の食材費を値上げする。
③ 島根県職員、松江市職員は給食にし、給料引きにする。
小・中学生時代は当たり前に食べていた給食も、大人になると、食べる機会がほとんど無く、「昔を思い出したい」「昔とどれだけ変わったのか」などと思いお金を払って食べたいと思う人は少なくないはずだ。都会では、給食専門の食堂もあるくらいだ。また、普通の食堂とは異なり、あくまでも作りすぎた給食を販売するため、今より経費がかかる事は無い。場所も、各給食センターの会議室を利用すれば、新たに建物を作る必要性はない。また、各給食センターの売り上げが出るので、各給食センター間での競争意識が出る。そして、よりおいしい物を作るという意識が今以上になると思われる。
今の給食の一食当たり単価は約250円、ランニングコストも考えると一食当たり1000円になる。松江市の小学校の生徒数は約13,200人、教員数約1000人、中学校の生徒数は約6,700人、教員数約600人である。合計約21,500人である。これに食材費250円を掛けると5,375,000円の徴収し、すべての経費を考えると21,500,000円掛かる事になる。
| |
生徒数
|
教員数
|
合 計
|
|
小学校
|
13,200
|
1,000
|
14,200
|
|
中学校
|
6,700
|
600
|
7,300
|
|
合 計
|
19,900
|
1,600
|
21,500
|
|
食材費
|
250円
|
総経費
|
1,000円
|
|
|
×21,500
|
|
×21,500
|
|
|
5,375,000円
|
|
21,500,000円
|
|
|
差 額
|
16,125,000円
|
|
これに対して食材費を値上げし、一食当たりの食材費を500円とする。市職員約1,500人も給食にして、一般市民へ400食販売する。そして、食数が増え、無駄な食材も減るので一食あたりの単価が下がり、750円になったと仮定すると下表になる。
このようになれば今現在よりは差額が少なくなり、松江市の財政的にも良いことがわかる。しかも、今後より効率的に給食運営することにより一食当たりの総経費も下がる。
これらの実現には給食法などの難題が多くあるが、学校給食を無料化することによって、松江市の少子化問題に歯止めが掛かるはずであるし、全国的にも注目され、知名度が上がり、観光客の増加も見込まれることから是非、実現して欲しい。
4. 松江市の自動車事情について
松江市には自動車が多い。人口に対する自動車の所有率はかなり高いのではないだろうか。
松江市はノーマイカーデーと称して、毎月1日・20日はマイカー通勤の自粛を呼びかけているが、はたしてどれだけの成果があるのだろうか。
決して車の交通量が減っているようには見えない。むしろ、わが松江市役所の職員でさえ、多くの人が1日・20日も平気でマイカー通勤しているのではないか。
考えてみて欲しい。では、なぜマイカー通勤が減らないのか。
それは明らかに、公共交通体系が充実していないことだと考えられる。
都心部のように次の駅まで歩いていけるくらい地下鉄線が張り巡らされていれば、マイカーでなくとも通勤は容易だ。
では松江はどうか? 例えば島根町の人が、市街地に公共交通機関で通勤するならばバスしかないはずだ。では、バスがどれだけ通勤に適しているのかと言えば、決して便利と言えるものではない。通勤に便利なバスがあればいくらでも通うけど・・・と思っている人たくさんいるだろう。
本当にそんな人がバスを利用するなら、路線を増やしたりダイヤ改正をして1日何本も走らせても採算が取れるだろう。結局は卵が先かニワトリが先かという話になってしまう。
| |
生徒数
|
職員・一般人数
|
合 計
|
|
小 学 校
|
13,200
|
1,000
|
14,200
|
|
中 学 校
|
6,700
|
600
|
7,300
|
|
市 職 員
|
|
1,500
|
1,500
|
|
一般市民
|
|
400
|
400
|
|
合 計
|
19,900
|
3,500
|
23,400
|
|
食 材 費
|
500円
|
総経費
|
750円
|
| |
×3,500
|
|
×23,400
|
| |
1,750,000円
|
|
17,550,000
|
| |
差 額
|
15,800,000円
|
|
松江市は城下町の面影を残した情緒あふれるすばらしい街である。だから、自動車量が気になる所でもあるのだ。
そこで提案する。松江市完全パークアンドライド化を。
現在観光向けのパークアンドライドはあるが、今回は通勤用に、駐車場を市街地郊外に作ることを想定する。
そして、そこからの公共交通機関を充実させ、市街地は指定車両以外通行禁止とする。時間制の交通規制でもいいかも知れない。
とにかく、自家用車では市街地は走れなくして、代わりに人力車等を走らせてみて、観光に役立ててみるのも一つの手かもしれない。個人の心がけで車を減らすノーマイカーデーより、むしろ強制的に車を排除し、有無を言わせずバス通勤にすれば、松江市は日本を代表する世界に誇れる真の国際文化観光都市と言えるだろう。
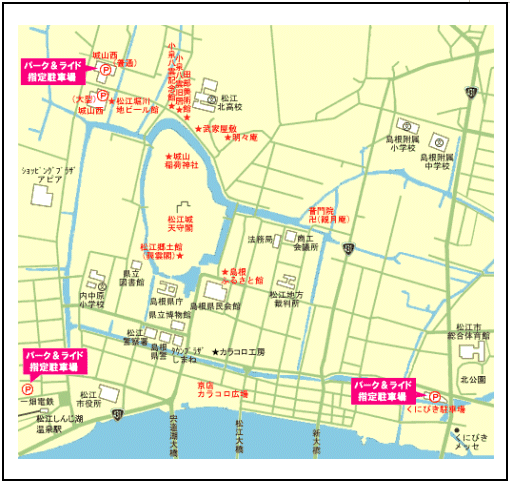
5. 理想的な庁内について
松江市は、2005(平成17)年3月31日に市町村合併をした。合併を行い、多様化する市民ニーズに答えるべく、組織機構の編成が行われ、新しい課が設置され、1課当たりの人員も増えた。そして、庁舎内での課の移動があった。また、合併にともない、旧町村役場の人数は激減した。
松江市役所本庁舎には、毎日大勢の市民の方が、来庁される。初めて来庁される方、足の不自由な方、高齢の方、障害を持っておられる方などいろんな方が、来庁される。そしてよく、来庁された市民の方々が手続きのため、庁内を行ったり来たりする光景を見る。市民サービスを向上させるためにこの点を改善しないといけない。また、旧町村役場は職員数の激減、旧町村時代の議場など多数の空き部屋がある。これらの部屋のほとんどが有効活用されていない。しかも、職員数が激減したため、役場付近が寂れたという声も聞かれる。
今現在の庁内配置を見ると、部単位でまとまっている感がある。これでは市民本位の配置では無く、市役所本位の配置である。本当に市民サービスをするなら、庁舎内での移動距離を最小限にとどめ、始めて来た人でも分かり易いような庁内配置にしなければならない。また、旧役場を有効活用し、町の活性化をしていかなければならない。
来庁される方を来庁目的別に調査し、1回の用事で何処の窓口に行かないといけないかを調査する。
現在の窓口待時間を調査し、現在の窓口数で十分かを調査する。
支所の空きスペースにどのような施設が欲しいかアンケートを行う。
これらを調査し、庁舎滞在時間を短縮することで、少ない来庁者用駐車場を効率よく使い、旧町村の活性化を狙う。
調査結果を元に、部や課を超えた理想的な配置を考える。
窓口待ち時間が長い所は、カウンターを大きくして職員を増やし、適切に対応できる体制をつくる。
アンケート結果を元に現実的でかつ、有効なもの(コンビニ、居酒屋、市営住宅等)を支所へ配置する。
以上、我々ユース部で自由に話し合った結果出た意見の一部です。
現実性の高いものから低いものまで、いろいろありますが、人の思いというものは、そういったものであって、特に、経験の浅い若年層から出る意見というのは、一見すると取るに足らないものという印象を持たれるかもしれません。
しかしながら、それを精製していく過程で、今、松江市が抱えている問題に一筋の光をもたらすものとなる可能性を秘めています。
問題は、「若い者が好き勝手に言っていることだ」で終わらせるのではなく、若者ならではの着眼点や発想を、これからのまちづくりに生かしていくためのシステムが必要なのです。
そういったアイデアのどこかに有益なものがあるのではないか、あるのだとすれば、それをどうやって今後に繋げ、発展させていくのかを考える場が求められています。
そこで、ユース部が提案するのは「若年層で作る第2の議会」です。
まずは、議員の構成から考えていきます。
単に若年層の議会といっても現在あるステージを構成する人と重複してしまっては、現在の既成概念から脱却することが難しくなり、経験豊富な人間が議員構成の大半を占めるようでは新たな取り組みとしての意味合いが薄れてしまいます。
前述のように、市議会、地域協議会ともに、40歳以下の構成員が非常に少ないことから、年齢の上限は40歳で設定するべきだと考えます。また、下限として設定する年齢は、参政権と同じく20歳が妥当と考えます。
次に選出方法ですが、1つの方法として選挙が考えられます。
しかしながら、選挙を行うには、市の独自の取り組みであるため、その費用は市が全額負担する必要があるため、現状では、現実性を失ってしまいます。
また、候補者についても、比較的低所得な年齢層である上、社会的立場や家庭における子育てなど、経済的にも時間の上でも非常に大きな負担を強いることとなってしまい、立候補したくても断念せざるを得ない状況が生じることが予想されます。このような理由から選挙は望ましくないと考えられます。
そこで、議員の選出に関しては、様々な視点から多くの意見を集約するためにも、市内で活躍する各種団体、グループから選出していくことが適切ではないかと思われます。
例えば、連合加盟の団体の代表、商工会議所や商工会等の青年部、各公民館や自治会等の青年活動団体、学校や幼稚園の保護者会、ボランティア団体からの代表、その他NPO法人や市民団体等から代表を選出してもらうのが妥当です。
選出議員に対する報酬については、年額1~2万円程度の各種審議委員会等と同等の報酬を設定するのが妥当です。基本的には職業との位置付けはせず、市議会議員と異なり公務員としての扱いはしないこととします。
任期については、通常、各種審査委員会等の委員の任期は1年程度が通例です。
しかし、この議会は政策にも意見を反映させていく必要があり、議会同等の扱いをする必要があるため、市議会にあわせて、4年任期にするべきだと考えます。
また、在任資格については、任期中に40歳を過ぎた場合を考えると、年齢構成が曖昧となり、将来的に本来の趣旨に反した会になる恐れがあるため、任期中に40歳を超えないものと設定すべきです。
議会の開催期間等については、本来の市の政策を決定する市議会の運営を妨げないように設定していかなければなりません。しかし、この議会で決定された事項や政策への意見等が政策や予算にほとんど影響を与えないようでは、この議会を設置したことが無意味となってしまいます。
よって、まずは10月の開催が望ましいと思われます。9月議会閉会後ということでほぼ年度内の予算や事業計画が確定している段階であり、新年度予算作成前の時期でもあるため、次年度への事業策定にとって最も相応しい時期と考えられます。
また、もうひとつの開催時期としては4月が望ましいと考えられます。
この時期は年度当初ということもあり、その年度の日程等を決めることができ、前年度事業の審査を行うことにより該当年度以降への継続審議や、修正点等の策定ができます。
そして、3月議会閉会後ということで、議決された議事や予算を踏まえての該当年度の事業計画や、その年度に策定し次年度以降に施行していくべき事業等を決定していくことができます。
先述のとおり、この議会の議員は家庭も経済的に厳しく、子育て等で時間もなく非常に多忙な年代です。また市の財政負担も最小限に抑えたいことから、日程自体を最小の日程で行う必要性があります。
よって、日程については基本的に休日を利用した日程にしていくことが望ましいと考えます。
しかし、市の政策や予算に対して影響を与えるものとしていくことを前提とした議会であることから考えると、やはり委員会を開催し慎重審議を行うことが必要です。
すなわち、必要な日程は、本会議に2日、委員会に1日であれば必要最低限の日数は確保できると考えられます。
ただし、このような開催回数で行った場合に本当に政策等に影響を与えるような内容になっていくのかという問題点はあります。この問題には、月1~2回程度の分科会を行うことで日程不足を補っていけばよいのではないかと考えます。基本的な事項はすべて分科会で策定していき、本会議及び委員会は分科会で決められた事項に対しての審議をする場として位置付ければこの日程での会期も可能となります。
本会議及び委員会の運営の方法については、市議会と同等のもので行うことが必要です。
本会議においては、市長はじめ市の四役、各部長及び教育委員会部局が対応します。
議会と異なり、強制力を持たない機関であるとはいえ、やはり市制について真剣に討議していく場であるので、市の側としても市議会に同等の扱いをすることでこの議会の価値を高めていく必要があるからです。
また、市議会議員は原則としてこの議会を傍聴することとし、当然のことながら決定事項を市議会でも審議するものとします。委員会についてもやはり市議会同等の対応をします。
ただし、委員会は、議員にとってもっとも身近であると思われる常任委員会のみを設置し、1議員1委員会を役割とします。
なお、市議会には特別委員会もありますが、議員の負担が大きくなること、また、この議会で決定すべき内容ではないと考えるため、現段階では必要ないと考えます。ただし、経年の上、この議会でどうしても設置する必要性が生じた場合には設置することも検討すべきでしょう。
分科会の運営方法については、市議会にはない機関のため、独自に考えていく必要があります。
先に述べたとおり、この議会の主な事項は分科会で決め、その最終判断を委員会、本会議で決定をしていくことから、この分科会が最も重要な機関になるといえます。
この分科会の構成としては、市役所各部単位が妥当です。
また、必要があれば課単位での分科会も作る。議員は、各分科会に1~2人を配置することにします。更に、この分科会には関係部課の同年代の職員を分科会の委員として配置します。
そして、この議会には多くの市民の意見を反映できるような組織を作っていきたいと考えます。
よって、この分科会には一般の市民にも参加してもらいます。各分科会に数名所属することとし、議員、市職員、一般の住民の計10人程度で分科会を運営していきます。
分科会は少なくとも10程度つくります。分科会の開催については、各分科会の判断によりますが、少なくとも月に1回以上は開催するよう義務付けます。一般の委員の選定については、公募することが望ましいと思われます。議員と異なり、一般委員の任期は1年とします。
このように分科会を構成するわけですが、問題はどのような内容を話し合うかです。
分科会には一般の市民が100人以上も参加することとなるため、やはり身近に感じる問題を提起していく事が基本となると思われます。市職員も委員として参加しているので、分科会の中で解決できるものは対処していくことも可能となります。
よって、分科会で決定し、本会議で審議を行う事項については、その時点では解決できない事項等の解決案や、新たに必要と思われる事業等を提案していくことになると考えられます。
この議会を作ることで、どのような効果が得られるかを考えてみると、まずは、議員の存在です。この議会の議員は、若年層の考える様々な意見や考えを集約することができます。
将来的には、この議会を代表し、市議会議員になることも可能です。この議会の代表が市議会議員になるということは、若年層の意見を市議会へと反映させることができるということです。
続いて、この議会に参加した職員です。
一般の市民と話し合いの場を持つことで、住民がどのようなことを考えているか知ることができ、行政にその意見を反映させることができるようになります。
また、この分科会で新たな事業が決まった場合、その事業の担当者となることで、責任を持ってその事業を遂行していくことになります。人事面でも配慮を行い、その担当者は事業が完了するまで、異動をさせないことも考えていく必要があります。
そして、分科会に参加した、一般の委員です。
一般の市民がこの議会に参加することは、市民の行政参加を推進することとなり、行政と市民が一体となったまちづくりに期待が寄せられます。また、任期を1年とすることで多くの市民の意見を聞くことができます。
また、そのような場を提供するということは、市民の行政への興味を引くこととなり、若年層の政治・行政への関心を高めることができます。
このように、この議会を作ることで様々な効果が得ることができると考えられます。
しかし、ここで得られる効果は、必ずしもこの議会に参加した人間には限りません。
この議会を行うことは若者が自分たちで住みよいまちを作り上げていけることになります。
若者たちが作った住みよいまちには、若者たちが集まってくることになるので、定住化の促進につながります。
実際には理想どおりにいかないかもしれませんが、若者たちにこのようなステージを与えることは、悪いことではないと思います。
自分たちのまちについて、真剣に考え討論する場を与えれば、必ず松江市にとって明るい未来の扉を開く鍵になっていくでしょう。 |