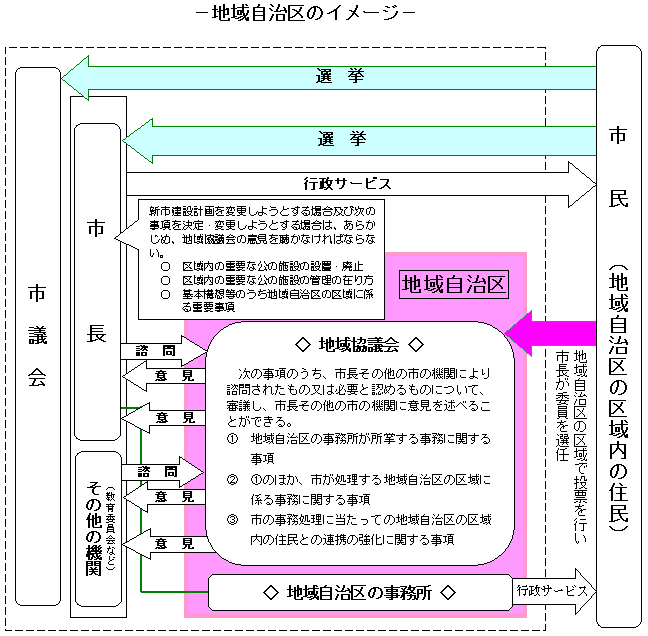【要請レポート】
|
住民自治の充実に向けた新たな取り組み 新潟県本部/上越市職員労働組合 |
1. はじめに ~上越市の紹介~
上越市は、新潟県の南西部に位置し、日本海に面しています。面積は973.32km2、人口21万人あまりとなっており、2007年4月1日に特例市への移行を目指しています。
国の重要港湾である直江津港を有するとともに、高速道は上信越自動車道と北陸自動車道が上越JCTで、鉄道は信越本線、北陸本線、ほくほく線が直江津駅で結ばれ、日本海側(北陸地方)と太平洋側(関東地方)の交通の要衝として重要な役割を果たしています。さらに、建設中の北陸新幹線が2014年(予定)に開通した際には、距離的、時間的にも首都圏に一番近い日本海に面した都市となります。
合併対象の旧町村の多くが過疎地域であったことから、合併後の上越市全域が過疎地域に指定され、「全国一人口の多い過疎地」となっていますが、地域が持つ豊かな自然とその恵みに育まれた個性に再び光を当て、「海に山に大地になりわいと文化あふれる共生都市上越」を合言葉に、より力強く自主自立が可能なまちづくりを目指しています。
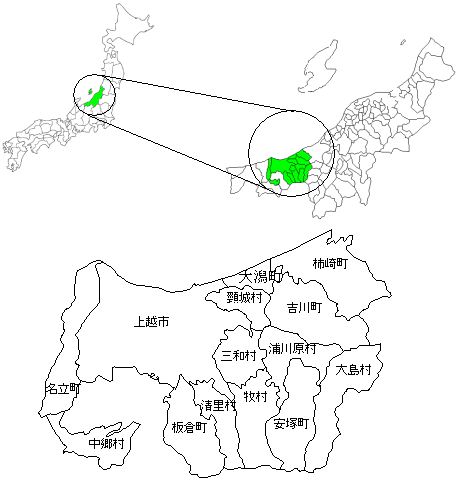
2. 合併と地域自治区設置
(1) 合併への経緯
2000年1月、1市3村による「市町村合併に関する勉強会」が設置され、合併に向けた協議がスタートしました。その後、「任意合併協議会」、「上越地域法定合併協議会準備会」へと進む過程で10町村が加わり、最終的に14市町村が参加した「上越地域合併協議会」を経て、上越市への編入方式により、2005年1月1日に合併が実現しました。
(2) 地域自治区
合併協議の結果から、合併前の上越市を除く旧13町村の区域ごとに、地域自治区が設置されました。
これは、地域住民の意見を聴き、その声を新市の施策に反映させていくことを目的とした地域協議会の設置を模索した中で、この地域協議会を各地域に設置するための手段として導入された制度です。
地域自治区は、2004年の地方自治法改正により創設された地域自治組織の仕組みですが、上越市に設置した地域自治区は、合併市町村に対する特例措置としての旧「市町村の合併の特例に関する法律」に基づいています。
各地域自治区には旧町村役場を転用した事務所が置かれ、○○区総合事務所(○○区は地域自治区の名称)として、区域内にかかる事務や地域住民に密接に関わる行政サービスのほか、地域協議会に関する事務を行っています。
また、各地域自治区の名称及び各区域内の住所には、旧町村の名称を使用し、合併後も旧町村名が残されています。
地域自治区の設置期間は、不均一課税などの特例期間が概ね終了する5年間とし、期間終了後の取り扱いについては設置期間中に検討することとしています。
3. 上越市における地域協議会
(1) 地域協議会の目的と役割
地域協議会は、市長の附属機関であり、地域自治区の区域にかかる市の事務などについて、地域住民の視点で意見を述べることを期待されています。
市長は、地域に関する事務のうち重要なものについては、地域協議会の意見を聴くこととされており、
○ 新市建設計画にかかる地域自治区域内の地域事業の変更
○ 地域自治区域内の重要な施設の設置・廃止、管理の在り方
○ 基本構想等のうち地域自治区の区域に係る重要事項の決定・変更
については、合併関係市町村の協議により定められた「地域自治区の設置に関する協議書」において、市長が地域協議会に諮問し、意見を聴くことが義務とされています。
さらに、地域協議会は地域の課題を自主的に審議し、その結果を意見書として市長に提出することもでき、これら役割から、地域に関わる市の施策決定に対し重要な役割を担っていると言えます。しかし、事務執行権は付与されていないため、意見を述べるのみの機関であるとも言え、必ずしも地域協議会の意見どおりに施策が決定されるものではないという側面も重要な特徴と言えます。