【自主レポート】
|
地方の視点で「少子化対策」を考える 群馬県本部/藤岡市職員組合「少子化対策」を考える会 |
1. はじめに
最近、新聞等で「少子化対策」「子育て支援」の文字を目にすることが多くありませんか? 年金や国の財政を論ずるときに「このまま少子化が進めば出生率が減少し、年金(財政)は立ちゆかない。」なんていう風に取り上げられることが多いようです。2006年に入ってから児童手当に関する法律が改正された時は「額が少ない」「いや十分」「安易に増やしていいのか?」といった議論が行われていました。
2005年度の厚生労働白書を見てみると次のような文章が掲載されています。
「2004年の合計特殊出生率は、過去最低の水準を更新した2003(平成15)年と同率の1.29となった。現在、我が国の出生率は、南欧諸国やアジアのNIES諸国などとともに、国際的にみても最も低い水準となっている。これは、子どもや子育てをめぐる現在の状況を変化させるためには、これまでにとられた対策のみでは十分な効果を挙げるにいたっていないということを意味している。(中略)①「若者の自立とたくましい子どもの育ち」、②「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し」、③「生命の大切さ、家庭の役割等についての理解」、④「子育ての新たな支え合いと連帯」の4つの重点課題を設定した。」(『第1章 第1節 次世代育成支援対策 1 「少子化社会対策大綱」及び「子ども・子育て応援プラン」の策定』より)
今までの政策は十分ではなかった、もっと対策を強化したいという意図が感じられます。重点課題についてもいうことはありません。児童手当の範囲拡大および所得制限の緩和もこの流れに沿って行われたのでしょう。しかしこれで出生率は上がるのでしょうか?
私の周りを見渡してみても、子育て支援の政策が充実したから出産・育児を決意したという人はほとんどいません。聞こえてくるのは見通しがきかない将来への不安ばかりです。
「『子育て支援』に関する政策は本当に効果があるのか?」「そもそも現在のような児童福祉の制度が成立したのはいつからだろう?」といった疑問が湧いてきたので、自分なりに調べてみました。
2. 日本の児童福祉の歴史
明治時代以降で考えてみると少子化対策よりはむしろ産児制限などの印象が強かったりします。何しろ避妊に関する知識と道具が広まったのは戦後以降のことであり、それ以前は「子どもを産まないためにはどうしたらいいか、産む場合には丈夫な子どもを産みたい」ということの方が問題でした。たくさん産んで、死亡率も高いという「冷たい方程式」が成り立っていたわけです(図1、図2参照)。政府も出生率には着目していましたが、これは「富国強兵」をめざす中で、安定した税収を確保し、徴兵制を維持するのが目的だったようです。1941年には人口政策確立要綱と言う方針が閣議決定されますが、これを見てみると、国を支えるために「健康な子ども」を両親は育てるべきであるという書き方をしてあります。子どもを育てるのは親の義務であり、国が責任を持つものではないという考え方が色濃いですね。
戦後になりますと日本国憲法の施行により状況が変わってきます。生存権が憲法に盛り込まれたことにより、国は子どもを含めた国民が健康な生活を享受することに責任を持つこととなりました。憲法がすぐに実際の立法・行政に影響を与えたわけではありませんが、戦災孤児等に対しては積極的に対策が講じられたようです。そして昭和40年代に児童手当(1972年開始)、福祉医療制度等が始まり、今に至ります。医療技術の発達、および生活レベル向上により乳幼児死亡率は大幅に改善し、敗戦直後は1,000人中100人が3歳誕生日までに死亡していたのが、2002年には3人しか死亡しないようになりました。もっとも出生率もそれに従って減少し、敗戦直後は4以上だったのが2002年には1.32と言う数値を示しています。敗戦直後の多産多死から、ベビーブーム時代の多産少死、そして現在の少産少死へと推移しているのです。
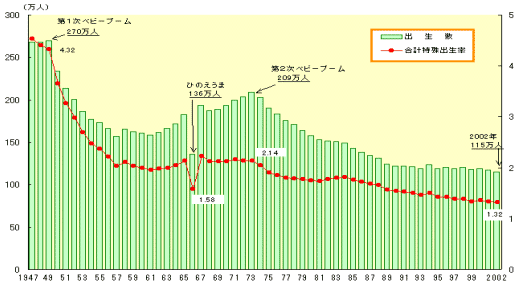 |
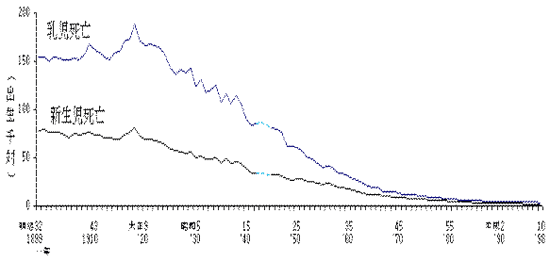 |
| 用語解説その1 合計特殊出生率:人口統計上の指標で、一人の女性が一生に生む子どもの数を示す。この数値によって、将来の人口の自然増減を推測することができる。 死亡率:出生から1年未満の死亡を乳児死亡といい、乳児死亡率は、年間の出生件数に対する比率として計算され、通常1,000件当たりの乳児死亡数として表される。なお生後4週間以内の死亡が新生児死亡である。 |
3. 諸外国との比較
日本の制度を検討する前に、諸外国の制度をちょっと見てみましょう。対象国は日本・フランス・ドイツ・アメリカ・ノルウェーの5カ国、日本とアメリカ以外のデータは2003年~2004年海外情勢白書から引用してあります(別紙1参照)。児童手当以外の制度についても比較したかったのですが、資料を集められませんでした。
単純に手当の金額を比べて見ると、ドイツ、ノルウェー、フランス、日本、アメリカとなります。税制、物価の違いなどもあるので、そのまま比較することは危険ですが、欧州各国が手厚い児童手当制度を設けているのは間違いないでしょう。アメリカについては自助努力の気風が強く「大きな政府」はあまり好まれないことが影響しているようです。
4. 現在の群馬県における諸制度
| 用語解説その2 乳幼児福祉医療制度:一定の年齢以下の子どもについて医療費の一部負担金分を助成する制度。県によって対象範囲は様々であるが群馬県の場合、小学生未満児を対象としている自治体がほとんどである。県の補助対象となるのはその内の3歳未満児分であり、補助率は50%となる。 |
今度は日本国内で制度の比較をしてみましょう。児童手当については国内ではほとんど違いはありません。現在は手当として支給される金額の内、およそ2/3を国が補助し残りの1/3を自治体が負担する仕組みのようです(支給内容について細かく補助割合が定められています)。東京都の一部の区では所得制限をはずしてその分を自治体単独で補助するという制度があるようです。自治体単独分については国の補助対象にならない可能性が高いので、これを行っているのはかなり財政状況が良い自治体だと思われます。