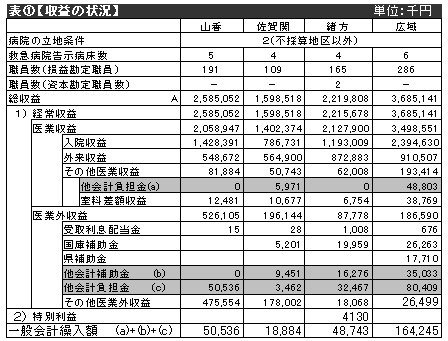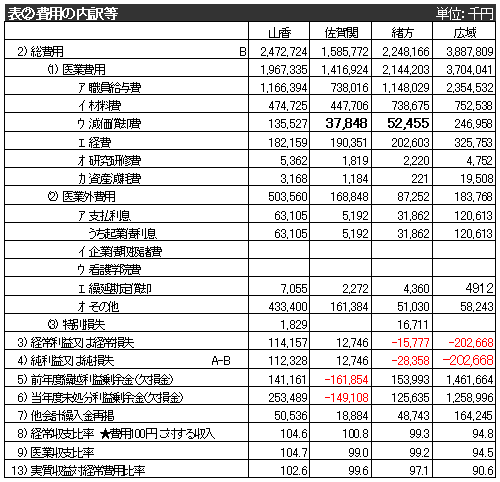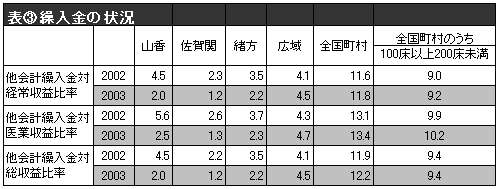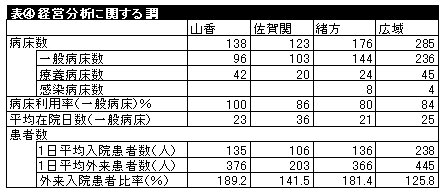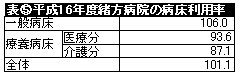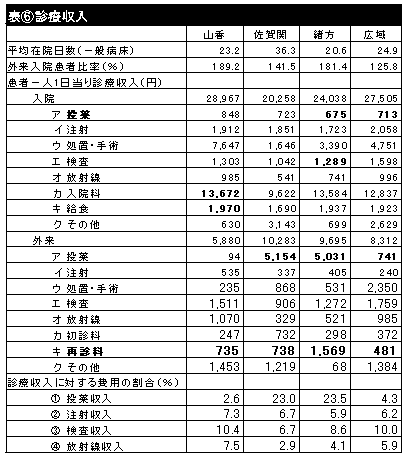【自主レポート】
|
公立おがた総合病院 大分県本部/豊後大野市職員労働組合 |
1. はじめに
今、自治体病院は、国の三位一体改革による自治体財政の危機的な状況、さらには、医療制度改革による診療報酬のマイナス改定等、非常に厳しい経営環境にさらされている。2002年に、医療界初の診療報酬のマイナス改定が行われ、以後、病床数の削減に向けた医療制度改革、さらには自治体財政の悪化や圏域の人口減少、高水準で推移する高齢者比率など、厳しさは増すばかりだ。
こうした中で、佐賀関病院の民営化、県立病院の公営企業法全部適用(以下「全適」という。)に見られるように、大分県でも自治体病院の経営のあり方が大きく問われている。現状としては、2004年4月の時点で、全国的には、60団体163病院が、公営企業法の全適へ移行している、という(全国自治体病院協議会調べ)。豊後大野市も、町村合併を機に、緒方病院における経営形態のあり方として、公営企業法の全適を視野に入れた協議を迫られ、合併後、新市において「公立医療施設評価委員会」が組織された。委員会では、2007年4月からの全適に向けた議論が行われているところである。
2. 公立おがた総合病院の現状及び課題
2003年度公営企業年鑑で、業務運営内容を検証した。比較対象は、山香国保総合病院、佐賀関町国保総合病院、東国東広域連合国保総合病院の県下3自治体病院である。いずれも、公営企業の財務会計のみを適用している、いわゆる公営企業法一部適用だ。2003年度4病院の収支状況は、表②=8)の経常収支比率でわかるように、山香病院は、104.6%(100円の経費で104.6円の収入)、佐賀関100.8%と黒字となっている。これに対し、緒方、広域の2病院はマイナス(赤字)となっている。ちなみに緒方病院は、100円の経費で99.3円の収入しか得られなかったという結果だ。
しかし、他会計繰入金を差し引いた純粋な意味での黒字かどうかは、表②=13)の実質収益対経常費用比率で見るわけだが、その場合、黒字は「山香病院」だけとなっている。
次に実際の経営状況を損益計算書(表①)から見てみる。問題は、医業外収益の中の他会計負担金、補助金である。これは、地方公営企業法第17条に基づく繰入金である。「経費の性質上、病院経営による収入を充てるべきでない経費」や「病院事業という性質上、いかに能率的な経営を行っても、なお病院事業による収入を充てるのが客観的に困難であると認められる経費」については、自治体の一般会計等から出資、貸し付け、負担金等で負担しなさい、というものである。
繰入対象となる事業は、交付税措置をされる事業以外に、いくつか列記すると、「巡回診療等に必要な経費」や「医師、看護婦等の研究・研修に要する経費」、「病院事業の経営研修に要する経費」、「リハビリテーションに要する経費」、「周産期医療に要する経費」「保健衛生行政に要する経費」などで、病院の収入だけで事業を実施するには、「無理がある」「酷だ」というものである。これらは、自治体としての政策にも関わる部分、つまり政策医療と言われるものである。
緒方病院は表①で他会計負担金(a)は、2003年度の計上はないが、他会計補助金(b)は「共済追加費用分」、「研究研修費」で、負担金(c)は「企業債償還利子」分や「二次救急施設運営費」分である。
なお、表③は、一般会計からのこうした繰入が、経常収益、医業収益及び総収益のどれだけを占めているかを示す。
この比率の高いのは広域病院だが、全国町村立の自治体病院の2003年度の水準では、「対経常収益比率」11.8%、「対医業収益比率」13.4%、「対総収益比率」12.2%となっており、いずれも2002年度をわずかではあるが上回っている。県内では、広域で若干上回ってはいるが、山香、佐賀関、緒方いずれの病院も2002年度を下回っている。このように、県下自治体病院の操出しレベルは全国水準に比してかなり低い結果となっている。参考のため、いちばん経営が厳しいとされる病床数「100床以上200床未満」の町村立の病院での繰入金の状況は、全国平均で、いずれの数値も9%~10%台(表③)となっている。県の場合、総収益に対する他会計繰入金の比率は、県立病院で13.5%、三重病院で9.2%と高い水準にある。
緒方病院の場合、2003年度の普通地方交付税は、病床数に対する算入分は、1床当り506千円(2002年度544千円、2001年度592千円と年々引き下げ傾向にある。)で、84,991千円が、さらに病院事業債に係る利子分の経費で12,774千円が措置されている。特別交付税では救急指定Bランクで24,500千円(2004年度は23,500円に削減)、共済追加費用分として、14,396千円(113千円円×職員数)が措置され、普通、特別合せて136,661千円が交付されている。
3. 新築で膨らんだ減価償却費
費用の部で医業費用(表②)について見ると、緒方病院、佐賀関病院で目立つのは、減価償却費の計上額の低さである。緒方病院52,455千円、佐賀関37,848千円となっている。減価償却費は、器材機器や構築物など固定資産の取得価額を、その耐用年数の期間中に費用として各年度に配分する会計手続だが、地方公営企業では、利益の有無に関係なく必ず減価償却を行わなければならない。緒方病院では建替えを理由に、器材等の購入を控えてきた。緒方町職労のときから、この点について、「建替え後の償却費の高騰が想定される。実際に現金が動かないとはいえ、注意すべきだ」と。緒方病院が新築移転したことにより、2004年度は、減価償却費が、309,690千円となった。実際に毎日の取引に影響するわけでもなく、支出を伴うわけではない償却費が306,690千円だから、不測の事態における対処が可能だ、資金ショートは起こさないから大丈夫、という病院側の考えが示されたことから、合併協議の際に、物議をかもしたわけである。
例えば、50億円の起債で新築したとする。償却を25年の定額法とすると費用が毎年2億円生じることとなる。実際に現金の移動(支出)はないが、費用として扱わなければならないため、その分利益が2億円減ることとなる。赤字なら、当然赤字が2億円増えるわけである。ちなみに山香病院では、135,527千円の減価償却費を留保しながらも、黒字決算となっている。
緒方病院の場合、2004年度の減価償却費309,690千円の計上は、経常経費の12.4%(表⑧)を占める。一般的に減価償却費の費用に占める比率は、3%~5%がベターとされているが、新築と合せて医療機器の更新等、一気に設備投資をしたためである。この投資がどういう結果となるか、今後の財政運営を圧迫する要因の一つではある。こうした減価償却費を計上していることは、「実態を見誤らない」「税務上の損をしない」などの観点から当然のことである。ただ、現在の減価償却費が、実際に支出を伴わないから資金ショートは起こさない、という考えではなく、将来的に資金ショートを起こさないために的確に計上している、と考えたいものである。
さらに、医療機器の耐用年数は、大多数が5年となっていることから、今後の5年間、この投資を活かすことは、税を投入した病院の責務であり、無責任な言い方かもしれないが、そこに働くものの使命であることを深く認識しなければならない。
4. 「在院日数」短縮と「病床利用率」の適正化
経営分析の項目(表④)では、2003年度は、病床利用率が、79.6%と県下4病院中で緒方病院は最も低い。緒方病院に限らず6人部屋が多いことや、診療科毎のエリア意識が強かったり、看護職員の人的配置が適正でない、個室が少ない、など施設それ自体の構造的なことや、男女別、感染等で利用効率の悪いことも、病床利用率を引き下げる大きな原因と言われている。旧緒方病院の場合、個室は、1室しかなかったことから、こうした結果になっていると思える。このことは、新築後、緒方病院では大幅に改善され、2004年度の病床利用率は全体で、101.1%と、これまでを大きく上回っている(表⑤)。しかし、100%を超えることは、喜ばしいことではない。
一般的に病床利用率は、「90%以上を目標にすべし」、と言われているが、緒方病院のように、救急病院を告示し、告示病床が4床であることから、その分の4床は、常時空けておくべきといえる。厚生労働省基準で、一般病床の病床利用率が、105を超えれば、入院基本料の20%が削減される。
ちなみに、公営企業会計基準では、退院日に入院患者があれば、2人ともダブリカウントされることから、100を超える結果となっているが、厚生労働省基準では、深夜0時の入院患者数で割り出すことから、ダブリカウントにはならず、それでいくと、実際は98.5%と、緒方病院は、良好な結果となっている。
次に在院日数についてである。在院日数が長い病院は、急性期よりも慢性期の患者が多く入院しているということだろう。だからといって、入院期間が24日を過ぎると入院基本料が大きく引き下げられるなど、収支にとっては、大きな問題がある。表⑥でわかるように県下4病院の患者1日当りの入院料は平均在院日数が短い山香で13,672円(2002年度14,548円)、緒方病院は、平均20.6日と一番短く、入院料は13,584円(2002年度13,325円)で、在院日数が一番長い佐賀関では、9,622円(2002年度10,507円)となっている。
しかし、気になるのは、広域病院である。1日平均入院患者数(表④)が238人と山香の135人、緒方の136人を100人近く上回っていながら、収支結果は、厳しい結果となっている。平均在院日数が、24.9日(表④)と24日を超えたことによる、入院基本料の引き下げが影響しているとしたら、やっかいな数値といえる。
「急性期病棟では、常に空きベッドが確保され、急性期患者の入院にいつでも対応できることが、患者の信頼感を得るための要件の一つでもある」と緒方病院の野田院長も指摘する。
効率よく収益をめざすには、在院日数の短縮が必要になる。しかし、短縮を図るだけで、それに見合う患者の確保ができなければ病床利用率は下がる。今後、この在院日数による締め付けは、さらに厳しさを増す。今後の診療報酬の改定の先には、20日とか14日とかが視野に入れられている。
2004年度、新病院の開院と共に、緒方病院にも「地域連携室」が設置された。その使命、役割をどう果たしていくか、在院日数や病床利用率の適正化は、病院と診療所の連携、医師会との連携なくして解決できるものではないだけに、今後の体制の充実と果たす役割は大きい。
5. 経費削減と外部委託
次に、減価償却費以外の主要経費についてだが、緒方病院は、「医療材料費」の経常経費に占める割合が、費用中31.8%と4病院の中で最も高い結果となっている(表⑦)。このことは、診療圏の高齢化率や大分市等への距離等立地条件といった地域事情にもよるわけだが、緒方病院は外来や投薬の占める割合が、他の病院に比べて高いということになる。佐賀関病院についても同様の傾向が見てとれる。
2004年度から緒方病院も、待ち時間の解消も視野に入れ、院外処方箋を導入した。その結果、2003年度決算では、医業費用の31.8%を占めていた医療材料費は、2004年度は18.2%、17年度16.5%と大きく減少している。逆に2003年度2.4%を占めるに過ぎなかった委託料は、2004年度は6.8%、17年度7.9%と増加傾向にある(表⑧)。
しかし、経費削減ばかりに目がいき、院外処方箋を導入しても、人件費や材料費は削減できても、委託料の経費増と合わせ、一方で表⑥にあるように、外来患者1日当たり5,031円という投薬収入も減少することとなる。同時に、雇用の確保や材料の調達といった企業体として地域へもたらす役割や税を投入した企業体としての必然性も細ることを見過ごすわけにはいかない。
なお、緒方病院の医業収益に対する職員給与費は、院外処方箋導入前である2003年度は、51.4%だが、院外処方箋が導入されれば、投薬等の比率が大幅に下がり、必然的に人件費率は、上昇する。広域病院では、2002年度に院外処方箋を導入したが、翌年の2003年度は、費用に占める人件費率が、53.9%から60.6%に跳ね上がっている。緒方病院の場合、人勧等の給与抑制効果で、広域病院のような影響は、回避できたようだが…。
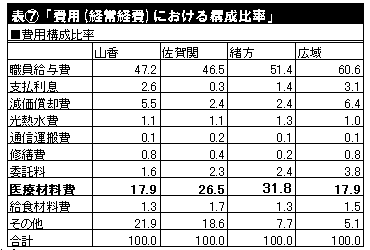
|
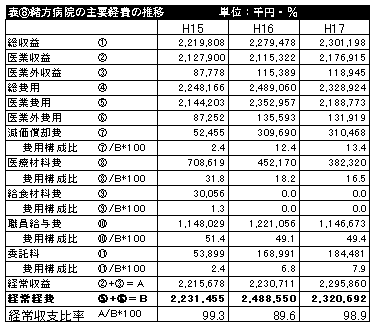
|
6. 経営の質と地域医療
経営分析の面では、病院経営は、その立地条件や圏域の状況に左右される。緒方病院は、半径20km圏内の人口が3万人を割っているわけで、しかも高齢化率も高い。こうしたことを背景に緒方病院は、診療収入のうち、再診料収入が高く、山香、佐賀関、広域を大きく上回る収入となっている。これら指標については、それぞれの立地条件や診療圏域の大きさ、他の医療機関の設置状況、交通事情等によることも大きいわけだが、病院自体の求心力も問われる。標榜する診療科目や医師に対する信頼感、施設・設備の状況及び患者サービスの有り様などである。
さらに、「年間延べ外来患者数」を「年間述べ入院患者数」で割った数値である「外来入院患者比率」(表④)は、外来患者がどれだけ入院措置を必要としたかを示すもので、低いほど効率的と言われる。広域の125.8に比べ、緒方病院は、181.4と山香病院と共に高い数値となっている。この数値が高いほど外来患者のウエイトが高く、経営上のみの視点から言うと、外来患者は多いが、入院を必要とする患者は、それほど多くない、ということを物語っている。1日平均入院患者数とともに、広域病院と大きく異なる点である。
また「患者一人1日当りの診療収入」(表⑥)の項目では、1日当りの「入院収入」は24,038円で、山香、広域に次ぐ結果となっている。逆に、「外来収入」では、緒方病院は9,695円と、山香、広域を上回っている。その要因は「投薬収入」と「再診料」が高いことである。このことは、緒方病院を「かかりつけ医」とする固定患者が多く、しかも高齢の慢性期患者が多い、という過疎地域ならではの体質をあらわしているといえる。
7. 安心の医療提供めざして
以上、県内の公立病院について、公営企業会計年鑑(2003年度版:2005年3月発行)の指標並びに数値を追ってみた。緒方病院においては、外来患者が多く、しかも再診による収益が、他の3病院に比べて高い。
また、県が5年ごとに保健医療計画を策定している。最新の2003年度版によると、「大野医療圏域は、高齢化率が高く、圏域の患者の受診行動は、圏域内医療機関での受診が67%で、圏域外医療機関での受診が33%となっており、他の圏域医療機関で受診する率は、県内で最も高い」とされている。
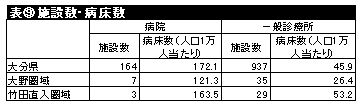 |
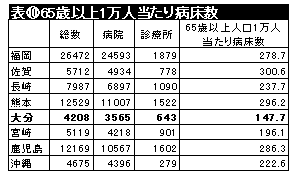 |
過疎・高齢化を背景に、疾病別の受療行動は、県の保健医療計画によると、「循環器系」「呼吸器系」及び「消化器系」の疾患については、80%の患者が圏域内の医療機関で受診しているが、「新生物」「皮膚及び皮下組織」、「精神疾患」については、圏域外での受診が50%を超えている、と。高齢者の疾患といえば、高血圧、動脈硬化、狭心症、心筋梗塞など循環器系の疾患が際立って多くなるといわれているが、そうしたことを反映した結果といえる。
2007年4月の全適移行というスケジュール以前に、今、この機会に、こうした医療環境並びに受診行動等、地域特性を視野にいれながら、市民みんなが安心できる医療体系の確立に向けた議論が望まれる。このことが、この地域の医療を守り育てるための切符である。はじめに全適ありき、ということでは切符に成り得ない。行き先を大きく誤ることとなる。今後の医療サービスの有り様次第では、独居老人や老人世帯の多いこの地域だが、豊後大野市に年寄りだけで住ませることは不安だ、ということから、都市部で生活する子供の所へお年寄りが、呼び寄せられることにもなりかねない。
8. おわりに
「医療に関しては、市場のメカニズムが有効に機能し得ないことは、米国の実例からでも明らかである。なぜ市場のメカニズムが有効に機能し得ないかというと、医療以外のサービス・消費財については、『財力がなければ購入を諦める』という選択が比較的容易になし得るのに対し、医療のサービス・消費財については、『購入を諦めることは死ぬことを意味する』という状況が容易に生じ得る、という決定的な違いがあるからである」
ハーバード大学医学部助教授である李 啓充氏の言葉である。