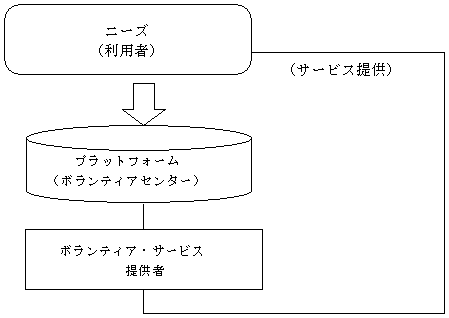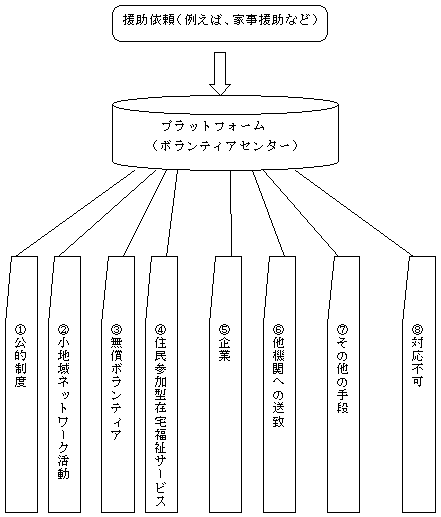【自主レポート】
|
松江市における地域包括ケアシステムの構築に向けて 島根県本部/松江市職員ユニオン |
| 1. はじめに 2. 松江市における高齢者の状況と課題 3. 市社協・地域包括支援センターと労働組合の役割 4. 松江市における地域包括ケアシステム構築に向けて 5. おわりに |
1. はじめに
平成の大合併により、2005年3月31日に1市7町村が一つになり、人口193,772人(うち高齢者人口43,109人、高齢化率22.25%。2005年度松江市高齢者統計表参照。)の新松江市が誕生した。また、介護保険制度が2005年6月に法律の一部が改正され、2006年4月より施行されたが、この中で特に要支援、要介護1といった軽度者に対するサービスの内容や提供方法について「新予防給付」を創設し、より「自立支援」に資するものとなるよう改められた。それに伴い全国の市町村において地域包括支援センターが創設され、松江市においては市地域福祉計画・地域福祉活動計画を基に市内を5つの生活圏域に区分し、5箇所の地域包括支援センターが開設され、その事業委託を市社会福祉協議会が受託した。地域包括支援センターの基本機能として、①共通的支援基盤構築、②総合相談支援・権利擁護、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④介護予防ケアマネジメントの4つの業務があるが、地域住民、介護保険事業者、NPO・ボランティア、行政等が一体となり、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域社会づくりを推進していくことが求められている。松江市では、健康福祉部・社会福祉協議会に働く職員が中心となり、持ち前の知恵、経験、馬力、根性をもって、この新たな介護保険制度をスタートさせたが、改正された介護保険制度に対する新予防給付などの市としての取り組み方を明確にすることや、特に民間福祉団体との協働のあり方について、労働組合としても検証していく必要があると思われる。
本レポートでは、地域福祉の推進団体である社会福祉協議会における地域包括支援センターと労働組合(松江市職員)のそれぞれの役割について考え、地域福祉を基盤とした松江市における地域包括ケアシステム構築に向けて考えてみたいと思う。
2. 松江市における高齢者の状況と課題
はじめに介護保険における被保険者数を見ると、全国的なデータでは介護保険制度がはじまった2000年4月末に2,165万人であったのが、2004年11月末には、2,484万人と約319万人、およそ15%の増加をしている。また、松江市においても、2000年に38,644人であったのが2005年には43,137人となり、およそ被保険者数が13%の増加であり、全国同様に高齢化が進展している。
要介護認定を受けている人の推移を見てみると、全国的に2000年4月末から4年7ヶ月でおよそ86%の要介護認定者が増加している。松江市では2000年に4,314人であったのが、2005年には7,191人となり、66.7%の要介護認定者数が増加しており、介護保険制度が定着してきたと思われる。ここで、要介護認定者のうち、要支援・要介護1(軽度者)の状況を見てみると、全国で2000年に842,000人であったのが、2004年には1,965,000人、松江市では2000年に1,579人から2005年に3,481人となり、120%の増加であり、介護度改善の見込みのある(可能性のある)人の割合が多いことがわかる。
つづいて、「年間継続受給者数の要介護状態区分の変化割合」を見てみると、2004年度の全国データから、要支援等と要介護1の状態をみると、軽度の状態から、26%、16.9%の割合で重度化していることがわかる。つまり、介護度の改善の見込みがある要支援等や要介護1の人が高い割合で重度化しており、できるだけ元気で自立した生活を継続するためには、介護予防の視点に立ったアプローチが必要であることがわかる。
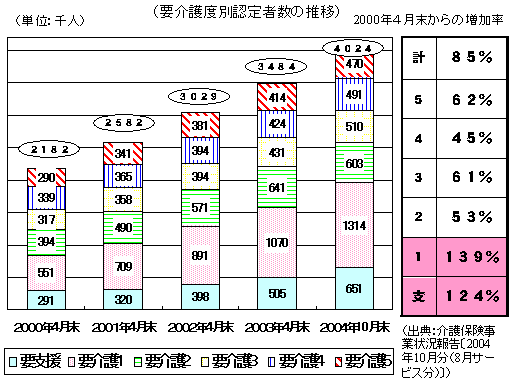 |
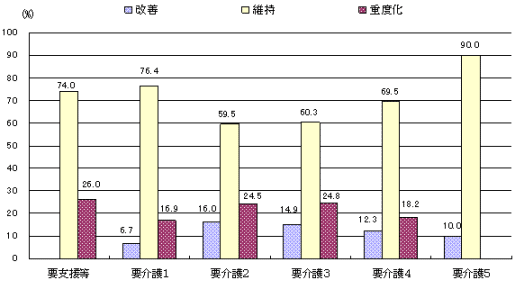 |
(出典:介護保険事業状況報告) |
また、介護保険財政の現状について、1号保険者の保険料を見ると、全国平均で第1期は2,911円、2期が3,293円と上昇しており、松江市においても3,140円から3,460円と高くなっている。現状のままでいくと、介護保険料が上昇していくことが容易に想定できる状況であり、介護度の改善見込みのある高齢者が重度化しないための介護予防への取り組みが重要となる。
厚生労働省老健局長の私的研究会である高齢者介護研究会(さわやか福祉財団 堀田力理事長 座長)の報告「2015年高齢者介護」によると、
① 9年後の2015年には、団塊の世代が前期高齢者となり、その10年後の2025年には全国で約3,500万人となりピークを迎える。
② 認知症の高齢者もそれに伴い、2015年には250万人になると推定される。
③ 少子化に伴う家族形態の変化もあり、一人暮らし世帯が高齢者世帯の33%にあたる570万世帯に達する。
と報告されている。高齢者人口の増加、一人暮らし高齢者、認知症高齢者の増加により、介護保険制度のみでは介護を支えるしくみが難しくなってくるであろうと予測される。介護予防をはじめ、地域ぐるみでできるだけ高齢期を元気で暮らすことができるような取り組みや介護保険制度のみならず、ボランティア・NPO、地域福祉活動、労働組合など様々な支えあいができるような仕組みづくりが今から必要であると考える。
3. 市社協・地域包括支援センターと労働組合の役割
(1) 松江市における地域福祉活動の現状
松江市においては従来、市社会福祉協議会(以下、市社協)が地域福祉の中核的な推進団体としてその役割を担っている。また、1997年には地域の拠点施設である公民館に市福祉部の予算措置による地域保健福祉推進職員が設置され、市社協が組織する地区社会福祉協議会(以下、地区社協)の事務局を担当することで公民館を基盤とする地域福祉の推進体制が確立した。また、市社協は地区担当職員を配置しており、地区社協が行う地域福祉活動に関する助言等側面的な支援を行う。ここで、松江市社協が行う主な地域福祉に関わる事業を紹介すると、①地区社協が行う地域福祉活動支援(地区担当職員の配置、活動費の助成、地域福祉に関わる研修会の開催等)、②地域福祉権利擁護事業(判断能力の不十分な高齢者、障害のある方等を対象とした福祉サービス利用援助・金銭管理・書類等預かりサービスを行う)、③ふれあい総合相談所の開設(民生児童委員による暮らしのなんでも相談)、④なごやか寄り合い事業(地区社協を実施主体とした閉じこもり予防を図る自治会単位のサロン開催に関する支援)、⑤ボランティアセンター活動事業(ボランティアの紹介・斡旋、ボランティア養成、福祉教育、民間ボランティア活動助成金等ボランティア情報の提供を行う)などがある。また、地区社協の活動について触れると、各地区の特性に応じてそれぞれ様々な活動があるが、その活動の中心を民生児童委員や自治会選出の福祉推進員が担い、高齢者見守りネットワークやミニデイサービス、配食サービスや障害のある子ども・親と地域とのつながりづくりを目的としたあったかスクラム事業、子どもの居場所づくりなど地域の課題に即した取り組みが熱心に行われている。2001年より各地区において地区地域福祉活動計画の策定も行われており、各地区の計画を基に、松江市においても行政・市社協による松江市地域福祉活動計画・地域福祉活動計画を策定し、住民参加による総合的な福祉でまちづくりを進める指針となっている。
(2) 松江市における市社協・地域包括支援センターの役割
平成の大合併により松江市も1市7町村が一つになり、それに伴い市町村社会福祉協議会も合併をした。このことにより、特に地域福祉にとっては一社協が対象とするエリアが広域化し、今まで町村社協が行ってきたミニデイサービスやいきいきサロン活動などで築いてきた地域福祉の実践や福祉コミュニティ形成の実績をいかに継承していくかが問われている。つまり、地域福祉実践の量と質の低下とならないための公民館区等地区単位を基本とした地域福祉活動をどのように支援していくかが大切であると考える。
地域包括ケアシステムとは、厚生労働省老健局長の私的研究会である高齢者介護研究会によると「個々の高齢者の状況やその変化に応じて、介護サービスを中核とした様々な支援が継続的かつ包括的に提供される仕組み」と定義されている。介護保険制度等フォーマルなサービスを担う民間事業所や地区社協を中心として展開されている住民地域福祉活動、NPO・ボランティアによる在宅福祉活動などの把握・活用を図る仕組みづくりが、これまで松江市において地域福祉推進の中核を担ってきている市社協・地域包括支援センターの役割であると考える。
(3) 松江市における労働組合の役割
地域包括ケアに向けた仕組みづくりは、松江市においては地域福祉の推進団体である市社会福祉協議会(地域包括支援センター)と行政とが協働して推進していくものと考えるが、一方で市民福祉の充実が図られるよう、行政・公共福祉サービスに携わる労働者の立場から、果たすべき役割もあると考える。
介護保険制度にある利用者(市民)に対する自立支援は、自分でできる人のことまで代行するのはやめよう、というのが原理・原則であることは当然のことである。しかし、介護保険制度運営上のコスト削減のみが先行し、何が本当に必要な介護で、何が重度化を防ぐのかということを見失ってしまっては、制度改正の基本理念の一つである「明るく活力ある超高齢社会の構築」とはいかないであろう。
松江市の労働組合としての役割は、松江市が進める介護保険制度のあり方に対し「利用者本位の本物の介護を実現しつつ、その中から真の介護予防、自立支援の取り組みとなっているか」を職員の立場から検証・提言していくことや、労働組合として、地域における高齢者介護の支えあいの仕組み(地域包括ケアシステム)の中で、行政責任で行うべきことは何か、社会貢献としてできることは何かを考え、取り組んでいくことが役割なのではないかと考える。
4. 松江市における地域包括ケアシステム構築に向けて
松江市において個々の高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことの出来るよう、その支えあいの仕組みとして地域包括ケアシステムを構築していくためには、以下の点が必要であると考える。
(1) 地域における福祉連絡会の立ち上げ
市内15箇所に設置されていた在宅介護支援センターが廃止となり、市内5箇所の地域包括支援センターを各生活圏域の高齢者に関する相談の拠点として開設されたが、生活圏域エリアは公民館区・旧町村単位で4~7地区という広範囲であり、地域包括支援センター1箇所の相談窓口で賄えるものではない。また、これまで松江市在宅介護支援センター事業を行ってきた社会福祉法人・医療法人は地域の民生委員・福祉推進員等とのつながりもあり、身近な地域の医療・福祉施設として地域住民から期待されている所もある。また、何よりも重要なことは、同一地域に地域住民をはじめ、医療・社会福祉施設、保健師、地域福祉担当職員等様々な専門職種や立場の関係者が関わることが、地域でのニーズ発見や課題解決のために必要であるということである。そこで、地域における高齢者相談のネットワークづくりが必要であると考える。これまで行われている民生委員・福祉推進員等の活動を基盤としながら、地域に関わる専門職(福祉施設職員、保健師、地区担当職員等)により、相談を適切な機関等へつなげる相談の流れ、それぞれの立場で地域に対して協力できることや役割をまずは整理しておく必要がある。そのような話し合いの場として、地域包括支援センターの呼びかけにより、地区単位(公民館区・旧町村エリア)毎に行政やサービス事業者の福祉連絡会を立ち上げ、地域における相談体制のあり方、地域課題等について検討できる場となればと考える。また、当該圏域や市全体で課題解決を図ることや情報の共有のため、必要に応じてブロック連絡会や高齢者サービス調整会議を活用していく。
(2) 福祉プラットフォームづくり
介護保険制度のみでは高齢者の生活を支えていくことは難しい。例えば、僻地に住居があるなどの理由により介護予防サービス以外にも生活支援サービスが必要な高齢者も多くある。高齢者の様々な生活課題の解決を図る手段として、フォーマル・インフォーマルなサービス(あるいは活動)に関する情報を一元化し活用していくしくみが必要である。そこで、三重県上野市社協において実践されているプラットフォームの考え方が有効ではないかと考える。プラットフォームとは、本来「駅で、乗降が便利なように、線路に沿って適当な高さに築いた構築物。ホーム」であり、コンピューター用語では、「アプリケーションソフトを稼動させるための基本ソフト、またはハードウェア環境」という意味(参照:福祉NPOと社協等地域の関係団体による連携・協働促進モデル事業報告書、上野市社協上野市ボランティア・市民活動センターボランティアコーディネーター乾光哉)であるが、市社協ボランティアセンター(プラットフォーム)に同意の下、様々な団体に登録をしてもらい、ボランティアコーディネーターが個々のニーズに合わせコーディネートを行うしくみ(図1・2参照)である。プラットフォームに登録されたサービス(活動)はボランティアセンターから冊子やインターネット等を通じて住民、相談機関に向けて広報を行い、活用に際してボランティアコーディネーターにより登録団体・グループとの調整を利用料金等個別ニーズに合わせて調整を行う。
労働組合の社会貢献活動として行っている年1回の障子張りボランティアや年末の電球の取替えボランティアなど労組として登録を行ってもよい。また、労働組合として一番重要なことは、今後団塊の世代が退職となることを受け、いかにこの人材を社会貢献につなぐことが出来るかである。普段仕事や子育てをしながら社会貢献活動も行うことは時間的にも難しいので、むしろこれから退職する人たちが現役時代に職場で培ったノウハウを生かせるようなグループづくり・メニューづくりを行えるような側面的な支援活動が求められているように思われる。
| (参照) |
|
出典:福祉NPOと社協等地域の関係団体による連携・協働促進モデル事業報告書、上野市社協上野市ボランティア・市民活動センターボランティアコーディネーター乾光哉 |
(3) 地域福祉活動
松江市では、公民館区・旧町村ごとに地区社会福祉協議会が組織され、住民参加による地域福祉活動が展開されている。高齢者見守りネットワーク、なごやか寄り合い事業、障害のある子どもと地域のつながりを作る、あったかスクラム事業など高齢者から子どもまで地域の課題に目を向けた活動が行われている。地域包括ケアの観点から高齢者をはじめ誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりとして、介護予防や認知症、消費者被害、権利擁護に関することなど住民への啓発活動や学習会などを地区社会福祉協議会と地域貢献を考えている民間事業所など地域の関係者同士が協働して行える仕掛けを、社協地区担当職員、地域包括支援センター職員、行政保健師などと公民館の地域保健福祉推進職員が中心となって工夫していく取り組みが必要であると考える。
(4) 労働組合における取り組み
松江市職員ユニオンにおける取り組みとして、3つの事柄を提案したいと思う。
一つは、施策への検証・提言である。松江市に働く職員の立場から、高齢者等が安心して暮らせるまちづくりに向けて、保健・医療・福祉サービスをはじめ、地域福祉活動へのサポートなど公務労働によるサービスの必要性を引き続き松江市に対し働きかけ、財政事情にのみ偏重しない「公・共・私」の役割を検証することが大事であると考える。公的責任を担保した、住みよい地域づくりを進めていくことが求められている。
二つ目は、労働組合としての社会貢献活動である。先ほどの福祉プラットフォームでも提案したように、退職した団塊の世代の人々をいかに地域の活動に結びつけるかを真剣に検討していくことが、地域福祉の活性化や介護予防・生きがいづくりのポイントになるのではないかと考える。そこで、退職者に地域活動への必要性や興味をもってもらえるような「ボランティア養成講座」の開催、パソコン、事務処理、車の運転等現役時代の技能が生かせるような「シニア人材バンクの設立」(本人の同意を得て、ボランティアセンターや公民館に人材情報を提供する)、退職後の生活をサポートする「年金セミナー」の開催などこれから松江市を退職する職員等への働きかけをすることで、活力ある高齢社会実現に向けた社会貢献活動を行うことができるのではないかと考える。
三つ目は、組合員への啓発(学習)活動である。例えば、松江市職員ユニオンでは、松江市労連時代から松江市移送サービス(運転ボランティア)の取り組みを行っている経緯から、新入組合員等を対象に、松江市に住む高齢者・障害者について、その生活を知るきっかけとして、このボランティアへ参加してもらうことや、「認知症」や「介護予防と生活習慣病について」などの学習会を設け、高齢者福祉の観点から、松江市職員としてそれぞれの職場で業務に工夫できることを提案できるような機会をもつことも大切ではないかと考える。
5. おわりに
財政的な観点から公的介護保険制度が将来的に持続可能かどうかが問われている今日、公的な福祉サービスのほかに、民間活力による支えあいの仕組みづくりが求められている。個々の高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、行政・市民・労働組合それぞれが自らの社会的責任について考え、実践を行っていくための仕掛けが必要なのではないかと思う。
また、自殺の増加、児童虐待、競争社会によるうつ病の増大等々、健康危機が広がっている現状が、日々、報道されている。社会問題としての健康問題への対応は、地域住民に健康で安心な暮らしを保障する義務を負う自治体が担わなければならない仕事である。こうした役割を後退させることにつながらないよう、保健師をはじめ、松江市に働く医療・保健・福祉に働く専門職を確保することや市民や民間福祉団体等への支援の人的な基盤を作ることなど労働組合として、行政としての責任を明確にしていく働きかけも必要である。
本レポートでは、松江市における地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域包括支援センター・労働組合の役割を考えることをテーマにそのポイントについて意見を述べた。松江市に働く職員として、高齢社会について学習・提案ができるような組合活動や、なによりも松江市健康福祉部や社協職員は現場で働く者として、介護保険制度をはじめ、地域福祉を基盤とした松江市における地域包括ケアのあり方について、市民とともに検証しながら、進めていくことが大事なのではないかと思う。市民、職員、行政が協働のあり方を模索しながら、よりよいまちづくりを進めていくことが、私たち松江市に働く職員の使命であると感じるところである。