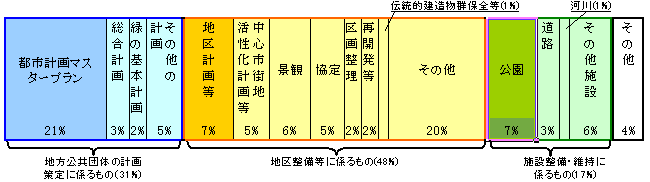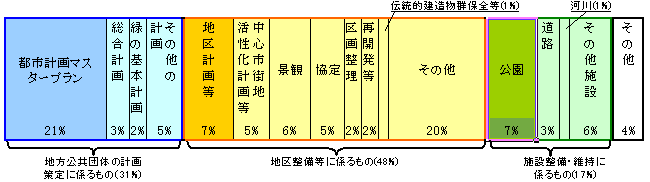|
(注)出所データのままでは全体足上げが+1%となるため、本図表では「その他」を▲1%して調整している
(出所)国土交通省 http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/jisedai/1/030415.pdf をもとに作成
(2) 市民参加の方法 ◆参照 → 図表2 まちづくりへの参加の手法
次に「②まちづくりへの市民参加の方法」については、少なくとも図表2に示すような「まちづくり協議会」「ワークショップ」「各種委員会」「アンケート」等の複数のルートが存在しており、それらが市民参加手法として並列的に採用されていることが分かる。
|
図表2 まちづくりへの参加の手法
|
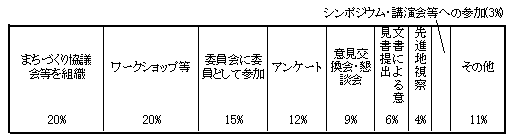
|
(出所)国土交通省 http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/jisedai/1/030415.pdf をもとに作成
(3) 市民参加の階層 ◆参照 → 図表3 Arnsteinの「市民参加の梯子」
アメリカの社会学者Arnstein(1969)は、市民参加のあり方を梯子に見立て「市民参加の梯子」を提唱している(注4)。同女史は市民参加を「市民の参加とは住民に目標を達成することのできる権力を与えること」と定義し、市民の力(権力)の程度に応じて1段~8段までの8段梯子を想定している(図表3)。これによれば1段~2段は「参加不在」状態であり、まちづくりに対する市民の権力は何も認められていない状態を指す。次に3段~5段は「形式だけの参加」状態とされ、参加機会は存在するものの情報の流れが一方通行であるなど市民の権利が形式的な水準に留まっている状態を指す。最後に6段~8段は「市民の権利としての参加」状態であり、一定水準以上、市民の権利が確立しており、これに基づいてまちづくりを進めることが可能な状態を指すという。
前橋市を含む全国の自治体で、いまや市民参加に関わる取り組みは盛り上がっているが、それらが内包する「市民参加」の効果を測る尺度として「市民参加の梯子」は有効であると思われる(注5)。「市民参加の梯子」に照らして市民が6・7・8段目の状態、すなわち「市民の権利としての参加」状態に位置づけられる事業であれば、質的にも量的にも市民参加の効果が大きく発現すると思われる。
|
図表3 Arnsteinの「市民参加の梯子」 |
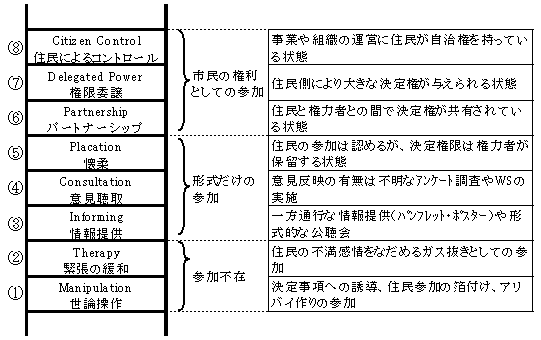
|
| (出所)世古(2001,p40)等をもとに作成 |
(4) 公務員市民とまちづくり
ここで先述の「役割相乗型社会」を念頭において、まちづくりへの市民参加を鑑みるに、「市民参加の梯子」6・7・8段目に到達するには「まちづくり制度の整備」もさることながら「まちづくりを支える人材の育成」も欠かせない視点であると言えるだろう。
このことは、行政がまちづくりに関する会議を招集するとき、どの会議を見ても、結局選出されて出席するのは「同じ顔ぶれ」といった事態が起こることからも明らかなように、現状「まちづくりを支える人材」は稀少である。一部の人間が複数の役職を兼務しているケースが多く、地域における人材確保は永年の課題となっている。この状況に着目すると、我々は「公務員市民」として、まちづくりに何らかの貢献ができるのではないだろうか。
そこで次節では、市民参加のまちづくりを促進させる手法として知られる"ワークショップ手法(注6)"に注目し、先進自治体における取り組みについてその課題を含めた実態調査を行う。そしてこれを踏まえ、公務員市民のスキルとしての可能性を検討したい。
3. ワークショップ実施に関するアンケート調査
(1) 調査対象属性について
本節では行政運営に「ワークショップ手法」を取り入れている先進自治体についてアンケート調査を実施し、その運用実態と問題点の把握に努めた。その際、先の「市民参加の梯子」を踏まえ、調査対象は全国の基礎的自治体のうち次の[1][2]を満たす団体とした。
[1] 全国の基礎的自治体のうち、「自治基本条例」「まちづくり条例」「市民参加条例」など市民参加促進のために自治体独自の条例(以下、自治基本条例等という。)を策定済のもの(2005年3月31日現在)
[2] 自治基本条例等が策定済である基礎的自治体のうち、条例中に「ワークショップ」を明示しているもの |
(2) 抽出方法および抽出結果
抽出作業[1]として文献調査およびインターネット閲覧調査を行った。文献調査では地方自治職員研修編集部(2002)とイマジン自治情報センター(2004)を利用、インターネット閲覧調査では神奈川県大和市および東京都練馬区のホームページ(注7)をもとに自治基本条例等の先行事例集を入手のうえ併せて参考にした。抽出作業[1]の結果、基礎的自治体の自治基本条例等の先行事例として53自治体/61事例が確認された。内訳としては自治基本条例14例、まちづくり条例16例、市民参加条例17例、その他14例となっている。
次に抽出作業[2]については、抽出[1]より自治基本条例等として53自治体/61事例を抽出できたことから、53自治体のホームページにアクセスして例規集を閲覧、各条文の見出しをまとめ、自治基本条例等の先行事例一覧を作成した。その結果、53自治体/61事例のうち、条例でWSを明確に位置づける自治体は「多摩市」「西東京市」「京都市」「下関市」「鹿児島市」の5団体であった。
以上[1][2]の作業の結果、5つの自治体が抽出されたのでこれを調査対象とし、ワークショップの運用実態およびその課題を把握するために11問から成る調査票を作成した。
なお、質問構成は図表4に示す内容となっている。
◆参照 → 図表4 調査票の質問構成について
図表4 調査票の質問構成について
|
質 問
|
質 問 内 容
|
回答方式
|
|
質問1
|
条例でWSを位置づけることとなった「きっかけ」について |
記述式
|
|
質問2
|
過去のWSの実施回数 |
記述式
|
|
質問3
|
いつWSを開催するか。また発案・決定は誰が行うか |
記述式
|
|
質問4
|
WSの利用範囲は組織のどこまでと想定しているか |
記述式
|
|
質問5
|
WSの運営は主に誰が行うか |
選択式
|
|
質問6
|
WSへの参加範囲の決定方法、決定権者 |
記述式
|
|
質問7
|
WSへの参加者をどのように集めるか |
記述式
|
|
質問8
|
WSのファシリテーターは誰が行うか |
選択式
|
|
質問9
|
WSのファシリテーター養成の研修を行っているか |
選択式
|
|
質問10
|
WSファシリテーター研修の内容 |
記述式
|
|
質問11
|
WS開催に関連して抱える最大の課題とは何か |
記述式
|
4. 調査結果から得られる示唆
先進自治体におけるワークショップ(WS)手法の運用実態と課題に関わるアンケート調査の結果は、図表5-1~4に示す通りである(別添の資料を参照)。
然るに、本調査から得られる知見ないし示唆とは何であるのか、またそれらをどのように評価したらよいのだろうか。これに関して、我々は以下に掲げる3点を指摘したい。
第1に、WS手法は、先進自治体の運用実態を見る限り(その必要性の判断は各担当課の裁量事項に留まるものの)、条例化の効果も手伝って住民参加手法として日常的に活用されていること。また委託業者のみならず、市職員や参加市民によるWS運営も行われるなど、限られた世界で実施されるものではなく、すでに一般的な手法になりつつあること。
第2に、WS手法の導入・実施にあたっては、(実施しないケースもあるものの)WSファシリテーター研修やパートナーシップ講座を実施することで、その実効性を高めていること。また、それ故にWS手法の習得にむけた効果的な研修が望まれること。
第3に、「実施が目的となるようなWSの形骸化の懸念」(京都市)や「WSの効能と限界を意識する必要性」(多摩市)、「ファシリテーターの手腕」(鹿児島市)、或いはそもそも「WSへの参加者が少ない場合の対応」(西東京市、下関市)などの指摘に見られるように、WS手法は決して万能ではなく、常に「実践」と「改善」を繰り返す必要があること。
◆参照 → 図表5-1~4 WS調査とりまとめ結果
|
図表5-1 WS調査とりまとめ結果(質問1・2)
|
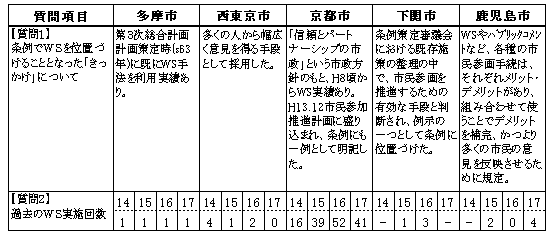 |
| (出所)調査結果をもとに筆者作成 |
|
図表5-2 WS調査とりまとめ結果(質問3・4)
|
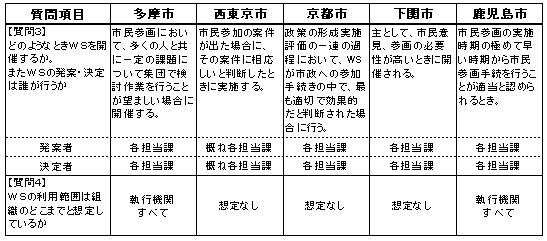 |
| (出所)調査結果をもとに筆者作成 |
|
図表5-3 WS調査とりまとめ結果(質問5・6・7・8)
|
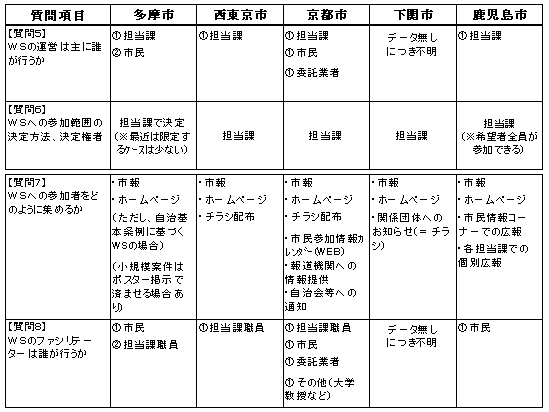 |
(注1)質問5回答欄の数字①②は、あてはまる順番を意味する。同じ数字は同順位の意味。
(出所)調査結果をもとに筆者作成 |
|
図表5-4 WS調査とりまとめ結果(質問9・10・11)
|
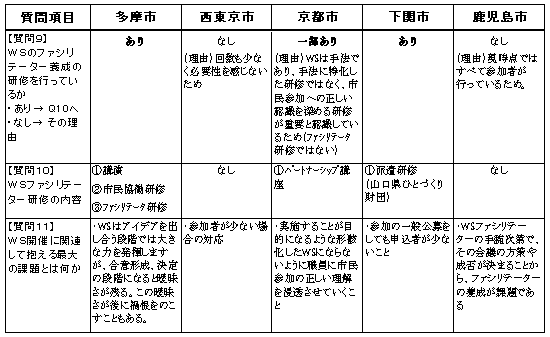 |
| (出所)調査結果をもとに筆者作成 |
5. まとめ
先進的な自治体では市民参加を確保する手段として、すでに条例等において「ワークショップ手法」を明確に位置づけているが、仮に条例等がなくても、市民と行政とをつなぐ「触媒役」の存在は、「支持される公務員」の創出に貢献できるものと思われる。
確かに、先進自治体の実務担当者が指摘するように、WS手法は決して万能ではなく、多くの留意点や課題があるのも事実である。しかしながら、先に触れたArnsteinの「市民参加の梯子」に照らすと、WS手法はより上位の段階(=678レベル)に位置する参加手法として活用できる可能性を内包しているのもまた事実である。それ故、公務員市民がまちづくりへ参加する際のスキルとしてワークショップ手法は有効であると思われる。
以上の議論を踏まえ、本研究のまとめとして、県内職員労組に対して(また全国の職員労組に対して)、組合員のワークショップ手法習得に関する人的・財政的支援を要望したい。
各地の職員労組がワークショップ手法に長けたまちづくり人材を育成・創出することにより、地域の活力は向上するものと思われる。そう遠くない将来、ワークショップ手法を習得した自治体職員が「公務員市民」として、それぞれの地域社会で有為と評価される日が来ることを願うばかりである。
注 記
1 黒川和美「<自治体破綻制度>議論と国民のモラル」、笹川平和財団『日本人のちからVol.32』、2006年、pp.8-9
2 http://eco.goo.ne.jp/business/keiei/planner/29.html
3 国土交通省社会資本整備審議会資料http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/jisedai/1/030415.pdf
4 Arnstein Sherry. R. (1969) ‘A Ladder of Citizen Participation’, Journal of the American Institute of Planners, Vol.35, pp.216-224
5 世古一穂『協働のデザイン』、学芸出版社、2001年、pp.37-39
6 本研究では「ワークショップ」の定義を「参加者が自ら参加・体験して協同で何か学びあったり創り出したりする学びと創造のスタイル」(中野民夫『ワークショップ-新しい学びと創造の場』、岩波新書、2001年、p11)とする。
7 地方自治職員研修編集部(2002)『自治基本条例・参加条例の考え方・作り方』、公職研、pp.196-197
イマジン自治情報センター(2004)『地方自治体新条例解説集2004年版』、公職研pp.49-63,151-183
大和市http://www.city.yamato.lg.jp/bunken/jyourei/020827link.html
練馬区http://www.city.nerima.tokyo.jp/kikaku/jichi/houkoku.html
|