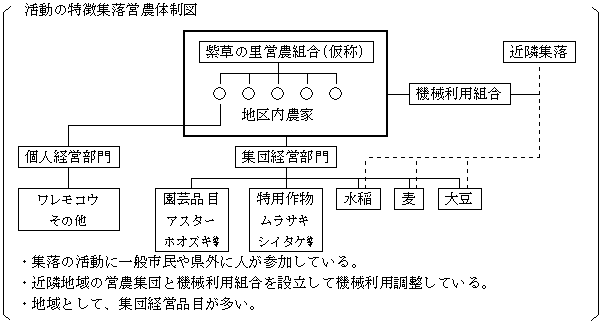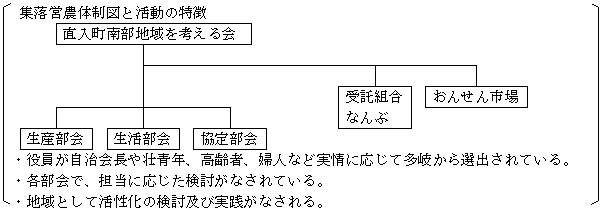九重野では基盤整備に伴い地域の担い手を選定し、彼らが中心となって受託組合を結成して地域の農作業を受託している。近隣に次倉地区があり、この地区でも集落営農に取り組んでいるが、九重野地区と次倉地区の間にある地域は営農の組織化が遅れており、九重野地区と次倉地区が間にある地域の営農を支援している。
男性の活躍に刺激されて女性達の活動も活発となり、婦人部の「若葉会」で「みらい香房若葉」を起こし、地域で生産された米・麦・大豆や野菜などを加工して販売している。
地域には均等に水を3地区に配分できるようにした円形分水があり、この施設は、水争いを解決しただけでなく地域の和を形成したシンボルともいえるものとなっている。 将来に向けて地域営農を確立するため法人化について現在検討が進められている。
| 九重野地区 |
|
|

|
|
 |
|
集団で管理する大豆
|
|
九重野のオペレーター
|
| |
|
|
 |
|
 |
|
円形分水
|
|
加工品各種
|
志土知地区では、集落営農の取り組みの中で園芸品目や特産農作物の取り組みも行われており、特にムラサキの栽培は全国的にも珍し取り組みであり、栽培は極めて難しく、試行錯誤の中でようやく本格栽培が可能になってきた。
一般市民も参加した古代紫草復興に向けた活動がの中で紫根染め製品も完成し、今年3月には全国各地から染色を愛好する人々が志土知に集まり染色交流会を開催した。
このように志土知地区はムラサキをとおして地域の情報を発信、また、交流も期待できるようになり、「紫草の里営農組合」として法人化を目指しており、本市では最も早く集落営農が法人化できると見込まれている。
| 志土知地区 |
|
|
 |
|
 |
|
ムラサキ
|
|
ムラサキの根(紫根)
|
| |
|
|
 |
|
 |
|
紫根染め製品
|
|
紫草染色交流会
|
直入町南部地域を考える会は1997年に設立され、この会には各集落の様々な立場の人から代表が参加し、農業生産や生活環境、直売活動などについて話し合いがなされ、歩きながら行った点検活動の中から、直売所の開設、地域シンボル権現山の整備、温泉資源の整備、農道の整備などが提案され、そのほとんどが実現できた。
1998年から冬場の農地利用が少なかったことから、菜の花を活用した農地の高度利用や地力増進の取り組みが始まり、併せて「菜の花交流会」開催されるようになった。
直入地域全体への波及効果も高く、直入各地で受託組合が設立され連絡協議会により作業料の調整がされている。
組織化今後は稲作の低コスト化や「おんせん市場」と地域加工所を活用した直販活動の拡大、そして、菜の花を利用した都市交流等により地域の活性化を図ろうとしている。
| 直入南部地区 |
|
|
 |
|
 |
|
水稲収穫作業
|
|
菜の花交流会
|
| |
|
|

|
|
秋の交流会
|
3. 今後の課題
本市の集落営農は、古い時代から共同作業や機械の共同利用など少なからず行われていたが、近年は米価格の下落や担い手不足の解消、生産の効率化・低コスト化、そして、地域の活性化の手法として本格的に取り組まれるようになってきた。
今後は国の新しい施策と併せた取り組みが中心になると考えられるが、全市を見た場合集落営農に取り組んでいる地域は少なく、特に、高齢化の著しく後継者がいない地域では集落営農に取り組むことが難しい地域も多い。
また、集落営農に取り組んでいる地域においても、比較的若い専業農家が担い手となっていることが多いが、これらの農家は各自の経営規模が既に大きく、オペレーターとして作業受託を行う場合はある程度自分の経営を犠牲にしなければならないこともある。
さらに、園芸品目で規模の大きい農家が多くいる地域では個々の経営が主体となるため集落営農の展開が難しい場合もある。
その他、集落営農に取り組んでいる地域においても、後継者がいない地域もあり、これらの地域については集落営農が継続できるかどうかも将来問題になると予想される。
このように集落営農の今後の展開については大きな課題が多く、地域の状況を十分に把握しながら、場合によっては他地域と連携した集落営農の展開を図る必要がある。
例えば本市の特徴である標高差を活かして早い時期に田植えを行う高標高地帯と田植え時期の遅い低標高地帯とで共同で機械を購入、あるいはオペレーター及び田植機の派遣のなどの取り組みによって集落営農が遅れている地域を、集落営農が展開できるように誘導することも考えられる。 |