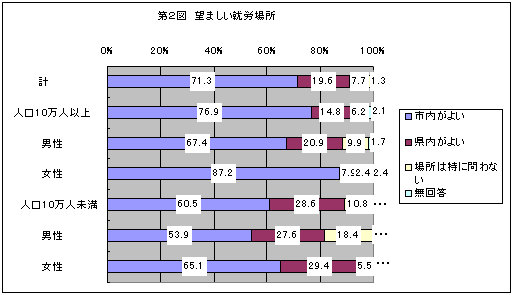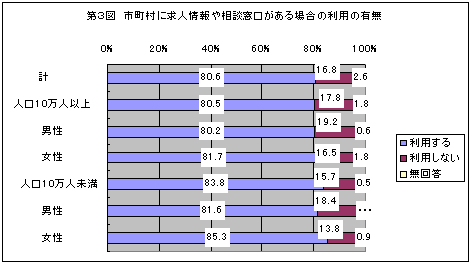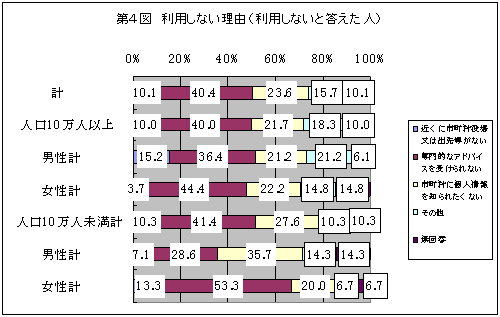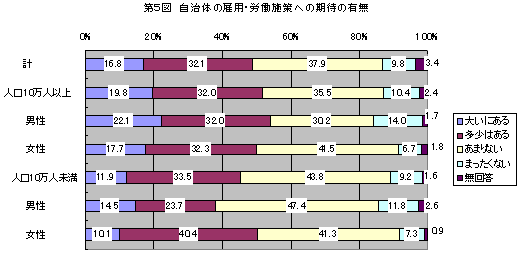【要請レポート】
|
自治体雇用・労働施策に関するニーズ調査結果の概要
富山県本部/富山大学経済学部 坂 幸夫 |
1. はじめに
本調査は、富山県内において求職活動中の人に対して、主に自治体の雇用・労働施策としてどの程度ニーズが存し、ニーズの中身としてはどのようなものがあるのかを明らかにすることを目的に実施しました。
以上の調査目的の背景にある問題意識は、以下のようなものです。富山県地方自治研究センター(理事長:竹川愼吾 以降自治研センターと略)は2005年度に県内自治体の雇用・労働施策の実施状況の調査を行いました。この調査は、県内におけるいわゆる平成の大合併の直前に実施したものですが、その目的は合併前、市民・住民にとって最も身近な自治体である市町村において雇用・労働施策がどの程度行われているのかを明らかにすることにありました。この調査結果によれば、富山市や高岡市といった県内の中核的自治体においては、一定程度雇用・労働施策が実施されているものの、それ以外の自治体においては実質的な取り組みはほとんどなされていないことがわかりました。周知のようにこの時期、広域合併に伴う自治体行政組織の再編と行政の見直しが進行しつつありましたが、上記の調査結果を受け、この機会を利用して雇用・労働施策への取り組みを求めることが喫緊の検討課題であり、かつチャンスであると考えました。
今回の調査は、市民・住民の雇用・労働施策に関わるニーズを把握することによって、自治体に対して、具体的に提案を行いうるようなデータを収集することを目的に実施しました。
2. 調査の実施主体および調査時期、調査方法
本調査の実施主体は、富山県自治研センターであり、調査を担当したのは同センタープロジェクトの雇用・労働政策部会です。
調査は2006年3月から4月にかけて実施しました。調査方法は、県内4ヶ所のハローワーク(ハローワーク富山、同高岡、同砺波、同小矢部)の前で求職活動に訪れた人に対して、調査員によるアンケート方式で行いました。
3. 調査の主な項目と調査票の回収状況
調査票は、部会メンバーによる数回にわたる討議を経て以下の項目が盛り込まれました。
①これまでの職歴、②現在の生活状況、③求職にあたっての希望、④求職情報、セミナー等の周知度・参加度、⑤自治体の雇用・労働施策へのニーズと期待、⑥性、年齢等回答者の主な属性。
調査票は全部で530枚が回収されました。各ハローワーク前での回収枚数は以下の通りです。なお「その他」とはハローワーク前以外で求職活動を行っていた方々に回答していただいた分です。ハローワーク富山=222枚、同高岡=145枚、同砺波=79枚、同小矢部=64枚、その他=20枚、計530枚。
4. 求職者の主な属性(第1表)
─居住地によって異なる求職者の像─
第1表 回答者の主な属性
| 平均年齢(歳) | |
||||||||||||||||
| 男性 | 女性 | 無回答 | 独身 | 親と同居 |
独身 | 単身 |
既婚 | 無回答 | 平均値 (回) |
4回以上の比率 | 仕事は何もしていない人の比率 | ||||||||
| 総計 | 46.8 |
51.5 |
1.7 |
44.6 |
26.6 |
10.8 |
59.8 |
2.8 |
2.3 |
20.3 |
70.2 |
||||||
| 人口10万人以上 | 50.9 |
48.5 |
0.6 |
46.6 |
24.9 |
13.0 |
61.2 |
0.9 |
2.4 |
20.8 |
70.1 |
||||||
| 男性 女性 |
100.0 0.0 |
0.0 100.0 |
0.0 0.0 |
|
31.4 18.3 |
19.8 6.1 |
48.3 75.6 |
0.6 0.0 |
2.5 2.2 |
28.3 12.6 |
72.1 68.9 |
||||||
| 人口10万人未満 | 41.1 |
|
0.0 |
40.2 |
30.8 |
7.0 |
59.5 |
3.9 |
2.2 |
20.0 |
70.3 |
||||||
| 男性 女性 |
100.0 0.0 |
0.0 100.0 |
0.0 0.0 |
|
|
11.8 3.7 |
39.5 73.4 |
3.9 1.8 |
2.4 2.1 |
|
|
||||||
| は比率が多め | は比率が少なめを示す。 |
回答者の主な属性を要約的に箇条書きで示すと以下のようになります。なお文中において回答者の居住地域として、中心地域と周辺地域という表現が出てきますが、中心地域とは人口10万人以上の地域を意味し、具体的には富山市と高岡市を指します。これに対し周辺地域とは人口10万人未満の地域、つまり富山市、高岡市以外の地域を指しますが、その大多数は人口4万人未満の地域です。
① 性別は、全体では男性が47%、女性が52%で、わずかに女性が男性を上回っています。地域別にみると、周辺地域では女性が59%と一層多くなっています。
② 平均年齢は男性が48歳で、地域差はみられませんが、女性は地域によって差異が生じており、中心地域では45歳なのに対し、周辺地域では38歳といった差が生じています。
③ 家族構成では、女性は居住する地域にかかわらず4分の3が「既婚」です。一方男性は地域によって違いが見られ、中心地域では既婚者と独身者はほぼ半々ですが、周辺地域では独身者が6割を占めています。しかもその多く(45%)は「親と同居」で、これは中心部の男性の比率(31%)を大幅に上回っています。
④ 現在の就労状況をみると、当然「現在は何もしていない」という回答が多い(70%)のですが、特に周辺部の男性はこの比率が78%と8割近くに及んでいます。それに対し、同じ周辺部の女性の3人に1人は現在「パートで働いている」と回答しています。
5. 注目すべき居住地別・性別にみた回答者の像
以上のようにみてくると、回答者の属性は、居住する地域や性別によって一定の片寄りがあることがわかります。
特徴が明瞭なのは、周辺地域です。すなわち同地域では女性の求職者がほぼ6割を占めていますが、その多くは30代後半と比較的若く、「子どもあり」の既婚者です。そのうちの3人に1人はパートを中心に現在も就労中です。
他方、同地域の男性は、年齢的には40代後半層が多いにもかかわらず、6割近くが独身者であり、しかもその多くは「親と同居」です。さらに現在の就労状況では「現在仕事は何もしていない」と答えた人が8割に近く、転職回数も多めです。
ところでこの調査において周辺地域とは、富山市や高岡市といった富山県の中心部以外の地域ですが、これらの地域は元来農業が中心の地域であるとともに、近年では県中心部へ通勤する人たちの新興住宅地という側面ももちつつあります。こうした地域性とこれまで見てきた回答者の地域別・性別の属性をつき合わせるなら、求職者に一定の像が浮かんできます。すなわち人口10万人以上地域の求職者は、都市部居住者の像にほぼ合致します。それに対し周辺地域の場合、女性は30代後半の既婚者で子どもがおり、生活費の不足分を補うためにパートで働こうとしている、ないしは現にパートで働いていますが、より条件のよいところを探しているといったイメージです。
他方同地域の男性の場合、年齢は40代後半ですが、独身者が多く、かつその多くは親と同居です。地域性を考慮した場合、家は第2種兼業で農業を営んでいる可能性が高いと思われます。推測をまじえて言えば、結婚した兄弟・姉妹は家を出ており、家に残った回答者が、多分70代に達しているであろう親と同居し、場合によっては介護をしているといった像が浮かび上がります。
ちなみにこの周辺部の農業後継者について、2005年農林業センサス(概数値)によって(北陸農政局富山事務所調べ)調べたところ、例えば独身者比率は、全体として農業後継者では高めではあるのですが、とりわけ山間地農業地域、および都市的農業地域と山間地農業地域の間に位置する中間農業地域ではかなり高いことがわかりました。かつて農業後継者の結婚難が社会問題になったことがありました。もちろん今もすべて解決された訳ではありませんが、問題なのはそれを引きずりつつも現在では、それらの人たちの中から求職活動する人がでているということ、つまり失業問題が生じているということだと思われます。
以下、調査結果を順次みていきます。
6. 求職者の現在の生活状態と求める仕事の条件
─半数は「今は困っていないがこの状態が長く続くと困る」─
(1) 現在の生活状態(第1図)
全体としては「今は困っていないがこの状態が長く続くと困る」が55%と半数強を占め、次いで「生活に困っており、早く何とかしたい」という困窮度の高い人が25%です。後者の比率が最も多いのは中心部男性の36%であり、逆に最も少ないのは同地域の女性の16%です。総じて女性は「生活に困っており、早く何とかしたい」という人は少なめです。なお周辺地域の男性も「生活に困っており、……」は29%と必ずしも困窮度は高くありません。当面住居は確保されていますし、兼業農家であれば、かつて親は正規社員・職員として勤めていたケースも少なくないでしょう。その場合親は厚生年金なり共済年金を受けている可能性は高く、そのために切迫した生活状態ではないのもうなずけます。しかし問題は今後であり、親と同居であれば必然的に介護の問題が生じ、老老介護に直面することもありえましょう。
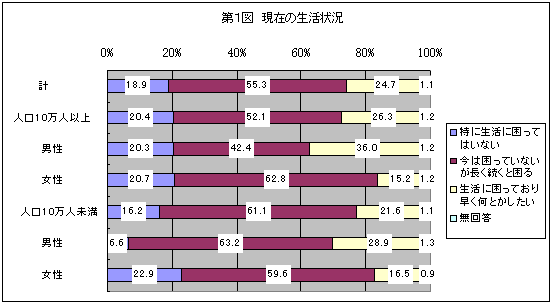
(2) 再就職先を選ぶ際に重視すること(第2表)
総計では「現在の生活水準を維持できる収入」をあげた人が38%で最も多く、次いで「今までの経験が生かせるような仕事」が26%で、この2つが他の項目を引き離しています。これを地域別・性別にみると、男性は居住地に関係なく第3位に「正社員として勤められること」があげられており、安定した職への希望の根強いことがわかります。
他方、女性は男性と異なり、「非正規やパートで働けること」が上位にあげられているのが特徴的です。そうした中で、周辺地域の女性は「現在の生活水準を維持できる収入」が44%と中心部の女性の同回答の比率(38%)を大きく上回り、仕事の目的が生活補助的色彩を有していることを強く感じさせます。と同時に「今までの経験が生かせるような仕事」(32%)や「専門的な技能・知識を生かせるような仕事」(15%)といった仕事の中身に関わる回答が多いことも見逃せません。これらの回答者は年齢も比較的若く、前職を育児等の理由で離れたものの、培った職能を生かした仕事につきたいという気持ちが強いように思えます。しかしいわゆる家庭責任のもとで先にふれたように「非正規やパートで働けること」が条件であり、そのために「不規則勤務や交代勤務がないこと」(16%)も相対的に高いウエイトを占めており、それらの条件のすり合わせが就職を難しいものにしているようにみえます。しかし生活補助的色彩が強いということは、収入水準にはこだわりが少ないということにもなり、そのことを前提にすればむしろこうした人的資源が周辺地域に少なくないことを企業に周知するとともに、条件のすり合わせ次第で例えば短時間正社員など、多様な働き方を念頭に求人誘導することなども考慮してよいように思えます。