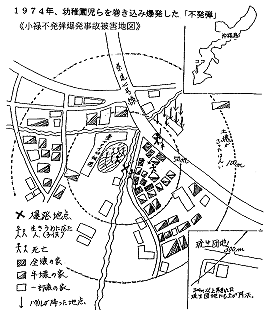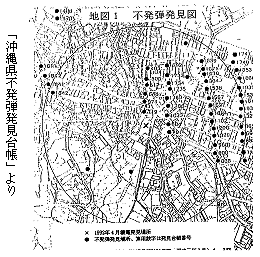3. ガマ・沖縄戦のタイムカプセル
ガマと呼ばれる自然壕は沖縄戦の際、日本軍の陣地となったり、住民の避難壕として用いられたりした。ガマの中は、ある意味「タイムカプセル」といってもよいだろう。61年前と同じ石や岩や土、足元をよく見ると、遺品や遺骨がいまだに残る。持参したライトを消せば、そこには1センチ先も見えない暗闇の世界が待っている。
しかしその闇の中こそ、当時の人々にとっては唯一、心が休まる場所であったことだろう。地上には、「鉄の暴風」と形容されるほど、爆弾や砲弾の嵐が降り注いだ。(南部地区では、1m2当たり52発もの砲弾や爆弾が打ち込まれた計算になるという。)
極限状態のガマの中で、さまざまな悲劇が起きたことも事実だが、ガマがあったことで、多くの住民や兵士たちの命が助かったことは、紛れもない事実だろう。
時が流れ、否応なしに戦争体験の風化がすすむなか、ガマなどにおける体験学習はさらに重要になってくる。しかし、ここで問題となるのは(県外の人には意外なことかも知れないが)、沖縄県内の児童・生徒や教職員、そして一般の人々の「ガマ体験率」が実はかなり低い、ということ。
戦争中の強烈な体験を持つ者があまりに身近にいすぎて、ガマが一種の「タブー視」されていた時期があったことは否めない。しかし、今こそそれを乗り越えるときに来ていると思う。
(1) 子どもたちにガマ体験を呼びかける
昨年、戦後60年の節目をひとつのきっかけとして、クラスの子どもたちや保護者を対象に「ガマ体験」を呼びかけたところ、11人の子どもたちが参加してくれた。全員が初めての「ガマ体験」。ガマに入ることをまるで「映画のセットの見学」的な感覚を持つ彼らに、どう理解させるか…。
話のはじめは、やはり最初の「学校が戦跡!」だった。
① HPの地図を拡大し、そこに子どもたちの自宅を記入させる。
・彼らの家が、米軍の侵攻ラインと日本軍の陣地との間にはさまれる姿が見事なまでにあらわれた。
② 学校やその周辺から、最近、不発弾の発見が相次いでいること。
③ 首里西方の「シュガーローフの戦い」等に比べ、首里東方陣地をめぐる戦いについては、あまり知られていないこと。
④ なぜ住民は、戦争末期になってもなかなかガマから出なかったのだろう。
・中国やアジア各地の戦線における日本軍兵士の実態→「オレたちもやった。当然、米軍もやるだろう……。」
⑤ 6月23日は何の日?
・牛島司令官の「最後の命令」を取り消す者がいないまま、沖縄戦はいつまでも続いた。6月23日以降ピタッと戦闘が終わり、そのまま沖縄に平和が訪れたわけではないこと。
組合支部のワゴン車を借り、土曜日の午後、子どもたちとともに南部戦跡をめぐった。沖縄本島南部は、「沖縄戦最後の激戦地」と表現されることが多い。しかし、1945年5月末、軍司令部が首里から撤退した後の戦闘は米軍にとって、もはや掃討戦。8割もの戦力を失いながらなおも戦い続けることの意味を考えてほしい。
住民を巻き込みながら、「本土決戦・国体護持」のための時間稼ぎをすること。それこそが沖縄戦の持つ意味だった。
コースとしては、
城東小出発 → 南風原文化センター → アブチラガマ →
→ クラシンジョウ(ガマ)→ 魂魄の塔(車窓から)→ 城東小着
|
というルートを選んだ。 短時間にふたつのガマ、というけっこうハードなコースだったが、子どもたちはよくついてきてくれたと思う。
できれば、保護者も一緒に参加して欲しかったが、それは今後の課題としたい。子どもたちの日記によると、その日の夜は彼らの話(体験談)を中心に、家族みんなでガマや集団「自決」のことなど沖縄戦のことを話し合った、という内容が多かった。
(2) 校内研修でガマめぐり
今年7月末、夏季休業中の職員研修の一環として、「戦跡めぐり」を行った。沖縄の教職員の「ガマ体験率」が低いことを職場の仲間に話し、なかば強引に夏休み中の校内研修として取り組んだところ、多くの仲間が賛同し参加した。
◎コース ナゲーラ壕(車窓)→ 南風原陸軍病院跡(車窓)→ アブチラガマ
→ 工業健児の塔 → 平和の礎 → ずゐせんの塔 → 魂魄の塔 → 城東小へ
参加者27人のうち、実際にガマに入った経験のある者は4人。それも「10年ほど前に一度入ったきりで何も覚えていない」、「7、8年前に入ったが、どこのガマだったかわからない」など、自らのガマ体験をもとに平和教育を行う、ということからは程遠い。
バスの中では学徒隊とその引率教員に関すること、そして戦前から戦中にかけての「皇民化教育」について重点的に話した。天皇(制)のために命を捨てることをいとわない児童・生徒を育てること、それが当時の教員に課せられた最大の使命だった。
① 引率教員がつかなかった学徒隊
② なぜ「ひめゆり学徒隊」だけが有名なのか
皇民化教育とは、国家ぐるみで「弱い者いじめ」を行っていた教育かもしれない。強い兵士になれないような、体の弱い者・力のない者・視力の弱い者・運動能力の劣る者、そして障害者など「弱者」は徹底的に差別され疎外された。その先頭に教員が立っていたことは、残念ながら明らかであろう。
「昔のことだから、今の教員とは関係ない」ではなく、その責任を負いつつ「教え子を再び戦場に送らない」というスローガンを今一度、かみ締めていかねばならない。
4. 保護者への宿題(「おかあさんの木」の感想文)
〔昨年度の取り組みから〕
平和教育は学校の中(授業等)だけでなく、地域・保護者と一体となって取り組むことが大切である。クラスの子どもたち、そして保護者とともに平和について考えたいと思い、保護者による「おかあさんの木」の感想文づくりに取り組んだ。
物語:「おかあさんの木」について
大川悦生さんの短編。5人の男の子を次々と兵隊に取られる母親の姿をえがいた物語。激しい戦闘シーンがあるわけではなく、静かに話がすすんでいくが、戦争のむなしさや悲しさを強く訴える作品。
以前は小学校の教科書にもけっこう掲載されていた。しかし、国語版「教科書問題」的なことから、次第に消えていった経緯がある。(内容の一部書き換え等。ほぼ同時期に起きた国語版「教科書問題」には、他に「かさじぞう」や「大きなかぶ」などの民話作品がある。)教科書問題は、社会科だけのことではない。 |
「おかあさんの木」の物語と感想文のお願い、それに原稿用紙を添付し、「みなさんのお母さんやお父さんへの宿題です」と切り出すと、子どもたちから歓声が上がった。「いつもの仕返しをしてやる!」などと物騒なことを言う者もいる。
保護者にとってはおそらく初めてのことなので、はたして何編の感想文が集まるか、とても不安だった。だが、作品の内容に共感してくれたのだろう、なんと20人以上の方が感想文を書いて提出してくれたのだ。
親子で一緒に読んだ、祖父母も交えみんなで物語の感想を述べ合った…、などということも書かれており、かなり大きな反響を呼んだことと思う。
当然、保護者の中にはさまざまな考えや思想をもつ方がいる。そのことに萎縮してしまうのではなく、逆にそれを当たり前のこととしてとらえ、真正面から取り組みお互いに向かい合うことで新たな道が開けてくるのではないだろうか。
「親への宿題」と同時進行的に、授業の中で子どもたちにも感想文を書かせていた。現代っ子たちは普通、感想文が大の苦手である。しかし、この「おかあさんの木」に関しては、何も言わなくてもほとんどの子が心を込めて書いてくれた。
5. 沖縄は「癒しの島」か!
沖縄ブームが続いている。NHKの朝の連続ドラマや、沖縄出身のミュージシャンたちの活躍も大きいだろう。そして最近、観光やダイビング、リゾート地めぐりなどとともによく耳にするのが、「癒しを求めて」沖縄に来た、という人々。果たして本当に沖縄は「癒しの島」なのか。
全国最下位の県民所得に全国最高の失業率、長寿県のブランドも今や昔。全国の75%の米軍基地が集中し、米軍人・軍属による犯罪(特に性犯罪)も突出している。これで本当に「癒しの島」といえるのだろうか。
「癒し」を強調する人たちの言葉に、「沖縄のオジイ、オバアたちはかわいくて優しい」というのがある。だが、沖縄県の高齢者の精神疾患率が、全国平均と比べて異常なまでに高いという事実をおそらく知らないだろう。
「ありったけの地獄を集めた」と形容される凄惨な沖縄戦を体験し、その後の60年余りを生きてきた「オジイ、オバア」たち。時にはトラウマに苦しみながら……。オジイ、オバアのもつ優しさや強さは、深い悲しみやつらさを長い時間をかけて乗り越えてきたことによるものなのだろう。
6. 終わりに ~エイサー禁止令と今後の沖縄~
沖縄の芸能を代表するものに「エイサー」がある。勇壮で小気味よい太鼓のリズムと、きりっと決まった衣装が実にかっこいい。最近、全国の小中学校の運動会や青年団の催し等でもよく行われると聞く。また、甲子園で沖縄代表の試合が行われる時の「応援の定番」といってよい。
このエイサーが10年ちょっと前、高野連の指示により甲子園の応援席から「追放」されたことがあった(現在は復活)。理由は「華美にして奇異」。しかし甲子園の応援に、華美でないもの、奇異でないものがあるだろうか…。
個人的な感情かもしれないが、当時の高野連の指示(通知)には、エイサーに象徴された沖縄文化に対する、ある種の「嫌悪感」のようなものが感じられてならない。日頃あまり見慣れないもの、なじみの薄いものに関して端から拒否反応をもつ、という姿勢である。おそらくそういった感情が過去の日本において、アジア諸国に対する蔑視を生み、あの忌まわしい戦争へと進む悪しき「原動力」のひとつとなったのではないだろうか。
「新しい歴史教科書をつくる会」主導による中学校用教科書が、自国(日本)の優位性を強調するあまり、他国(特にアジア諸国)に対し、きわめて無神経な記述をしていることとの同一性を強く感じる。
ただ、おのれの文化(エイサー)を「華美で奇異」とまで言われながら、抗議など何のアクションも起こし得なかったウチナンチュの弱さも特筆ものかも知れない…。
よく、沖縄経済を支えるものは「3K」といわれる。すなわち、観光・基地・公共事業である。かつて県経済の80%以上を占めた基地関連収入は、いまや5~6%程度。今後、公共事業(工事)依存型の体質を改め、真に自立した発展を目ざすため、立ち上がらねばならない。
1995年の少女暴行事件に端を発する「県民大会」、そして2004年の米軍ヘリ墜落事故等、幼い少女や多くの人々の悲しみや苦しみを乗り越え、沖縄はいま大きく動こうとしている。強さと優しさを持ちながら、これからもしっかりと歩き続けたいと思う。 |