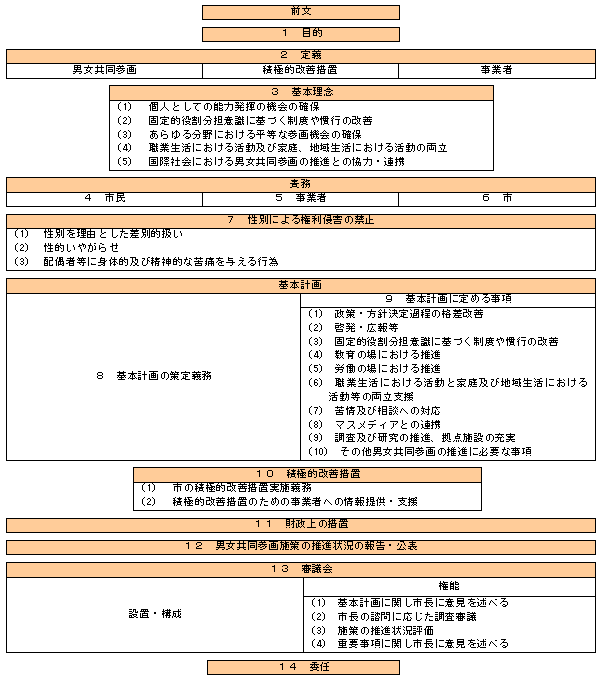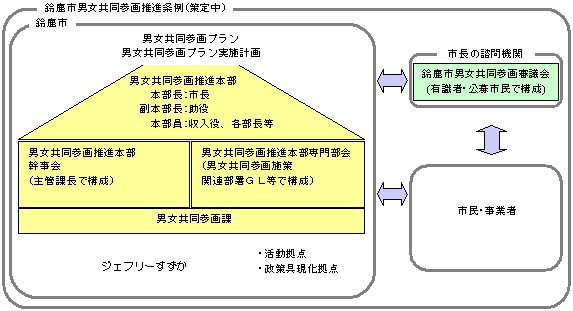【自主レポート】
|
鈴鹿市の男女共同参画施策推進システムづくり 三重県本部/鈴鹿市職員労働組合・生活安全部男女共同参画課 丸山 桃子 |
1. はじめに
男女共同参画社会の実現は、21世紀の最重要課題の一つとして、1999年6月には男女共同参画社会基本法が制定され、現内閣においては担当大臣が入閣するなど、国においても積極的な推進が図られています。
男女共同参画社会形成の促進は、国際社会における取り組みと密接な関係を有する一方で、市民、事業者、行政の協働なくしては実現しえない取り組みでもあり、地方分権の時代において、市民に最も身近な行政機関である市における地域の特性に合わせた更なる取り組みが重要とされています。
鈴鹿市では、1995年以降、『鈴鹿市男女共同参画プラン』の策定、改定の作業を市民と協働で行ってきており、その中で、施策の推進体制や計画の進行状況を評価するためのシステムの整備、鈴鹿市男女共同参画推進条例の必要性などを確認し、男女共同参画施策推進のためのシステムづくりにも取り組んできました。
2. 鈴鹿市男女共同参画プランの策定~鈴鹿市男女共同参画審議会からの提言
鈴鹿市では、1992年に市民対話課に婦人行政係を設置し、女性行政に対する具体的な取り組みを開始しました。
その後、1995年には、識見者及び市民で構成する『鈴鹿市女性問題懇話会』を設置し、幅広い意見の聴取に努めながら、1997年に「一人ひとりの生き方を尊重する社会づくり」を中心目標とする、『鈴鹿市男女共同参画プラン』(以下「プラン」という。)を策定しました。
この計画の期間は、1997年度から2006年度までの10年間で、その間、拠点施設として男女共同参画センターが整備されるなど、より一層の施策の推進が図られてきました。
一方で、プラン策定から7年を経てきた中で、男女共同参画施策には、新たな法制度との整合や少子高齢社会等への対応が求められ、また、市政全般にわたる男女共同参画施策についての総合的な調整機能や推進体制、計画の評価システムの改善など、現行プランでは対応しきれない様々な課題が生じてきていました。
鈴鹿市では、こうした諸課題に対応するため、『鈴鹿市女性問題懇話会』を発展的解消し、2003年1月に『鈴鹿市男女共同参画審議会』(以下「審議会」という。)を新たに設置、審議会に対し、「鈴鹿市男女共同参画プラン改定の基本的考え方について」の諮問を行いました。
また、2003年9月には、現状を正確に認識するための市民アンケートを実施しました。その結果には、依然として男性優位社会の現状が顕著に表れ、より一層の取り組みが必要であることが確認されました。
| 市民アンケート(抜粋) 社会の分野別の男女の平等感(平等であると感じている人の割合) ・学校のなかで……64.9% ・地域活動の場で……35.2% ・法律や制度の上で……30.3% ・家庭のなかで……30.2% ・職場のなかで……20.5% ・しきたりや慣習で……10.0% |
その後、2004年2月に、審議会からプラン改定の考え方についての提言書(以下「2004年2月提言」という。)が提出され、より実効ある施策を推進するため、予定より2年早く、プランの改定作業を開始しました。
「鈴鹿市男女共同参画プラン改定の基本的な考え方について(提言)」概要 1. 目標、施策の体系について 2. 新たに盛り込むべき課題について 3. 強化すべき課題について 4. 実効ある計画の推進について あとがき |
3. 「男女共同参画プラン ― 改定版 ― 」の策定
プランの改定にあたっては、2004年2月提言に従い、市民と庁内の職員の協働による男女共同参画プラン改定ワーキンググループの作業を通して施策を取りまとめましたが、このワーキンググループの市民メンバーについては、2003年度に当該改定作業を視野に入れた「参画ぱーとなー研修講座」を実施しており、その修了生の中から公募を行い、男女それぞれ3人の参画を得ました。
職員メンバーについては、男女共同参画に関連のある主要な課から、女性6人・男性5人が参加しました。
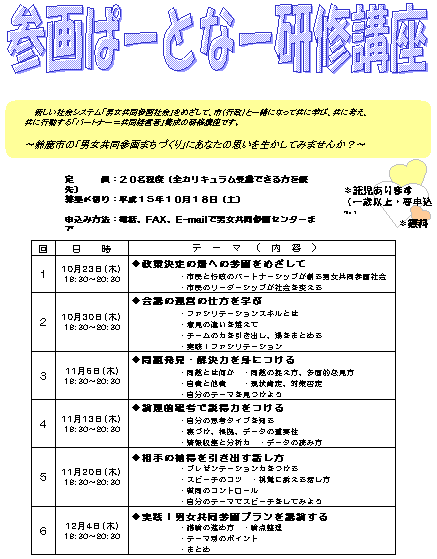
こうして組織したワーキンググループによる施策の取りまとめの後、庁内意見の募集、パブリックコメント、審議会への報告などを経て、2005年6月に『鈴鹿市男女共同参画プラン ― 改定版 ― 』(以下「プラン改定版」という。)が策定されました。
プラン改定版は、その期間を従来のプランの半分の5年間とし、基本目標は、従来どおり「一人ひとりの生き方を尊重する社会づくり」とするものの、提言や市民アンケート(2003年9月実施)の内容を反映し、基本目標を達成するための5つの基本課題、基本課題達成のための15の施策の方向性を次のとおり掲げています。また、計画の推進の項には、従来のプランにおける課題であった庁内推進体制の整備や進行状況の評価などについて定めています。
鈴鹿市男女共同参画プラン ― 改定版 ―(概要)
人 ひ と り の 生 き 方 を 尊 重 す る 社 会 づ く り |
1 政策・方針決定過程への女性の参画 | (1) 市政への女性の参画拡充 (2) 市役所等における女性職員の登用 (3) 企業・地域団体等における方針決定過程への女性の参画拡充 (4) 人材の育成 |
| 2 制度や慣行の見直しと意識づくり・教育の充実 | (1) 制度や慣行の見直し (2) 広報・啓発活動と生涯学習の充実 (3) 男女共同参画の視点に立った学校教育・保育の充実 |
|
| 3 労働の場での男女共同参画 | (1) 女性の就労環境の改善と就労支援 (2) 農林水産業・商工自営業に従事する女性の労働条件の向上 |
|
| 4 仕事と家庭生活・地域活動との両立支援 | (1) 子育て・介護支援策の充実 (2) 男女共同参画の家庭づくり (3) 男女共同参画の地域づくり |
|
| 5 社会問題化する人権侵害への対応と心と体の健康づくり支援 | (1) DV・セクハラ・児童虐待等人権侵害対策の推進 (2) メディアにおける人権尊重 (3) 心と体の健康づくり支援 |
画 の 推 進 |
推進体制の整備 | ① 庁内推進体制の整備 ② (仮称)鈴鹿市男女共同参画推進条例の制定 ③ 鈴鹿市男女共同参画審議会の設置 ④ 苦情等の相談調整機能の強化 ⑤ 男女共同参画センターの機能強化 |
| プラン改定版の進行管理と評価 | ① 客観的な評価システムの構築 ② 具体的事業を整理した実施計画の策定と担当課からの年次評価報告の義務付け ③ 鈴鹿市男女共同参画審議会による評価の実施 |
|
| 市民や企業、市民団体等との連携 | ||
4. 鈴鹿市男女共同参画推進条例制定への取り組み
国において『男女共同参画社会基本法』の制定、県において『三重県男女共同参画推進条例』の制定がなされてきた中で、『(仮称)鈴鹿市男女共同参画推進条例』の制定の必要性は、幾度となく議論にあがりました。
法や県条例が存在する中、ただ、市条例を制定するというのではなく、その必要性、内容などのあり方について慎重な議論を行ってきたためです。
そのような中、2004年2月提言の「実効ある計画の推進について」の項において、「市民、事業者、市が共通認識を持ち、それぞれの役割と責任を果たすために、また、地方分権時代において、まちづくりの方向性を地方自治体自らが主体的に選択し、責任を負うべきであることなどから条例化が望ましい」との旨の提言がなされたことにより、プランの改定作業と並行しながら、その制定に向けた具体的な検討が始まりました。
条例の策定に当たっては、検討段階からの市民参画を求めるために、2005年1月に識見者や市民で構成する『鈴鹿市の男女共同参画を推進する条例検討委員会』(以下「検討委員会」という。)を設置し、「鈴鹿市の男女共同参画を推進する条例のあり方について」の諮問を行いました。
なお、検討委員会の意思をより明確に条例に反映させるために「条例に盛り込むべき事項」という形の提言ではなく、「条文形式での条例案」の提言を依頼するという、鈴鹿市では初めての試みも実施しました。
検討委員会では、約1年間にわたる審議、鈴鹿市と検討委員会の共催によるパブリックコメントなどが実施され、2006年1月に条例のあり方についての提言書(以下「2006年1月提言」という。)が市長に提出されました。
「鈴鹿市の男女共同参画を推進する条例のあり方について(提言)」条例案の構成