【自主レポート】
大分県本部/日田市職員労働組合 |
1. 男女がともに担う市職労委員会の取り組み
本市は、「天領ひた」という土地柄なのか地域や家庭で古い慣習・考え方が根強く残っており、真の男女共同参画社会の実現には地域とともに取り組む必要があります。
このような状況の中、組合は「男女が共に担う市職労委員会」を設置し、まずは現状把握をするために「市職員アンケート調査」を実施しました。
夫婦間の役割分担では、「共に働き、家事・育児・介護も共に担当」を望んでいます。
職場における男女平等の状況については、「平等である(52%)」「不平等である(23%)」「わからない(25%)」となっており、職場環境について実際にあるものとして、「女性の管理職が少ない(74.6%)」「女性は仕事と家事をこなしている(67.8%)」「重要な業務には女性が少ない(59.0%)」という実態があるという結果がでています。このような職場の現状に対する意識としては「改善すべき」との意見が大半を占めていますが、「当然である(10.6%)」との回答も見逃せません。また、共働き職員で一方の管理職登用に際する他方の退職勧奨(強要)などがあるとの意見もありました。
(職場からの意見)
・少子・高齢化社会を迎え、女性の社会進出は不可欠である。
・女性の意識改革、男性の意識改革、男対女ではなく共に生きるという視点で考えなければ進まないと思う。
・行政が積極的に取り組み、女性職員を多くの職場へ配置して欲しい。
・男性から見て、女性はまだ優遇されている。男女共同参画はすぐには解決しないが、男性側からの理解と女性も積極的に参画していくことが必要。
・職場内での男女差別を感じることはあまりないが、家庭のことは全て女性では負担増になる。男性の「家事を手伝っている」という言い方は、内心、家事は女性の仕事という意識がある。家庭、社会での偏見や慣習を改めていく事が最重要である。
アンケート結果により、今後は働き方の見直しはもとより、女性の参画と能力を活用し、これまでの男性中心の固定的な性別役割分担体質の改善に努めるとともに、地域や職場の実態に即した行動計画策定に取り組む必要があります。
2. 男女が共に支える社会づくりのための日田市民意識調査
行政側も男女が共に支える社会づくりのために意識調査を行っています。
この調査は、市内に居住する20歳以上の男女1,444人から回答を得て、市民の家庭生活・職場・社会活動などの様々な場面における男女の意識や実態を把握し、基本計画の第二次行動計画策定の基礎資料とするとともに、市民の男女共同参画に関する意識啓発を行うことを目的として調査しています。その結果、「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識については、4割の人が否定的な考えを持っていますが、家庭や職場、地域等、分野ごとの男女平等の状況では、多数の分野で「男性が優遇されている」と感じています。また、職場における男女差別について、約半数の人は差別はないと回答していますが、「賃金に格差がある」「能力を正当に評価しない」「昇進・昇格に差別がある」と感じている人がいることも事実です。
3. 同一生計職員給料20%削減問題
2006年1月、市長は組合に対して「厳しい財政状況が見込まれるため、市民から指摘をされている共働き職員の給料の一部(20%を2年間)返上を該当職員と協議のもと自発的に返上していただきたい」と通知してきました。
これを受けた組合は、「このことは共働き職員とそれ以外の職員を差別することになり、憲法、法律で保障される法の下の平等を侵害するため、協議すること自体が差別の助長にしかならない。したがって、当該申し入れは受け入れられない。」と市長に回答しました。
さらに、「市民からの指摘」については、「互いに尊重しあう社会の実現」を目指す市長の立場からすれば、むしろ当該市民に対してその差別性を「啓発する立場」にある。と申し添えました。
組合はその後も、法的問題や差別性を指摘し当局を追及しました。当局のマスコミ発表で全国的話題となり様々な議論が交わされた結果、市長は「総務省次官のサジェスチョン(暗示)」を受けて、条例案白紙撤回しました。しかし、今回の条例案が差別的取扱で違憲であることなどについての見解は述べられませんでした。
組合は、市長の職員に対する謝罪をもって、収束することとしましたが、「条例案のもつ差別性の認識」については、改めていないことから、部落解放共闘日田市民会議等市民団体と共にその差別認識を糾す取り組みを行うこととしました。
4月から解放共闘日田市民会議とともに、共働き条例にかかる市長発言に対する抗議行動として、市民に「市長発言の差別性」を伝えるためにビラ配布行動を行いました。
また、自治労大分県本部顧問弁護士を講師に招き、市長発言のどこに差別性があるのか、何が差別行為なのかを学習するために「同一生計職員給料20%削減案の差別性」と題して講演会を開催しました。
講演会の中で、同一生計職員の差別的取り扱いは、男女共同参画社会の実現と矛盾している。市長に仮に差別意識がないとしても、差別を意識化していないなかにその差別性の深刻さが潜んでいるといえる。また、現代社会でたえず差別的取り扱いが繰り返されていることを直視すると、憲法尊重擁護義務を負う自治体の首長がこの提案を行うこと自体が歴史に逆行し、歴史的評価に耐えないとしました。
4. 組合としての法的見解(問題点)
当局から今回の問題で提案を受けたときに、「まさか」というのが率直な感想でした。
そして、あり得ないことですが、仮に合意しようとしても法に反することを組合として合意することはできませんから、交渉の余地はありませんでした。当局側はその点を理解していましたし、幹部職員としてまた行政職員として市長をとめきれないところに、市長のパワーハラスメントが隠されていたのかもしれません。以下は法的問題として当局に説明した内容です。
① 憲法第14条では「すべての国民は、法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」と定められていることから、明らかに憲法違反と考えられる。
② 同一生計の職員で想定できる構成は親子・夫婦・兄弟姉妹であり、今回対象となる33世帯はすべて共働き世帯となっている。親子・兄弟姉妹の場合は市役所という職場を共に選択したことにより給料の削減を受けることになり、夫婦の場合は市役所という職場同士で結婚することにより給料の削減を受けることになり、それぞれ憲法第22条の「職業選択の自由」と第24条の「婚姻の自由」に抵触するものと考えられる。
③ 地方公務員法第13条では、「すべての国民は、この法律の適用について、平等に取り扱わなければならず、人種、信条、性別、社会的身分または門地によって、差別されてはならない」としている。また、労働基準法第3条でも「使用者は、労働者の国籍、信条、または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」としている。
このことからも、明らかに違法と考えられる。
④ 地方公務員法第24条では、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」と定められ、職務給を原則としていることから、明らかに違法と考えられる。
⑤ 地方公務員法第24条では、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」とも定められている。国や他の地方公共団体では前例がなく、民間でもこのような事例は把握できなかった。日田市のみ実施することは、他の事例がない以上、明らかに違法と考えられる。
⑥ 市長は、地方公務員法第24条の「職員の給与は、生計費……を考慮して定めなければならない」を根拠に条例を提案するとしているが、この条文は個人を対象としたものではなく、職員全体の賃金水準を対象にしたものであり、何ら合理性はない。この生計費を根拠とする給料の削減は、明らかに違法と考えられる。
⑦ 今回のように、一般職員全体を対象としたものではなく職員の一部を対象として給料20%削減を実施する場合の地方公務員法の取扱は、第27条「すべての職員の分限及び懲戒については公正でなければならない。職員は、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない」が考えられる。しかし、この条文は職員個々に処分を行う必要がある場合に限られるとされている。
また、もう一つの取扱は、第29条「職員が次の各号に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職または免職の処分をすることができる。法律・条令・規則・規程に違反した場合。職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合。全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合」が考えられる。
それぞれは、処分による降給であり減給であることから、生計を一にすることを理由とする処分は不可能であるため、地方公務員法に基づく給料の削減はできないものと考えられる。
⑧ 憲法第11条「基本的人権の尊重」や憲法第13条「個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重」はもとより、内閣府や総務省を中心に取り組んでいる「男女共同参画社会基本法」の趣旨を鑑みるとき、時代の趨勢と逆行するものと考えられる。
⑨ 今回の条例案の発表にともない、共働き世帯に対する大きなプレッシャーとなり、女性の社会参画にマイナスの要因を働かされることに成りかねない。また、少なくとも、日田市職員や地方公務員だけの問題ではなく、労働者全体に影響を及ぼす問題であると考える。
⑩ 憲法や法律を超える条例の制定は違憲であり違法であるため、たとえ可決されても無効である。
 |
|---|
|
市長の差別性を問いただす!! |
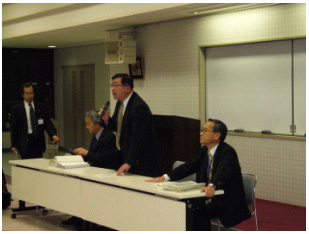
|
| 条例案は白紙撤回 |
|---|
5. 男女がともに担う自治労運動の推進に向けて
今回の市長提案にみられる差別意識、職員意識調査にみられる実態等が個人の個性や能力を妨げているのではないでしょうか。また、男女共同参画社会を実現するためには、市民の牽引的役割を果たすべき市職員が率先して、男女が共に働きやすい労働環境づくりに取り組む必要があり、今後とも男女共同参画社会実現のための啓発が必要といえます。
さらに、男女平等参画は、組合運動でも組織強化にとって重要です。男性中心の運動にするのではなく女性組合員が抱えている問題を組織全体の問題として男女がともに担って組合運動をつくり上げていくことが必要です。
市職労は、地域や職場で抱えている課題を解決するために、自治労方針にそって「男女がともに担う自治労第3次計画」の具現化に向けて、あらゆることに対して目標値を30%に定め取り組んでいきます。