【自主レポート】
|
市民と行政の協働による松江市の清掃事業のあり方 島根県本部/松江市職員ユニオン |
1. 清掃事業の沿革
清掃事業は人々の生活様式の変化とともに大きく変わってきており、廃棄物に関する法律もその目的を生活環境の衛生保持から地球規模の環境保全を目的とした内容へと変貌してきた。
高度経済成長期には産業の発展とともに消費生活が進展し、ごみの質は多種多様なものへと変化し、排出量についても増加の一途をたどってきた。そうしたなか、1970年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が施行され、事業所の産業廃棄物の処理責務について規定がされた。しかし、その後もごみ排出量は増大し続け、地球温暖化や限られた地球資源の確保、廃棄物最終処分場の残余年数の圧迫など環境保全全体の問題へと発展してきた。
こうした問題を解決するため、大量廃棄型社会構造を環境への負荷が逓減される循環型社会構造へと変えていくことが最重要課題となってきた。1991年には廃棄物処理法の大幅な改正、ならびに再生資源の利用の促進に関する法律(旧リサイクル法)が施行され、廃棄物の発生抑制と分別・再生の適正処理の明確化、有害廃棄物や処理施設に対する規制の強化、不法投棄に対する罰則の強化改正がされた。さらに2000年には「循環型社会形成推進基本法」が施行され、容器包装リサイクル法など本格的に循環型社会に向けた具体的な法体系が整備されてきた。
2. 松江市の清掃事業
松江市においては、もやせるごみ・もやせないごみ・粗大ごみの収集に加え、ごみ減量化とリサイクル推進の取り組みとして、1992年より古紙・布類の資源ごみ分別収集を開始し、現在では15種類(可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・新聞紙・雑誌類・段ボール・布類・牛乳パック・ペットボトル・ビン類・カン類・容器包装プラ・容器包装紙・廃食油・乾電池)の分別収集を実施している。
ごみ分別の市民への指導啓発については、ごみ収集時に清掃作業員が分別不徹底のごみにステッカーの貼付を行っている。戸別収集など排出者が特定できる場合はその場で指導を行い、ごみ集積所など排出者が特定できない場合は後日報告書を基に指導員が指導・啓発を行っている。公民館・自治会・各種団体に対しても説明会などを通じて分別指導、リサイクル啓発を行っている。また、昨年より生ごみ減量対策として堆肥化プラントを実施しており、生ごみ処理器の普及とともに一層の普及活動が急務となっている。
ごみの最終処分場の逼迫対応策として、西持田のエコステーション松江で不燃ごみの減容処理を行っている。2009年にはガス化溶融炉焼却施設の建設が計画されている。この計画では新ごみ処理施設の処理能力が既存2施設の日量300トンを下回る250トンを検討しており、年間1万4千トンのごみ減量をしていかなければならない。これによる建設費削減効果は30億円にのぼり、4年間という時限的計画の中で、市民への一層の啓発と市民活動の活性化、事業所の分別強化や分別した資源ごみ受け入れ体制の構築を進めていかなければならない。
3. 具体的な問題と対策
(1) ごみの減量化を進めていくために
① 目的 家庭ごみ分別の推進
2004年に旧松江市では、年間4万トンの可燃ごみを焼却処分しており、うち2.3万トン(57%)が家庭からの搬入ごみとなっている。2005年度の旧松江市地区のごみ組成分析結果では、可燃ごみの中に資源化が可能な物が重量で20%、容量で44%含まれており、厨芥類残渣は重量で58%、容量で20%含まれている。不燃ごみについては資源化が可能な缶・ビン・ペットボトル・プラスチック製容器関係のごみが重量で約37%、容量で約67%含まれている。この結果から再資源化に向けた分別が進んでいないことが明らかである。今後はごみ分別の推進及び、ごみ減量化への意識啓発をより効果的に行っていかなければならない。
② 対策 モデル地区による家庭ごみ減量化の推進
これまで松江市が行ってきた指導・啓発に合わせて、家庭ごみ減量化「モデル地区」事業を推進していくことが必要である。「モデル地区」では(ア)設定した品目の収集を行い、分別不徹底のごみにはステッカーの徹底、きめ細かい指導・啓発を行う(イ)分別状況を細かく把握した上で、ごみの適正処理について市民・自治会・公民館へ指導・啓発を行う(ウ)ごみ減量化の趣旨説明とともに生ごみ処理器の普及推進を行う(エ)モデル地区同士の分別状況の比較や生ごみ処理器普及状況を広報やエコタウン松江などで公表していくことで住民の分別意欲に繋げていく。モデル地区の選定は、核家族化や学生・企業による転入や転出の多い旧松江市を中心に小単位地区を設定し、組成分析の結果から一定の基準へ適正化が図れれば新たなモデル地区を設定し収集・指導を行っていき、市内全域に取り組みを進めていく。(別紙モデル例参照)
モデル地区の実施例
|
|
|||
| 公民館区 | 小自治会区 | 地区を数区(法吉地区など) | |
| 全品目 | 全品目 | 地区ごとに品目を設定 | |
| 組成を通じて状況を把握し、全ての世帯に指導・啓発を実施 | 組成を通じて状況を把握し、全ての世帯に指導・啓発を実施 | 各地区の組成結果を公民館、自治会、広報などで公表し、地域からの啓発を求める | |
デメリット |
広い地区への指導・啓発を行っていくため、実施期間が長くなる | 地区が狭いため,きめ細かい指導啓発ができるが、小地区となる | より広範囲となるので細かい指導・啓発はできない。地区ごとの意識・啓発がメイン |
モデル地区実施計画
○モデル品目の収集運搬・組成分析・指導・啓発
モデル地区すべての世帯・公民館・自治会に対して、ごみ減量化の趣旨、指導・啓発、生ごみ処理器の普及依頼等を行う。
① 目的 事業所ごみ分別の推進
松江市南北の可燃ごみ焼却工場では、2004年度に4万トン(旧松江市)の可燃ごみが搬入されており、うち1.7万トン(43%)が事業所からの搬入ごみとなっている。これまで松江市は家庭ごみの分別を基本に市民に対して指導・啓発を行ってきたが、事業所可燃ごみは、厨芥類が約50%、古紙類が約40%であるため、いずれも堆肥化ならびに再資源化を行っていくことが可能である。今後は事業所に対しての分別強化を行っていくことで、循環型社会の形成とともに大幅な可燃ごみ減量を進めていく必要がある。
② 対策 事業所ごみ分別のシステム構築
急務となっている事業所のオフィスミックス古紙・生ごみ堆肥化を推進していくため、環境を創る企業の会に協力を得ながら、企業に説明・協力の呼びかけを行っていく。
現在、オフィスミックス古紙は、エコヒグチのみが無償で自己搬入の受け入れを行っているが、オフィスミックス分別を実施している事業所が少ないため回収指定業者も費用対効果が得られず本格的実施を行っていない。オフィスミックス古紙分別を推進するため、可燃ごみ搬入料金(もしくは指定袋)の値上げをするとともに資源化可能なごみの搬入禁止規定をつくり、南北工場で廃棄時のチェックを行っていく。合わせてオフィスミックス古紙および資源化可能なプラスチック類等の無料または安価での自己搬入受付を環境センター、南工場、北工場、エコステーション、川向リサイクルプラザ等で実施し、一層の分別促進を図る。
生ごみ堆肥化については、補助金による生ごみ処理機の普及を推進し、拡大生産者責任の観点から可燃ごみ搬入料金(もしくは指定袋)の値上げを実施し、分別を推進していく事業所は経費節減となるシステムを構築する。
事業所ごみ分別推進計画
○事業所対策班を設置
松江市全域の事業所に対して、資源化に向けた推進とオフィスミックス古紙搬入禁止の趣旨説明、分別の指導・啓発、生ごみ処理器の普及
○事業所可燃ごみ自己搬入時の指導
事業所ごみ搬入時のごみ分別確認と指導・啓発
オフィスミックス古紙、資源化可能なプラスチック類等の自己搬入受付
(2) 高齢者のごみ収集支援と地域コミュニティの基盤づくり
① 目的 高齢者支援の対策
高齢化・少子化が一層進み、住宅事情が変化していく中で、介護が必要な高齢者世帯に対し、地域みんなでいかに支えていくかが大きな問題となっている。高齢者や障害者の日常生活上の支援は、親類もしくは地域の方々により行われており、ごみ出しについても、地域の方々の支援で行われていることもある。
一方、2000年から介護保険制度が導入され、65歳以上の方々で寝たきり、認知、虚弱などで日常生活に介護が必要な方は、介護保険により必要なサービスを受けることができるようになった。しかし、介護保険認定で自立と判断された方でも一定の支援を要する方々がいることもあり、支援を充分に受けられず、ごみ出しに苦労している世帯もある。また、支援を受けている場合でもごみの排出時間が8時30分までであることから、地域もしくはヘルパーの方にごみを持って帰ってもらう例も少なくない。ごみの排出者責任が強まるなか、何らかの対策が必要となっている。
② 対策 ふれあい収集の実施
実際に親類・地域の方々からの支援も受けられず、ごみ出しに困っている高齢者世帯への支援として、松江市の職員が計画収集とは別に玄関口までごみを取りに行き、ごみ出しの補助をしていくことが求められている。また、収集時に一声を掛けることで安否の確認する「見守り」機能も合わせて行っていく。ごみの分別も多種多様になっていることから、それぞれの対象者に合わせた指導啓発も行うことができる。対象者は地域推進員の方々とも話し合い、親類や地域の方々、もしくは介護補助を受けていない支援を要する高齢者・障害者の方を対象に実施する。
こうした高齢者支援の基盤を行政が構築し、将来的に地域ボランティアの方々と協力してふれあい収集を行っていける体制をつくり、すべての地域の高齢者支援活動と地域コミュニティの構築に繋げていくことが行政の重要課題となっている。
※ ふれあい収集とは……
先進地事例
新たな市民サービスとして、自らが一定の場所までごみを持ち出すことが出来ない方々を対象にごみを直接、排出者宅前又は所定の場所まで収集しに行くことをふれあい収集という。
対象者(例)
以下のいずれかに該当し、身近な人の協力が困難で、自ら一定の場所までごみを持ち出すことができない場合とする。
(1) 高齢者
① 寝たきりや痴呆症などにより、介護を必要とする要介護者や自由な行動が困難な人で、65歳以上の一人暮らしの高齢者
② 同居する家族がいる場合についても、同居者が高齢者や虚弱者及び年少者等で、ごみを一定の場所まで持ち出すことができない場合
(2) 障害者
① 一人暮らしの障害者
② 同居する家族がいる場合についても、同居者が高齢者や虚弱者及び年少者等で、ごみを一定の場所まで持ち出すことができない場合
【実施している主な市】
大阪市・横浜市・川崎市・旭川市・所沢市・藤沢市・名古屋市・神戸市・海老名市・堺市・逗子市・長岡市・土岐市・一宮市・牛久市・松原市・摂津市・都城市・藤沢市など多数
【ボランティア活動の例】
横浜市は通学前の小学生が高齢者の家のごみをごみ集積所まで持ち出すふれあい収集を行い、地域と子どもたちのボランティア育成にも繋げている。
ふれあい収集実施計画
○ふれあい収集班
ふれあい収集の受付業務と実施
最初はモデル的に行うこととし、週2回の全品目収集として実施する。
安定稼動すれば全市での対応とする。
(3) 環境保全と環境美化対策
① 目的 環境美化対策
経済発展に伴う消費の拡大や消費者意識の変化などにより、ごみ量の増加とごみ質の多様化が進み、松江市においても一部の地域でごみのポイ捨てや不法投棄によるまちの美観や自然の風致が損なわれている。また、合併により行政区域が広がり、海岸や湖畔の漂着物についての対策を早急に確立していかなければならない。
不法投棄については、廃タイヤ、家電製品、消火器等、住民では処理が困難な廃棄物が多く、件数も軒並み増加傾向となっている。また、上水道の水源地に不法投棄がされることが多く、河川流域の環境汚染防止のため不法投棄防止対策の更なる強化が必要である。観光振興の面からも、多くの観光客が訪れる国際文化観光都市として美化運動を推進し、「きれいな松江市」をつくっていかなければならない。
② 対策 不法投棄・環境美化対策
不法投棄対策は、市民の環境汚染防止への意識改革を推進していくことが重要であり、住民との連携・協力体制の確立を図り、住民と自治体が一体となった不法投棄パトロールや不法投棄の撤去作業、不法投棄防止看板の設置等、様々な対策に取り組んでいく。
環境美化対策は、市民ボランティアと協力し、ポイ捨てごみの清掃活動やポイ捨て禁止に向けた取り組みを行っていき、合わせて海岸・宍道湖・中海の漂着物などの美化対策も実施していく。
すべての住民がきれいな松江市をつくる意識の向上と社会的モラルの構築が重要であり、行政・住民・事業所がそれぞれの責任を明確にし、水と緑あふれるきれいなまちづくりを進めていかなければならない。
不法投棄・環境美化対策計画
○不法投棄・ポイ捨て・漂着ごみ対策班
不法投棄・漂着ごみの撤去運搬、不法投棄・ポイ捨て防止看板の設置、
監視パトロール、まちの美化清掃
4. おわりに
時代が大きく様変わりするなか、時代に沿った環境行政の促進は自治体運営の責務となっている。ごみの減量化は自治体・市民・企業がそれぞれの役割を果たしていかなければならず、自治体は住民・企業にごみの減量化の趣旨、必要性を説明し、どれだけ理解が得られるかが循環型社会の形成に向けての重要なポイントとなっている。住民意識を高めるためにも行政に携わるものが率先して4R(リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル)運動を実施していき、ごみの減量化に職員一人ひとりが努め、職員から周りの人へと、取り組みを広めていく必要がある。
また、高齢者支援対策など、市民が本当に必要とするサービスを行政の責任として担っていくことが重要であり、住民サービスの的確な把握に努め、松江市環境行政がより一層、充実し発展するよう取り組んでいかなければならない。
| 4Rとは Refuse(リフューズ)・ごみとなるような不要なものは断り、購入しない。 Reduce(リデュース)・ごみとなるような物は買わない。ごみそのものを減らす。 Reuse(リユース)・繰り返し使えるものを購入する。 Recycle(リサイクル)・資源化されたものを再利用する。 |
(参考資料)
可燃ごみ・不燃ごみの組成分析から
それぞれに含まれる不純物の重量割合
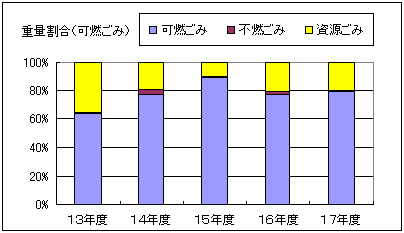
|
||||||||||||||||||||||||
|
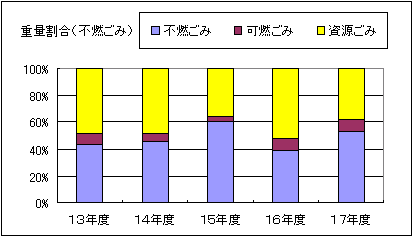
|
||||||||||||||||||||||||
|
可燃ごみ・不燃ごみの組成分析から
それぞれに含まれる不純物の容積割合
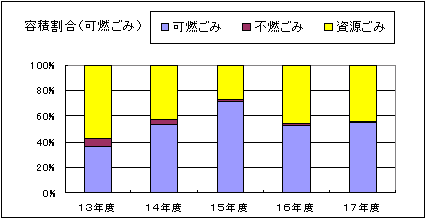
|
||||||||||||||||||||||||
|
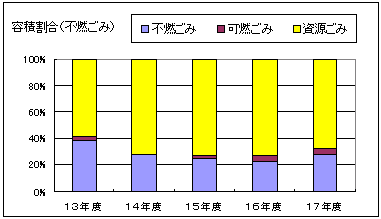
|
||||||||||||||||||||||||
|