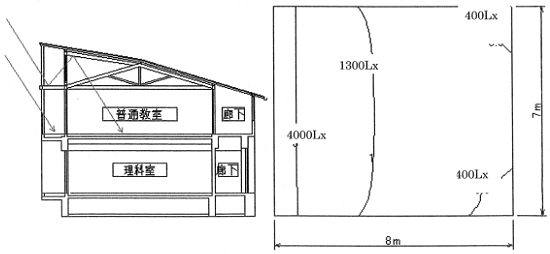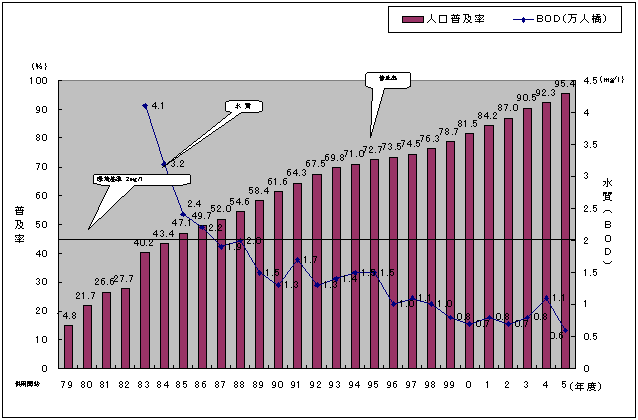【要請レポート】
|
高山市における公共事業と環境 岐阜県本部/高山市職員労働組合連合会・副執行委員長 小井戸真人 |
1. はじめに
岐阜県高山市は岐阜県北部に位置し、年間400万人を超える観光客が訪れる観光都市である。昨年2月、周辺9町村を編入し、新高山市が誕生した。人口は合併前の約6万7千人から約9万7千人、面積は合併前の139.57km2から東京都の面積に匹敵する2,177.67km2となり、日本一面積の広い市となった。その中でも森林面積は92.5%であり、国立公園は2ヵ所、県立自然公園は5ヵ所指定されている。山や川、渓谷、峠などで地理的に分断され標高差も2,000mを超える地形的な特色も多く、美しく豊かな自然は高山市民の誇りとなっており、自然環境の保全、環境にやさしいまちづくりは高山市にとって大きな課題となっている。高山市が取り組む施策の中、また、高山市で行われている公共事業における環境面への配慮について取り上げた。
2. 高山市環境基本計画とアジェンダ21たかやま
高山市では、1995年4月1日より「高山市環境基本条例」を施行している。環境基本条例は、市の環境保全施策に関する基本的事項を定めたものであり、日常生活及び事業活動において地球環境問題をも考慮し、市・市民及び事業者の責務などを明らかにするとともに、環境保全・創造に向け必要な措置などを定めている。
この環境基本条例第7条の規定に基づき、豊かで快適な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくために1998年3月に「高山市環境基本計画」を策定した。この計画の基本目標は「守りはぐくむ 豊かな自然とやさしい心 人がかがやく飛騨高山」とされている。また、環境基本計画における地球環境保全への具体的な行動計画として「高山市地球環境保全行動計画(アジェンダ21たかやま)」を策定した。1993年3月の国における「アジェンダ21行動計画」1996年3月には岐阜県において「ぎふアジェンダ21」が策定されている。
「アジェンダ21たかやま」の基本理念と基本的視点は、① 地球環境への負荷を抑制する社会の構築、② 豊かな自然環境と共生する都市づくり、③ 学習、参加、実践型の地域社会の実現、④地球環境保全に向けた国際協力、として地域に根ざした取り組みによって地球環境問題の解決に大きく寄与するものとして具体的な行動計画に基づき取り組みをすすめることとされている。
高山市環境基本計画の計画期間は2005年度までとされていたが、2005年2月1日に市町村合併したこともあり、新たな環境基本計画は合併後の市域における計画として2006年3月に策定された。また、アジェンダ21たかやまについても基本計画と同様に見直しがされた。計画期間は21世紀前半を視野に置き、2006年度から2014年度までとされている。基本的な考え方の中で、市は、事務事業や公共事業などにおいて率先して環境保全にむけた取り組みを推進していく必要があるとされている。
高山市合併まちづくり計画においても個性ある地域の連携と協調として市域全体の早期一体性の確保と均衡ある発展にむけて基盤整備を含めた新たなまちづくりをすすめることとしている。
3. ~事例1~ 道路整備における環境への配慮
(1) 中部縦貫自動車道 高山清見道路
高山市では、広大な市域となったことにより、各地域を連絡する道路や高速交通網など機能的な道路整備は新たなまちづくりの大きな課題となっている。
| |
 |
高山国道事務所では事業をすすめるにあたって「エコロード」として自然環境に調和した道づくりをめざし、1993年より「飛騨地域エコロード検討委員会」を設置し、飛騨地域内の野生動物の特性及び植物分布等を把握し、動植物にやさしい道づくりのあり方・共生について調査検討を行い、その整備方針・施行方法等の検討を行っている。
中部縦貫自動車道は松本市を起点とし、中部山岳地帯を経て福井市に至る延長約160kmの高規格幹線道路である。その一部の高山清見道路は高山国道事務所が事業を実施しているが、検討委員会の検討結果を活かし、道路整備による自然環境に与える影響を可能な限り回避、低減する取り組みがすすめられている。以下のような豊かな自然との共存をめざした取り組みが実施されている。
① 法面緑化の植生回復実験
法面緑化は、道路斜面を植物で覆うことによって雨等による斜面の崩壊を防ぐ目的で実施されるが、早期緑化や地域になじむ植生の回復等をめざして、11種類の植栽パターンによる植生回復実験が行われている。実験では、多様な種で構成されること、地域の在来種で緑化されること、早期に樹林化すること、少ない施行費用で緑化が行えること、法面が安定化することを目標に状況をモニタリングし、適した工法を現場で採用することとされている。
② 高山西IC調整地
道路により分断された里山環境の復元を基本コンセプトとし、「森の再生実験」として自然の回復力を利用した森づくりをすすめている。
整備内容として、樹木は全て現地のものを利用し、特に工事で発生した樹木の根株を移植する。造成地表面には、表土、チップ材、砂、小石等を用いて多様な植物の生育環境の創出を図り、池周辺の水辺環境を利用し、水生動植物の生育環境の創出を図る。工事で発生した表土を利用することによって、土の中に休眠している天然の種子や、近隣の植生から、風・野鳥等が運び込む種子の定着を促進し、多様な植物が生育できるようにする。工事で発生した大きな石をランダムに配置し、石の隙間に小動物や草などの植物が侵入・定着できるようにしている。
③ 周辺動物のための対策
生物の生息環境の分断、側溝への落下事故などを防ぐため、周辺の小動物などに配慮した施設となるよう工夫し、モニタリングをしている。植物や動物が棲みやすいようにブロックの間に空隙を護岸に設ける。大雨で流された小動物が側溝に落ちないように水たまりをつけた保護集水桝の設置、側溝に落ちた小動物がはいだせるように傾斜路をつけた保護側溝の設置がされている。
④ ゲンジボタル保全対策
工事によって消失されるホタルの生育区域の代償策として、ホタルの生育環境を創出する保全対策を実施することとしている。対策内容としては、新たに水路を整備し、現在ホタルの生息している沢の水を引く、水路には落差工を設け水路勾配を緩くする。石積や、砂利敷きにより流速を抑える。ホタルの生息空間として水路の脇に中低木を配置するなどの対策が施されている。
(2) 排水性舗装
県土木事務所における道路整備では排水性の舗装工事が取り入れられている。排水性舗装は、表層部の多孔質なアスファルト混合物による透水機能層と、その下の不透水層で構成されており、雨水は、透水機能層に浸透し、不透水層の上を流れて排水されるので、道路の表面には水が溜まらず、車両の走行安全性が向上することが期待できる。また、環境面として、透水機能層の中の空隙にエンジン音やタイヤのエアポンピング音が吸収されるので、交通騒音の低減が期待できる。さらに、沿道家屋住民および歩行者への水はねが大幅に改善されることや、ヒートアイランド現象の防止効果も期待することができる。排水性舗装は空隙が多いため、舗装の蓄熱容量が小さく放熱しやすいため周辺の温暖化防止への効果も期待される。
4. ~事例2~ 災害復旧事業における環境への配慮
(1) 災害復旧助成事業
2004年10月20日の台風23号は岐阜県下にも大きな被害をもたらした。高山測候所では20日20時に時間最大雨量56.5㎜、最大24時間雨量256.5㎜と観測史上最大値を記録、19日朝から21日未明までの総雨量は276㎜となった。宮川水系の各河川の沿岸では、破提・越水等により甚大な被害が発生し、浸水面積約377ha、住家の浸水531戸、このうち床上浸水は258戸、事業所等も含めた被害額は約147億円に達する大被害となった。また、河川堤防や護岸の崩壊、橋梁の流失、堰の損壊等の河川内施設の被害額も、約76億円に達した。
管理者である岐阜県高山土木事務所等によって災害復旧事業が実施されている。緊急水害対策懇話会の中で、住民からは、早期の復旧と河川環境、景観に配慮した河川整備を行って欲しいとの意見が出された。今回の復旧にあたっては再度の災害防止と安全度の向上を図るため、改良復旧を行い、台風23号により浸水被害が発生した能力不足区間を重点に河川の河積拡大及び法線是正等を自然環境に配慮して工事を行うこととしている。
護岸工事においては植物のための開口部を配し、自然な護岸を創造することとしている。
5. ~事例3~ 公共施設建設における環境への配慮
(1) 高山市立中山中学校建設事業
市町村合併により、支所地域における耐震力不足による改築及び耐震補強等が必要な校舎が多数あることをふまえ、計画的に整備するため小中学校建物等改造整備5ヵ年計画が策定された。
その中で、1961年度から1962年度に建設された旧高山地域の中山中学校校舎はバランスドラーメン構造であり、耐震補強工事が適さないことから、2006年度から2008年度にかけて校舎及び屋内運動場の改築工事を実施する計画で、今年度より工事が始まっている。
中山中学校の改築にあたっては、高度な設計能力、技術力と豊富な経験を生かして設計業務を行うことのできる設計業者を特定するため、プロポーザル方式にて設計者の特定を行うこととした。参加設計者は9社であったが、審査員による講評の中では各社とも高山市や建設地へのこだわりや気遣い、地球環境への貢献やライフサイクルコストへの提案など各社間の差は極めて小さいものであるとされた。その中で、十分な構想力、デザイン力、技術力が評価され、最優秀技術提案者は(株)日建設計となった。
設計業者からの技術提案の中で、環境配慮へのコンセプトとして、寒冷地の学校における快適な熱環境と光環境を実現させ、省エネルギーも両立させるエコスクールとして、以下のような具体的な設計がされている。
① ライトシェルフ(光の反射板)による光あふれる視環境の創出
南側が高い「高天井の教室」とし、ライトシェルフ(光の反射板)を設けることで、間接光を教室の北側に導き、明るい教室にする。