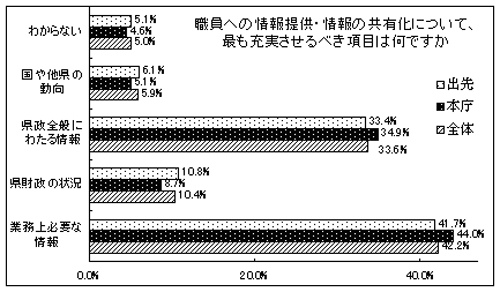【代表レポート】
福岡県本部/福岡県職員労働組合 |
はじめに
福岡県では、公金不適正支出問題(旅費問題)により情報公開下での組合運動のあり方について考えさせられました。また、地方財政危機により、単に勤務労働条件に関する活動だけでは限界があり、県の政策・施策の失敗により勤務労働条件に大きく影響することを痛感させられました。
そのため、財政状況を自分たちで分析することによって、財政危機に陥った原因と責任を明確にし、21世紀における福岡県政がどうあるべきか、県政のどこをどう変えていくかという議論を「県政への提言」という形で、県職労は踏み出しました。総論と各論、本音と建て前矛盾を抱えながらも第1次提言・第2次提言と進めてきました。
今回のレポートは、この提言を取り組むに至った経過と財政状況、及び提言で示している目指すべき県のあり方について、その概要を報告します。
1. 福岡県の現状と提言の必要性
(1) 福岡県の特徴
福岡県は、福岡市・北九州市の2つの政令指定都市を抱えています。全国的にも政令市を2市抱えているのは、神奈川県がありますが地域性や人口・財政規模が異なるため直接的な比較はできません。また、財政力指数から見た分類の同一グループ内では、政令市の設置状況が異なり参考としかなりません。
人口の分布を見ると、県人口約5,006千人のうち両政令市に46%を超える人が集中しています。また、福岡市を中心とした福岡都市圏(8市13町1村)に46%程が集中し、人口は増加傾向にあり大都市化しています。一方、福岡地域を除く地域では人口減少と高齢化が進み、日本全国の縮図のような状況にもなっています。
(2) 福岡県の歴史的背景
福岡県における知事公選制発足以来保守対革新の構図【1】の中で、県職労は、革新知事の実現を目指し、政治闘争を展開してきました。
亀井知事の出現以降、労使関係が歪になったことから、県職労は、県政の民主化の視点から自治体の在り方を議論することや、実現に向けた運動を本格的に展開するには至りませんでした。
その後、亀井県政16年間の弾圧の時代を経て誕生した奥田県政により革新知事は実現できたものの、野党が大多数を占める議会情勢の中、厳しい議会運営を強いられ革新県政としての施策展開は十分にできませんでした。また、県職労として、県政をどのように革新していくかの具体的な政策論議も不十分なものに終わっていました。
奥田知事の勇退により、誕生した麻生知事は、多党相乗り型の選挙により誕生し、議会情勢も奥田知事時代の少数与党と正反対の圧倒的な与党体制での県政運営となっています。しかし、福岡県行政と議会の関係は、奥田県政時代と同様に議会対策として「根回し」を行い、議会運営がスムーズにいくよう必要以上の調整を行っている状況が続いています。
(3) 公金不適正支出問題(旅費問題)
情報公開下での行政運営及び組合運動の在り方が問われたのが、1996年10月の新聞報道に端を発した「旅費問題」でした。
この問題で県職労は、「当局の権力的不正に対してはこれを告発し、民主的行政を進めるために奮闘してきた自負がある。しかし、『旅費問題』ではその不十分性を認めざるを得ないこととなった。具体的には、『①時間外勤務手当の完全支給を獲得できていなかったこと』『②旅費の実態を承知しつつも改善を看過してきたこと』『③県政の一方の担い手としての社会的な責任を負うことに対する自覚が不足していたこと』との総括に立った運動作りの創出をしなければならない」と総括しました。
県職労は当時、行財政システムについて36項目の要求書を作成し、改善を求めた結果、当面対応せざるを得ない旅費制度・時間外勤務手当等の改善が行われましたが、全てが改善されるに至らず、予算システム等構造的な改善は進んでいません。
(4) 県財政危機
1998年の夏から、大都市圏の都道府県を中心に財政状況の悪化が顕著になり、福岡県でも1999年3月2日に「緊急財政改革本部」を設置し、給与月額の3%カットを含む「人件費の総額抑制」を始めとし、「事務事業についての歳出削減」「各種の建設事業の規模の抑制」「財政収入の増加の確保」を柱とした緊急財政改革が進められました。給与の3%カット問題については、2002年3月で元に戻ったものの、2月に策定された「財政構造改革プラン(5ヵ年計画)」では、相変わらず財政の硬直化が強調されています。
(5) 行政改革
2001年5月に第3次行政改革審議会が設置され、「組織・システム改革小委員会」及び「県立病院改革小委員会」の2つの小委員会でそれぞれ議論が行われています。同年11月に「アウトソーシングの推進」や「外郭団体の統廃合」、「行政機関の再編」等多岐に渡る項目からなる、第1次答申が出されました。その視点は、地方分権時代の到来を標榜しながらも、従来の行政改革と同じく、財政効率化の視点から職員定数削減を中心としたものになっています。
内容的には、職員の勤務労働条件に関するものだけではなく、県民生活や市町村行政に大きく影響を与えるものも含まれていますが、住民・市町村・職員とも十分な協議が行わないまま、答申に基づき行政改革大綱が制定され、トップダウン型で個別に強行されようとしています。
また、行革審は今秋、「県立5病院の存廃・直営見直し」「人事評価制度」等を含む最終答申を行う予定になっています。県職労としては、提言等の運動を強化し組織内運動だけではなく、住民・市町村の仲間と共に県政のあり方を模索しながら自治確立を目指していかなければならないと考えています。
2. 福岡県の財政状況
(1) 財政分析の必要性
従来、県職労は、政策・施策に対するチェックや財政状況を積極的に分析することはなく、勤務労働条件に関する事項があれば協議するという程度でした。しかし、財政危機の原因が一部マスコミにより県職員の人件費にあるかのような報道が繰り返されたため、財政危機の原因と当局責任を明確にし、安易に人件費問題へのすり替えをさせないよう、財政分析を行いチェックをしてきました。また、「賃金カット」に象徴されるよう、財政面からも県の施策に関与しなければ、勤務労働条件さえも守れないという視点で、財政分析と併せ、財政課と節目において協議を行う取り組みを継続して行っています。
(2) 福岡県における財政状況の概要
福岡県に緊急財政改革本部が設置された時、経常収支比率の悪化が強調されていましたが、その推移は下図のようにB2グループ【2】平均に近づいています。福岡県がB2グループの平均を常に上回っているのは、2つの政令指定都市を抱え、教職員及び警察職員の人件費を県が負担しなければならないため、経常収支比率は高くなってしまうことが原因の1つにあります。
経常収支比率の推移は、H7~8年度にかけて、若干好転したのは税収と地方交付税の増加が、H11年度に急に好転したのは地方交付税の増によるものが、最も大きく影響しています。
これまで、地方財政危機に陥った原因について明確な説明は行われていませんが、国の景気対策に追随し公共投資を行ってきた結果、公債費が増加し県財政を圧迫してきているという全国的な流れの中に福岡県も当てはまると言えます。
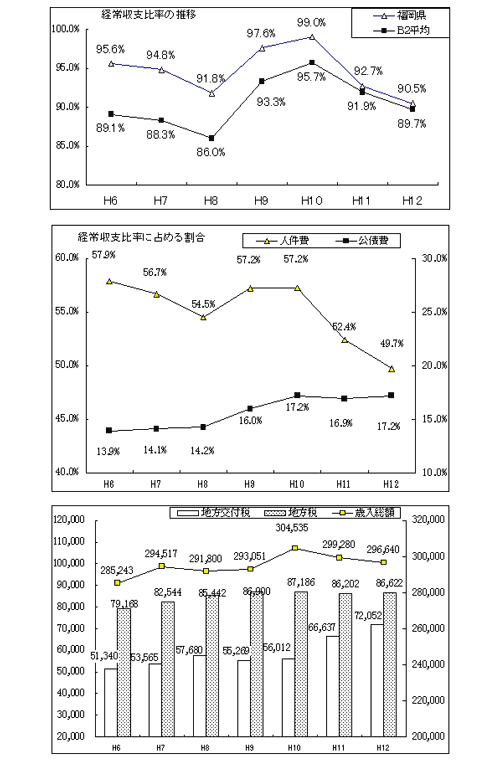
1999年3月2日に「緊急財政改革本部」が設置され、賃金カットを含む「人件費抑制」等の4本柱を中心に緊急財政改革が進められましたが、経済状況は回復せず、今年2月に「財政構造改革プラン(5ヵ年計画)」を策定し、「定数削減」「職員給与費の抑制」等を含む歳出抑制を図っています。
また、全国的に公共事業に対し様々批判されています。福岡県における大型公共事業として、現在のところ「流域下水道」「新北九州連絡橋」「ダム建設」等が進められていますが、特に議論は起こっていません。
一方、財政改革の柱の1つとして「建設事業費の抑制」が揚げられていますが、「新福岡空港」「関門海峡道路(第2関門橋)」について、懇話会等で議論が進められています。特に「新福岡空港」は、マスコミ・議会でも論戦が行われ、県職労としても動向をチェックし、議論しなければならない課題だと考えています。
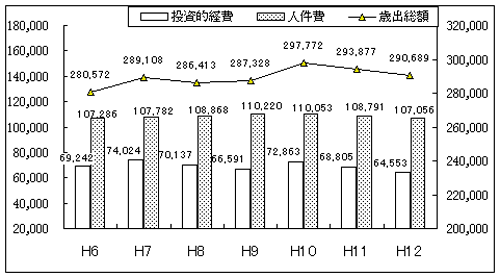
3. これからの県のあり方(地域密着型の県政への転換)=第2次提言より=
(1) 府県制の現在の立場
① 地方分権と「広域自治体」
地方分権一括法制定により、「新たな自治制度」が出発し、府県制度についても、機関委任事務の廃止、市町村との役割分担の見直し(統一事務の削除、補完事務の内容変更)等により、国の代行機関としての役割がなくなるとともに、市町村との指導・被指導関係の根拠もなくなり、府県は、明確に市町村と対等の広域自治体として位置づけられました。
しかし、広域自治体としての内容については、国民的な議論も自治体関係者の議論もほとんど行われていません。したがって、従来から中二階的「自治体」としてあいまいな存在であった府県制度は、理論的にも実態としても、あいまいなままであり、早急に自治体としての存在意義を示す必要に迫られています。
② 府県制のあり方
ア 全国的な状況
全国的には、知事のパフォーマンス、政治レベルでの府県の動きは活発になっています。高知・三重・宮城・岩手・栃木・東京・長野等において知事は、かつての革新自治体とは違った意味で、府県の存在意義を示そうとしています。
革新自治体の特徴が、国政のあり方を巡る政治対立・対抗を背景とした異議申し立て、国政批判型行政だったことと比べ、これらの府県の動向には次のような共通点が見られます。
a 国への対抗が主眼ではなく、府県という舞台での知事自らの理念や抱負の実現自体が目的である。従って、政策ケースにより国との協調・協力にも積極的である。
b 知事にとって、府県は、国を批判する道具ではなく、国から相対的に自立した組織である。
c 行政手法は、アカウンタビリティや住民参加等合意形成の仕組みを重視し、このことにより自らの正当性の根拠の拡大を図っている。
これらの府県では、先進的施策が多く見られ、「住民参加の拡大・定着」→「 行政の体質変化」→「 府県組織の真の自治体化」という過程に進む豊かな可能性をもっています。
イ 福岡県の実態
しかし、福岡県の実態としては、「県が変わらなければならない、変わることを求められている」という認識を持つ県職員は少なく、県行政の変化を期待する県民の声や市町村からの声も大きくないし、明瞭でもありません。
このことは、この間の地方分権論議の中心テーマが市町村の強化であり、論議を主導したのは国であったという事情も反映しています。しかし、基本的な背景としては、県民にとって市町村自治のイメージやそれへの期待感は存在するものの、府県自治のイメージ・期待感は薄弱であることを物語っているといえます。県は県民にとって役に立っているかどうかも不鮮明な遠い存在であるのかもしれません。
他方、ダムや干拓などの大型公共事業のあり方、3セク企業の経営破綻、旅費の不適正支出、談合問題、産業廃棄物処理問題など、府県にとって行政の透明性、公正・公平性等の姿勢を問われる事態が続出しています。福岡県も例外ではなく、スタンスを誤れば、県民の不信を買い「県無用論」が噴き出しかねません。
(2) 当面、求められる府県像
① 県民との関係
県民自らが自分たちの共通利益の実現のために、自己決定する仕組みを実質的に備えていること、知事公選制と議会制民主主義の保障に満足せず、直接民主主義の手法を政策過程に浸透させている組織であることが期待されています。
具体的には、
ア 県民利益=県民を顧客と見てその「顧客満足」を目的とする組織であること。
職員にとって、自分の行っている施策・事業が顧客に対するサービスになっているのか、目的の妥当性と効果が最優先の関心事になります。
イ 県民の自己決定権と政策参加を基礎とする組織であること。
政策・施策・事業の企画立案・執行実施・評価の各段階で、可能な限りの県民参加と協働が行われることになります。
この実現の前提として、県政の透明性とアカウンタビリティが求められます。
② 市町村との関係
地方分権が推進され、市町村合併などにより市町村の行政権限が拡大していくとき、県と市町村には新しい関係が必要となります。これまでのような指導=被指導の関係ではなく、府県は市町村支援に徹し、市町村と協働した地域密着型の行政を推進することが求められます。その支援内容は、「(ア)広域事務・補完事務における協力と支援」「(イ)市町村の県行政参加」「(ウ)権限の委譲=市町村の決定権の拡大」「(エ)国に対する市町村の立場の代弁」「(オ)市町村間問題の調整」があります。
また、地域密着型の行政実現のため、出先機関を地域の中核機関として位置づけ、市町村と協働できる体制が求められてくると考えられます。
③ 県の行政課題
県が重点的に取り組まなければならない行政課題は、次のような性格を持つ事項と考えられます。
ア 市町村を超える広域的な、住民の生活・生存条件にかかわる重要な社会問題(地域全体の生活条件を損ない、住民の安心・安全・快適な生活を保障できなくなるような社会的問題)。
イ 国際的な潮流や国全体にかかわる社会的な背景・要因としてあるもの。
ウ 個人や個別団体の力だけでは対処できず、また国や市町村の施策・事業だけでは解決できない問題。
④ 県民とのパートナーシップのありかた =行政主体と行政手法=
前記の問題群は、「行政=サービスの提供者」「住民=受益者」、又は、「行政=政策の立案者」「住民=事後承認」という、従来の図式では解決不能です。政策から個別事業まで、その立案・実施・評価の各段階での住民とのパートナーシップ、協働作業が必要となります。
NPOやボランティア団体との協働は勿論積極的に追及すべきですが、住民のすそ野にまで広がるパートナーシップのあり方、単に事業委託や実施段階だけでの協働ではなく、政策立案や事業計画も含めた参加・協働を考える必要があります。その実現のため、当面、政策・施策・事業での県行政の全体像を知ってもらうこと、それについて意見をもらうことから出発し、評価制度に則り、全事業の評価の公表と広聴の実施、基本計画策定時でのパブリックコメントの実施が求められます。
⑤ 総合出先機関設置への全国的な動き =地域事務所構想の具体化=
全国的にも総合出先機関設置の動きは、目立ってきています。昨年12月に調査した結果として、今年度の総合出先機関設置状況は、下図のようになっています。この調査後、群馬県が「2、3年以内を目処に実現可能なことから順次実行」と新たな動きも出てきています。
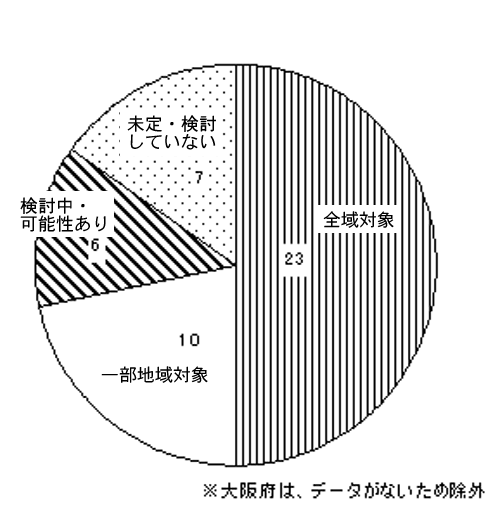
各県の総合出先機関は、名称・機能・対象地域も様々ですが、各県の共通認識として「より住民・市町村に近いところでニーズを的確に把握し、身近なレベルで総合的な県政を推進し、現地解決型行政の実現を展開することができる。」がメリットとしてあります。一方、デメリットとして「二重行政への懸念」「情報の共有化・意思伝達の欠如」「地域振興局内の縦割り」等が懸念されていますが、完全総合型の地域総合出先機関実現への過渡期的な課題ではないかと考えられます。
全国的な動向を見ると、総合出先機関の実現により、県民ニーズを把握し的確な事業展開を行うことが可能になっていることが実証されています。
(3) 福岡県モデルの実現を目指して
① 具体的課題、当面の方策
ア 情報の共有化
現在の福岡県の状況は、電子化が全国でも最も遅れているという事情もありますが、情報を職員にすら積極的に共有化していないことが次に示すアンケート結果から明らかになりました。職員間での情報の共有化を進めると同時に、県-市町村・住民、行政-議会で情報の共有化を進めなければ、職員・住民参加型の県政運営は望めません。
|
行政改革に関する組合員アンケート結果 行政改革審議会に関し組合員アンケートを実施した結果から見ると、行革審の答申を約5割の組合員が「見たこともない・見たが内容は知らない」としています。また、財政構造改革プランについても43%の組合員が「見たこともない・見たが内容は知らない」としている結果が出ています。一方、この答申やプランの内容を「十分に把握している・概略を知っている」とした組合員のうち上司から説明があったとする組合員は、僅か1~2割程度にすぎないという結果が出ています。
|
イ 職員の意識改革
先にも述べたように、現在の県職員は、「県の脱皮が求められている」そのことが時代の要請であるという知識、認識、意欲ともに希薄である様に見えます。個人の勉強不足の問題を解消しても解決できず、行政についての組織的・系統的な情報提供や啓発の仕組み、何より問題意識を持たせる場を数多く設定することが必要です。
また、これからの地方自治体の果たすべき役割に対応するために、管理職は従来の指示・命令に終始する管理職から、必要な情報や県政の課題等を正確且つタイムリーに職員に伝達し、大胆な職員への権限委譲と日常的なディスカッションによって職員に県政運営への参画意欲を引き出し、必要に応じ業務遂行上の支援や協力を的確に行う等、新しいコーディネーター型の管理職への変換が求められています。
ウ 出先機関の充実
県と市町村の関係が変化していくとき、本庁と出先機関の関係も変わっていかなければなりません。
地域密着型行政の実現のため、出先機関では直接接する地元のニーズに応えた政策立案を積極的に行うと同時に、縦割り行政の弊害を無くし地域内の出先機関同士の連携強化も必要となります。
そのために当面は、「(a)本庁から出先への権限委譲の推進」「(b)出先と市町村の協働関係の強化」「(c)県民・利用者に対するサービス提供の充実・強化」が必要です。
同時に、本庁と出先機関の人事交流を活発にすることによって、全員が本庁と出先機関双方の業務を理解し事業を推進する体制を作る必要があります。
全国的傾向として、山形県、新潟県等地域総合事務所の設置が続いています。将来の権限委譲をにらんだ市町村支援機能、住民参加の基礎となる総合的情報交流窓口の設置という地域総合事務所の主要な機能は、今日、府県の存在意義に係わる重要性をもっており、本県の単独出先体制との厳密な比較考量が必要になっています。
エ 意思決定部門の改革
知事、事業部局、人事、財政、企画という県の政策形成の意思決定に係わる部門が、整合性、統一がとれず、縦割り状態になっています。事業部門の立場から見ると、それぞれの側面からの評価査定が別々に長時間かけて行われるため、意思決定に時間がかかり、また県行政全体から見た当該施策の位置づけが見えません。このため、施策づくりのための施策、予算策定のための事業という倒錯した感覚に陥り、肝心の事業執行段階がなおざりになるという現象も起こっています。
改善策としては、意思決定の仕組みを2本立てとすることが考えられます。重要施策は、知事のもと一元的に査定することにします。そのために企画調整部門の充実・強化、それ以外の施策については、事業部局の権限を強化しある程度自己完結的に施策展開ができるようにします。こうすることによって、それぞれの立場で責任を持った施策展開ができると考えられます。
② 福岡県の目指す方向
県職労は、その基礎となる議論を「県民センター構想」【3】として1992年第67回県職労大会の中で、組織決定し、県でも1992年に検討され、県民情報コーナー設置等一部実現されましたが、「県民センター」そのものの実現には至っていません。
現在、福岡県では、行政改革大綱により生活出先機関のワンストップサービスという名目で保健所と福祉事務所の統合が2002年9月から実施されますが、他の出先機関については、具体的に明示されていません。
また、今回の機構改革に関し、保健所・福祉事務所を利用している住民や市町村に対する説明は、全く行われず、住民無視の組織機構改革と言わざるを得ません。福岡県におけるこれまでの組織・機構改革は、中・長期展望が示されず場当たり的な改革が行われ、「県民本位の県政運営」が行われているとは言い難いものがあります。
行政レベルで場当たり的な改革しか行われず、将来展望も示されない現状では、県で働く職員で構成した県職労から将来展望を見据えた県の機構のあり方を積極的に提言する必要がありますし、地域密着型の行政機構を実現させる必要があります。
4. 提言の具体化へ向けた課題
先に示したように、旅費問題による行財政システム改善要求に始まり、財政危機による財政分析から第1・第2次提言を県職労として取り組んできました。第1次・第2次提言については、議会やマスコミに公表したものの反応はほとんどありませんでした。また、自治労県本部を通じ市町村職労にも配布し意見をもらう取り組みも行いましたが、具体性に欠けるために議論を巻き起こすことはできませんでした。
しかし、提言に示している県のあり方や目指す方向性に基づき、「緊急財政改革・財政構造改革プラン」や「行政改革審議会の答申及び行政改革大綱」に対し、それぞれ提言に基づく県職労としての考え方を示してきました。
特に、行政改革審議会の答申時におけるパブリックコメントにおいては、「分権時代の県の役割」を補強させることができたこと。また、行政改革に関する県職労アンケートの結果により、幹部職員に対し「なぜ改革をしなければならないのか、どういう視点で改革しなければならないのか改めて考える」ための職員研修の実施が指示されるなど、徐々に変化が生まれてきています。職員研修の内容については不十分かもしれませんが、所属長等幹部職員がきちんと対応するように組織だって動き始め、徐々に変化がでてきたのではないかと考えます。
今後とも、県職労としてより具体的な県のあるべき姿を模索し、提言という形で発信し、実現に向け取り組みを進めていく必要があります。
【1】 保守対革新
1947年(S22)杉本勝次(社会)2期 1967年(S42) 亀井 光(保守)4期
1955年(S30)土屋香鹿(保守)1期 1983年(S58) 奥田 八二(革新)3期
1959年(S34)鵜崎多一(革新)2期 1995年(H7~)麻生 渡2期目
【2】 B2グループ
地方公共団体の財政力を示す指数である財政力指数により区分されたグループ
B2グループには、福岡県以外に、静岡・埼玉・千葉・兵庫・京都・茨城・群馬・栃木の各県が含まれる(H12)
なお、政令指定都市を2つ抱える神奈川県は、B1グループに含まれている。
【3】 県職労では、1992年に「県民や市町村の多様なニーズに総合的かつ迅速に応答するには、縦割り行政によって制度的疲労を来している行政組織の再編成、地域に密着した施策を展開するための分権的な行政機構の創設、職員の研修方法の改善やそれに基づく役割意識の高揚、県と市町村との新たな政府間関係の構築、そして、県行政への市町村や県民の参加が採り入れられる必要がある。」とし、広域レベルで県と市町村・住民を媒介し、総合調整を行えるような「県民センター」等の地域総合事務所の設置が必要として運動を進めてきました。