【自主レポート】
|
災害に強い街づくりをめざして 広島県本部/呉市職員労働組合 丸山 誠二 |
1. はじめに
わが呉市では南側に瀬戸内海が面し、呉の地名の由来ともなっている「九嶺」と言われているとおり三方を急峻な山に囲まれているという独特な地形となっており、急傾斜崩壊危険区域、砂防指定河川も全国的に突出しており規模の大小を問わず、災害に対して非常に危険性の高い地形を形成しています。
また、戦時中には軍港としてわずかの平野部において、海軍の施設などが存在することから軍事上の機密保持と言う観点から、多くの人々は生活上不便とされる、急峻な山地部分に雛壇上に仕方なく家屋を建築したり、灰が峰や休山などの山々の中腹まで生活の拠点を求めざるを得なかったのです。
以上のように地形状の特色や歴史上の事情などが重なり合い大規模自然災害が発生しやすく、被害も甚大となっている状況です。
そのような状況の中、呉市では1945年(枕崎台風)、1967年(梅雨前線)、それと、まだ記憶に新しい県内特に南西部を中心とした1999年の梅雨前線豪雨災害などの大雨洪水を中心とした自然災害が多く見受けられ、今までの防災対策も豪雨対策を中心として考えられてきている。
2. 1999年梅雨前線豪雨災害より
1999年6月29日の16時頃、朝から降り続いていた雨は一気に増し16時から18時までの2時間で136㎜を記録し市内各所で災害が発生した。
6月29日の降雨(時間降雨量)状況
|
時
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
降雨量
|
1
|
4
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
|
|
時
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
日降雨量
|
|
降雨量
|
3
|
9
|
6
|
70
|
66
|
19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
186
|
上表をご覧いただければおわかりのとおり、いかに短時間で集中した災害となったかがお解かりいただけると思います。この豪雨災害では短期集中であったため最初に述べたとおり呉市の地形的な特色も含め更なる被害の拡大が進んでいった。
また、呉市職労書記局のある福祉会館でも地下が冠水し停電の影響を受け書記局業務が完全にストップしてしまい多くの組合員にも影響を与えた。
その当時の模様を記した機関紙を掲載します。
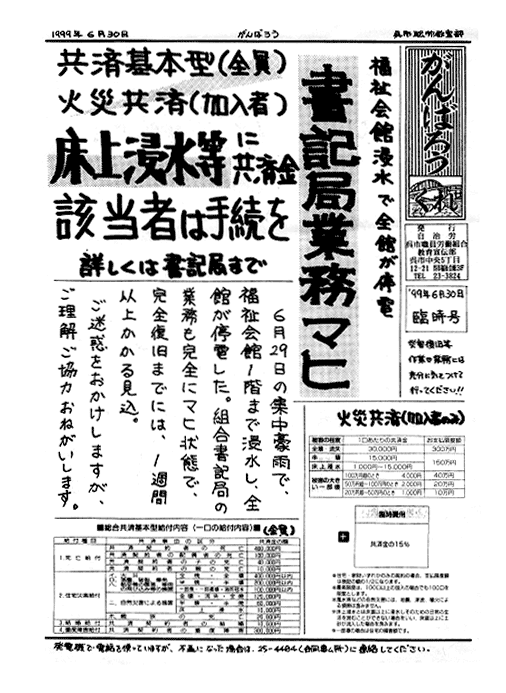
▲ 災害発生直後の機関紙
以上のように長雨である程度事態が予測される災害でなく、また災害の程度も呉市において過去に例を見ないような規模となり、全ての作業が事後整理になったことは最大の反省すべき点であったと思われる。
しかしながら、発生から約2週間後には人員不足に悩むボランティアセンターへの参加を組合員に呼びかけたり、執行部も休日返上で参加するなど呉市職労として呉市民の早急な生活の安定を目指し取り組みを行っていった。
3. 2001年の芸予地震災害を受けて
前述の災害で甚大なる被害を受けた呉市では、市内で被害を受けた施設の復旧作業(道路・橋りょう・農業関連など)や今後のための急傾斜崩壊地対策が急ピッチで完成し、ソフト面では呉市全域に対する防災マップの作成や警察・消防または地域と連携しながら防災体制と災害発生直後の対応できる体制作りに向けた動きが進む中で、ようやく災害で受けた傷が癒えてきた年度末の3月24日(土)15時30分頃に安芸灘を震源としてマグニチュード6.7(呉市発表)の地震が呉市民に襲い掛かって来た。当時呉市職労では書記の採用試験を行っており会場は一時騒然となった。災害発生時が土曜日と言うこともあり職員の大半が休日を過ごしていたにもかかわらず、初動の配置体制は何とか確保されたものの災害の種別が前年度とは異なったために被災状況にも違いが生じ、被災調査を進めて行くうちに災害対応の遅れが日に日に積み重ねって行き結果的にはかなり複雑なものとなって行った。
特にこのたびの地震災害では従来の水害とは異なり、下の状況写真のとおり民地に対して被害が大きく及んだ事が問題として浮かび上がってきた。

▲ 被災状況写真
しかしながら神戸、鳥取の大震災を参考に民地に対しても復興への支援事業が着々と進んでいる状況です。
呉市職労としては前回の水害時と同様にボランティアセンターへの呼びかけとボランティアセンターへ専従役員を派遣するなど執行部総力を挙げ呉市の復旧に努めていった。

▲ ボランティア参加写真
4. 大規模自然災害を受けて
呉市では、これまで述べてきたとおり2年連続で大規模な自然災害を受けた。さらにその内容がそれぞれ異なり不適切な表現であるが貴重な経験となった。
その中でいくつかの問題点が提起されその解決に向け呉市職労としても取り組んでいる。
はじめに、被災規模が大きくなり、復旧の目途が立たないとき最初に住民が生活を行う場として確保されるのが避難所である、その運営について以下のように考えます。
避難所へ派遣された職員(主に避難所付近に住居を構える職員)は避難住民の正確な把握や避難所の運営マニュアルなど無く目の前の処理を行うのが精一杯の状況であった。本来の生活している場を一時離れ、不安な心理状況の中で職員の場当たり的(職員としても仕方なく)な状況処理に対し住民も更なる不安を募らせるばかりであった。そのように職員、住民共に不安な状況で過ごさなければならない避難所の生活に対し災害の情報やこれからの見通しなど少しでも不安感を解消して行くことが、今後考えて行かなければならない問題のひとつと捉えています。
また現在の災害時の体制では各部署が独立しての事務処理を行っており様々な部署の職員(たとえば、建築関係職員、税務関係職員、土木関係職員、消防職員など)が別々の日時で被災地(者)を訪問し、各々の制度(調査)については説明するもののそれ以外のことについては最新の情報を有していない状況であるため、そのことが被災住民に対し混乱を招くこととなった。現実には他の部署での制度などについての認識が無いことは当然のことであり、日々細かな点で制度に関することなどが流動的な変化をもたらすことも当然である。ゆえにある一定の知識を有する一団で動く必要があると考えられる。
さらに、災害の事務処理を行う上で特定の部署(職員)に業務負担が偏るということも起きた。特定の職場(職員)に負担が集中し続けていくと必要以上のストレスなどから的確な状況判断も鈍り、そのことが1日も早い復旧に向けて取り組んでいるにも関わらず逆の作用を示して行く結果となっていった。
以上のことなどから、災害が起こったときに基本的に行政としていかに住民に対して正確な情報を伝えて行くことが出来るか。すなわち被災の規模、状況はもとより復旧に向けた適切な指導、適切な制度を常日頃から整理しておく必要があると思われる。住民が期待するのは早急な災害対策本部の設置ではなく不安な地元住民への素早い対応が求められていることを痛感した。
次に2点目として、行政として日頃の業務を生かしボランティアなどに積極的な参加をしていく必要がある。例えば、地震災害のとき災害ガレキの搬出に清掃業務で狭隘な市内の道路を運転している業務課の職員が奮闘している姿だった。呉市内は狭い道が多くまた、今回の最大の被害地区(両城・愛宕)に行くまでの道は非常に狭く大量なガレキの搬出には時間も無いことから大きな車が必然と求められ、その運転が出来るのはやはり常日頃の業務の特性を生かした業務課の運転手であった。それ以外にも今回は無かったものの炊き出しに対する給食員の参加など、その業務を生かせることの出来る職場は多岐に及ぶと考えられる。
以上のことから、われわれ行政職員が常に意識する必要があることは、いついかなる時であっても住民のために出来ることが何であるか、何を求められているかを適切に判断し、安心できる住民生活を作り上げることが大切だと感じました。
現在呉市職労では上述した内容を考慮しながら、昨年より独自要求書の中に政策制度要求として、「災害に強い街づくり」を目指した体制の確立を当局に求めています。最前線で寝食を忘れ、職場の床にダンボールを敷いて寝る状況を繰り返すことなく、呉市職労の「働きやすく、やりがいのある職場作り」を目指し、そして「住民が安心して暮らせる社会」を実現するための1日も早い防災・被災時における体制の確立を今後も粘り強く当局に求めて行きます。
最後にこの災害において亡くなられた方々に対しご冥福をお祈りいたします。