【自主レポート】
|
財政分析と進むまちづくり 宮崎県本部/五ヶ瀬町役場職員組合・自治研推進委員会 |
はじめに
今日、小規模自治体における一番の話題は市町村合併問題ではないだろうかと推察されるが、このことは、地方自治体が今までにない大きな転換期に立たされていることを指し示すものであり、また地方分権と共にこれからの自治体のありかたを論議する、避けて通れない問題であることを意味している。
さて、五ヶ瀬町は宮崎県の北西部(九州の中央)に位置し、総面積は171.77k㎡、全体的に急傾斜地が多く、総面積の88.0%を林野が占める町である。年間平均気温が12.7℃であり、宮城県の仙台市とほぼ同じという南国宮崎においては特異な気候を有する。基幹産業は農林業であり、特に釜炒茶は「五ヶ瀬みどり」というブランドを確立し、農林水産大臣賞を度々受賞している。また、日本最南端の天然スキー場を有する町でもあり、冷涼な気候を生かした夏秋野菜・花卉栽培や年間を通してのスポーツ合宿誘致などに力を入れている。五ヶ瀬町は昭和31年に合併して誕生した町であるが、その後、まちづくりにおいて「市町村合併」を前提とした施策をとってきたことはない。自治労五ヶ瀬では、合併はまちづくりの延長線上にあるもの、つまり合併する場合は目先の財源確保にとらわれない、「まちづくりの手段として必要であるから選択した」という町の将来像の論議を尽くした合併でなければならないと考えている。
自治労五ヶ瀬の自治研推進委員会では今回、この合併問題を研究課題として取り上げたが、国の財政問題を発端として始まった「平成の大合併」の問題は、国のアメとムチの政策により各自治体の財政事情を最優先課題にしてしまったことは否めない。そのことが、良し悪しは別として、少なくとも町の財政を正確に把握するきっかけとなり、この財政の分析からのアプローチがまちづくりにとっても重要であることを認識したところである。
ところで、五ヶ瀬町においても独自色を持ったまちづくりが進められてきているが、そのことによる影響として、町の予算規模をはるかに上回る地方債を抱えるに至った。今後も地方交付税の削減等、ますます財政状況が悪化していくと思われる。
そこで、当町の自治研推進委員は、過去の財政悪化を招いた要因と、今後進められる事業の展開について分析し、健全な財政運営を維持しつつ、これからの事業計画を計画的に実施していく方法を研究することとした。今回のレポートでは、まず、過去の財政状況を分析していくこととする。
1. 決算規模の推移(図-1)
1990年度からの決算規模を見てみると、1995年度が歳入で60億6千万円、歳出で60億3千万円となっており過去最高の規模となっている。その原因となったのが、この年度にスキー場設備増設、総合運動公園(Gパーク)造成、中学校校舎建設、公営住宅建設、文化財伝承施設(荒踊りの館)建設等のハード事業が重なった為である。また、1998年度にはスキー場の人工降雪機の増設を行っている。
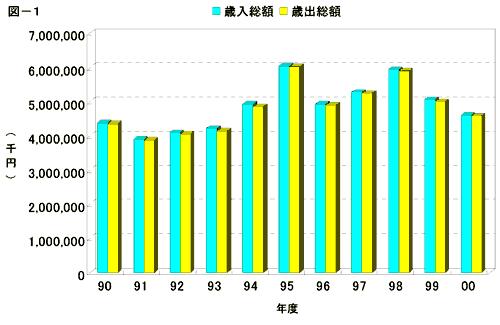
2. 決算収支の推移(図-2)
(1) 実質収支
歳入歳出差引額(形式収支)から翌年度へ繰り越すべき財源を引いた実質収支は過去10年間辛うじて黒字を維持してきている。
(2) 単年度収支
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差引いた単年度収支は1995年度で△5千万円、以降徐々に回復し1999年度では1千9百万円の黒字となったが、2000年度では再び△1千百万円の赤字となった。
(3) 実質単年度収支
単年度収支に財政調整基金積立額及び地方債繰上償還額をプラス要素として加え、財政調整基金の取崩し額をマイナス要素として引いた実質単年度収支は1998年度に突出した黒字を見せている。この原因は1997年度に4千9百万円、1998年度に1億円の繰上償還を行った結果である。
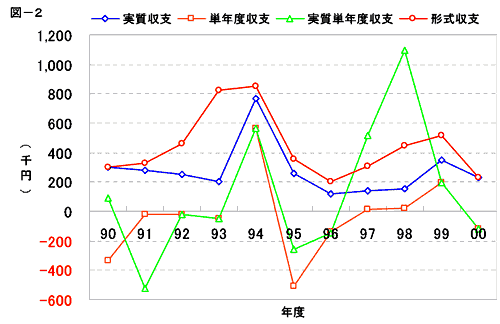
3. 歳入の推移(図-3)
自主財源である地方税の推移は、ほぼ横ばいであるが1996年度の3億円をピークに減少傾向にある。一方、依存財源である地方交付税、国庫・県支出金、地方債は例年歳入総額の80.0%以上を占めている。特に1995年の地方債発行額は15億を超え、地方債残高を一気に上昇させることとなった。このことは当町の財政基盤が不安定で、なおかつ今後の行政活動の自立性を確保し難いことを意味する。
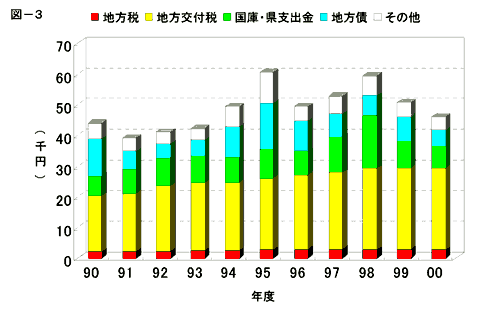
4. 歳出の推移(図-4)
義務的経費(人件費、扶助費、公債費)と投資的経費(普通建設事業費、災害復旧事業費等)との構成比を見てみると、1990年度と2000年度では義務的経費が26.5%から45.0%と18.4%もの増加となった。その原因は、従来から続いたハード事業がほぼ終了し、決算規模が縮小したことと、1995年度に発行した15億円もの地方債がその後の公債費の比率を上昇させる結果となったことによる。1990年度の公債費は4億5千4百万円、2000年度は10億5千万円となり、5億9千7百万円(131.7%)増加している。
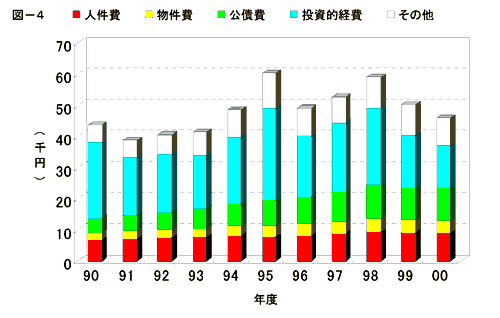
5. 地方債残高・基金残高(図-5)
1990年度の地方債残高は40億2千万円であったのが、1994年度から急激に増加し、1997年度で73億7千万円のピークに達した。その後は僅かずつではあるが減少してきているものの、依然として70億円もの地方債を抱え、町財政は硬直化している。一方、将来の財政運営を弾力的かつ計画的に行うための資金である積立基金は2000年度残高で11億7千4百万円となっている。今後の財政状況を改善する為には、一刻も早く地方債残高を減少させることが望ましいといえる。その為にも、基金を利用して繰上償還を行うことも必要であろう。
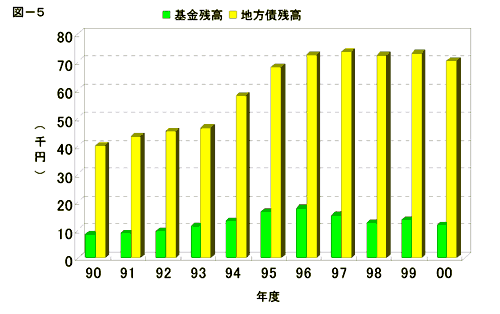
6. 財務指標の推移
(1) 経常収支比率(図-6-1)
経常的に収入される一般財源が経常的な人件費、公債費等にどの程度使用されたかを示す比率で、この数字が低いほど臨時的経費に充当できる一般財源が多く、財政構造が弾力的であるとされる。しかし、残念ながらグラフが示すとおり要注意ラインとされる80.0%前後を推移している。
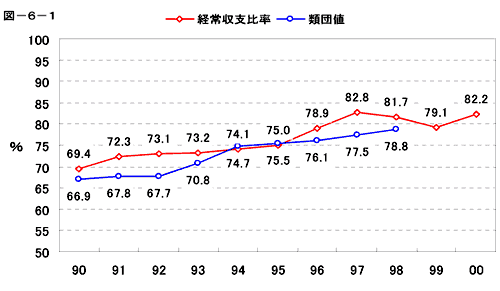
(2) 公債費負担比率(図-6-2)
一般財源総額のうち、公債費(借金返済)に充当された一般財源の割合を示す数値で、15.0%が警戒ライン、20.0%を超えると危険ラインとされる。驚くべきことに1990年度からすでに21.5%に達しており、その後も上昇をつづけ2000年度には34.4%もの数値となっている。財政チェックシートを使った見通しにおいても当面は30.0%を切ることはないと予想される。
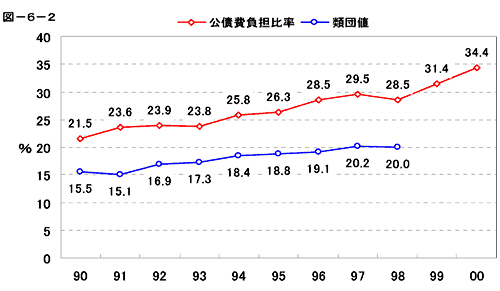
(3) 公債費比率(図-6-3)
地方債元利償還に充てられた一般財源の標準財政規模に対する比率を示す比率であり、10.0%を超えないことが望ましいとされる。この数値が高いと政策的経費に充てる一般財源が少ないことを意味する。1999年度の宮崎県の平均が14.8%、当町も14.9%であったが、2000年度では17.5%となり、県内でも上位グループに位置している。
(4) 起債制限比率(図-6-3)
起債制限比率も同様に厳しい推移を示している。1990年度の9.5%から、2000年度では8.2%に改善されつつあるものの、そのことを理由に今後も起債を借りつづけることへの大義名分にはなりえない。
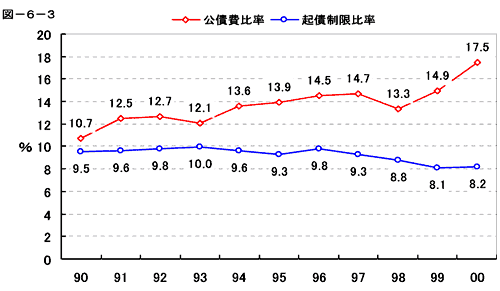
7. 今後の財政見通し
今回調査・分析を行った90年代は今までにないハード事業の集中した期間であった。その結果、町の財政規模をはるかに超える70億円もの膨大な地方債を抱え、後年度の大きな財政負担となっている。この額は、町民1人当たり130万円にもなるまぎれもない借金である。
当時国はバブル崩壊による景気対策として公共事業を増大させ、その財源としての地方債発行を認める、そしてその元利償還金は後年度に交付税算入措置を行って補うという手法を取ってきた。借金の返済分は交付税で面倒をみると国は言い、地方自治体はそれを頼りに借金を重ねてきた。このことが、五ヶ瀬町のみならず、全国の自治体で財政の危機的状況をまねいた大きな原因である。自主財源に乏しい自治体にとって、今後の財政見通しは大変厳しいものがある。まして約束されたはずの交付税が削減されてきた現状では、多大な公債費が財政をなお一層圧迫し始めてきた。
チェックシートを使ったシミュレーション(図-7)では、2004年度には赤字に転落してしまう可能性もあるのだが、国の制度改革や今後の本町の事業展開によっては、一層の暗転、または赤字年度の引き伸ばしが予想されるところである。
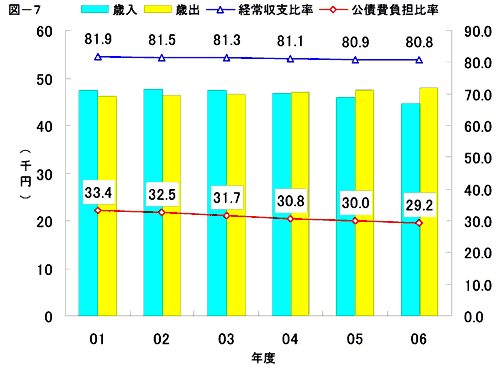
8. 今後の事業計画
これまで、多くの公共施設等の整備充実を図ってきたにもかかわらず、人口流出、高齢化により過疎が進行しており、現在もなお地域の経済は低迷している。
2000年度からの過疎計画によると、改めて農山村地域のあり方を問い、地域の風土・文化など多くの資源を生かしながら生活を高めていく必要不可欠な事業計画が展開されている。
その事業内容として、町の基幹産業である農林業への支援、情報・交通網・生活環境の整備、医療・保健・福祉の向上、教育文化の振興など住民生活の安定・向上を図りながら地域間の交流を促進するための地場産業の振興、観光及びレクリェーション施設等の整備を行い町づくりを進める計画となっている。具体的には、住民直結型プロジェクトとして、介護保険制度の施行に伴う全般的な高齢者福祉施設の整備、地域文化の振興を支援する社会教育総合施設などの計画がある。
また、地域間交流の促進のプロジェクトとして、スキー場など観光レジャー施設の整備拡充、Gパーク内への温泉施設の建設、グリーンツーリズム事業に伴う夕日の里づくり拠点施設整備の計画がある。この夕日の里づくり拠点施設はワイナリーを中心とした交流施設などが建設される予定であり、ワイン用のぶどうの作付けも町内の農家において急ピッチで進められている。
9. まとめ
(1) 市町村合併はまちづくりの延長線上に
1997年7月の市町村合併特例法の改正、同8月の「市町村の合併の推進についての指針」の自治省通知を契機に、2001年3月及び2002年3月に総務省から新たな指針が出され、自治体、地域における市町村合併推進にむけた検討、取り組みが強められつつある。市町村合併特例法は2005年3月までの期限となっており、市町村合併の手続き期間から逆算すれば、2002年度が法定協議会設置の最大の山場になることが予想される。
自治労五ヶ瀬では、冒頭に申し述べたとおり、市町村合併はまちづくりの延長線上にあり、まちづくりの一手段として必要な場合に限り推進されるものであると考えている。単に合併による期限付き特例財源の確保と歳出削減では町は失われるだけで将来への希望は見出せない。目先の財源に手を伸ばしたばかりに、住民のための行政ができにくくなるという、自治体のもっとも大切な根幹が本末転倒となることが危惧されるのである。
では、今何が必要なのか。それは、五ヶ瀬町の長期的展望を明確に示すことである。
(2) 計画性
五ヶ瀬町において今後計画されている事業はどれをとっても重要な施策である。しかしながら、現在の財政状況と今後の見通しは依然厳しいものがある。そんな中で本当に計画どおりの実施ができるのだろうか。「住民生活にとって本当に必要なものはなにか?」という検討を充分に重ね、その優先順位決定の判断を誤ってはならない。これからは自己責任をもった行政運営を求められる時代であり、また事業効果を評価するシステムが必要である。90年代に行ってきたようなハード面への集中投資を今後も続けるならば、取り返しのつかない結果をもたらすのは日の目を見るより明らかである。
この状況を打開し、健全な財政運営を実現させる効果的な手段はありえるのだろうか、答えは簡単である。安定的な歳入を確保し、歳出を削減すればよいのである。
しかし、自主財源の乏しい財政力の低い自治体では安定した歳入の確保が困難であり、自治体の内部努力には限界がある。本当に必要とされる事業であっても外的な財源に頼らざるを得ない。ただ1つの選択ミスも許されない財政状況だからこそ計画に乗っ取った行政をすすめなければならない。
(3) しようがあった
どこの自治体でも聞かれる、当局の「財源がないからしようがない」という発言。正確な財政分析のもと、事業の取捨選択がなされていれば避けられた言葉である。責任の転嫁は結局住民サービスに跳ねかえるものであり、五ヶ瀬町にとって何一つ得るものはない。今の財政状況を職員全体でとらえ、町民全体と情報を共有する必要がある。
意識改革がなされていれば、少なくとも「しようがあった」に違いない。
(4) 立案と実践
五ヶ瀬町では、2001年度を初年度とした10年間の「第四次長期総合計画」を策定し実施している。この計画は今までの行政単独での計画策定をやめ、数々の座談会等を通して町民の意見を反映させたものである。計画推進にあたっては14の行政区ごとに町民選出の「まちづくり地区推進委員」2名に役場職員2名の合計4名が地区の意見をとりまとめ、企画・立案から実施までを担当し、役場はそれをサポートする体制をとっている。私たち組合員も推進委員としてまちづくりに参加しているが、これまでの、将来への展望を持たずに行政運営を行ってきた当局を思うとき、組合からの働きかけによる情報の分析、そして立案が重要な鍵を握っているように思われてならない。
ところで、自治研では先だって、町立病院に勤務する組合員出席のもと病院の財政と今後のあり方に対する連絡会議を持つことができた。1998年の病院改築がもたらした累積欠損金の大きさに気付いた自治研からの申し入れで開いたものであるが、連絡会議では今後一般会計からの繰出金として町財政に与える影響は避けることができないことを確認し、また、「一般病床」と「療養病床」の選択等の改正医療法の実施による新たな財源不足の可能性の状況を共通の認識とした。今回の財政分析を活用し、今後の方向として病院会計との連結分析を模索している時であったのだが、逼迫した危機的状況であることがなお明確になったことで対策を急がなければならない。
今回、市町村合併の議論の前段である財政分析に時間を割き、また、町長の「現段階で合併は必要ない」との意思表示を受け、本町における市町村合併問題を深く議論するまでには至らなかったが、これまでの結論として、当局に対しては中長期的な財政計画を明確にした上での事業実施を要求していくことを実践したい。組合からの「提案」としてまとめるまでには職場・職員の相互理解の時間も必要であろうが、今こそ問題解決の糸口を見いだす行動をおこさなければならないと考えるものである。