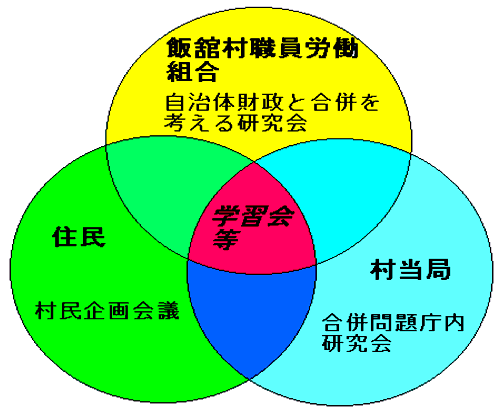【自治研究レポート(個人)】
|
合併問題は住民と協働の視点 福島県本部/飯舘村職員労働組合・執行委員長 佐藤 周一 |
1. はじめに
(1) 飯舘村の概要
飯舘村は、福島県の「浜通り」に属し、県の北東部、阿武隈山系北部の丘陵地帯に広がる標高200~600mに生活基盤をもつ農山村である。気候は比較的夏涼しく、冬は降雪が少ないものの寒さが厳しい地域である。人口推移は、昭和60年に8,206人1,728戸で、平成14年4月現在は6,963人1,760戸と、第4次総合振興計画で予測した平成16年度の人口7,000人をすでに割り込んでおり、過疎化が進行している。
(2) 飯舘村職労の現状
条例の職員定数は110人。現在特別職を除き97人の職員で、組合員数は87人である。このうち5級と6級の組合員は48人と、55%が5級・6級に溜まっている状況にある。財政状況類似団体比較カードを見ると、人口千人当たりの類似団体の職員数は14.11人に対し11.02人と、類似団体と比較しても20人少ない職員で仕事をしていることがわかる。
組合の昨年1年間の行動経過を見ると、団体交渉は4回、職場委員会16回、闘争委員会、執行委員会も相当数に及んでいる。主な交渉経過は、当局からは管理職の人事評価や、国・県への人事交流が提案されたが保留。また、懸案だった超勤と代休の取り扱いも、イベント業務について「1人年1回は代休」を受け入れ、今後「ボランティア」という曖昧な名目での勤務命令は受け入れないことを確認している。
2. きっかけは団体交渉
(1) 背景と問題意識
組合が財政状況の分析を始めるきっかけは、団体交渉時に「財政が厳しい」との防戦で交渉が進まなかった背景がある。財政が厳しいといわれても、果たしてどのくらい厳しいのか分らない状態でもあった。現在の村の財政が健全なのか、悪いのか、瀕死の状態なのか、それとも改善の方向に向かっているのか、悪化しているのかを知るきっかけとなった。
2つ目は行政改革案として人員削減が進められているが、すでに類似団体より20人も少ない職員で仕事をしており、人件費攻撃が着実に進められていることが分る。しかしながら、単純に人員を削減するだけでは、現行のサービスのレベルを少ない職員でどうやって維持していくのか、新しいサービスの提供を担う人材をどうやって育成するのか、という肝心な問題がないがしろになっている状況がある。
3つ目は高齢化社会への対応である。本村の高齢化比率は26.6%と高い状況である。後で、市町村合併問題の議論の経過報告でふれているが、合併ありきの議論ではなく、地域社会の最小の地域単位である「集落」、つまり「行政区」の集落機能がどのように変化していくのか、集落ごとの人口推移と高齢化比率の推移が、今後の村づくりに大きく影響するものと考えられる。
4つ目は地方分権の推進である。平成12年4月に地方分権一括法がスタートして、各自治体とも自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することが求められている。既に、本村においては平成7年度から飯舘村第4次総合振興計画で地区別計画を実践し、平成17年度からの第5次総への移行が課題となっている。
5つ目は住民協働の視点づくりである。後の経過報告でふれるが、平成12年8月の自治労中央本部自治体財政講座に参加。講師の鳥取県本部副委員長川下豊洋氏から「当局だ組合だと言っている時代ではない。現状を把握して将来の見通しを早期に認識する必要がある」との講演のとおり、いま私たちが置かれている状況を把握して、住民と組合と村当局が情報を共有することが課題となっている。
(2) 取り組み経過
このような背景なり問題意識を持ちながら、学習する組合活動を実践した。
昨年1年間の主な取り組み経過は次の通りである。
① 平成12年8月1日 自治労中央本部自治体財政講座に参加。
本講座で財政分析シートを入手。その後、人件費攻撃への対抗手段として、さらには現状を認識して将来の見通しを認識するために、財政状況検討提言書を作成。
② 平成12年11月29日 第49回村職労定期大会の決議を受けて「自治体財政と合併を考える研究会」を発足。
「全組合員の参加による目に見える運動」を目指し、地方自治を守るたたかいとして、市町村合併に関する研究会を立ち上げ3回の学習会を実施。財政状況を考えていく中で、市町村合併問題は今後の労働環境に大きく影響を及ぼすことからも財政分析と合わせて取り組んだ。
③ 平成13年2月6日 第1回学習会。テーマ「なぜ財政分析なのか」、講師は鳥取県本部副委員長 川下豊洋氏。
福島県本部の支援のもと、自治労中央本部自治体財政講座と同じ講師、川下氏を招いて2部構成で勉強会を開催した。1部はパソコンで分析。2部は本村の財政分析の解説を加え「なぜ財政分析なのか」を勉強した。
④ 平成13年2月13日 第2回学習会。テーマ「市町村合併と自治体職員」、講師は(財)地方自治総合研究所 島田恵司氏。
福島県本部浜総支部の支援により、市町村合併問題の国の流れ、全国的な状況についてと、組合と地域住民との係わりが大切であることを認識。
⑤ 平成13年3月16日 第3回学習会。テーマ「分権で問われる問題解決能力と自己評価」、講師は山形県遊佐町長 小野寺喜一郎氏。
村職労単独の開催。遊佐町の例を聞き、自主自立・自己責任の時代を迎え自分たちの町づくりを考えるとき、地域に合った自治のあり方を住民とともに考える勉強会であった。
(3) 財政状況検討提言書を作成
財政状況の検討は、開かれた財政運営をめざすことが地方分権の理念と共通するものであるので、開かれた組合活動の理念のもと、県内初の試みとして財政分析を行い提言書にまとめたものである。
この中では財政状況を見る指標を3点に簡略化し、まず1点目は「お金があるのか」、累積赤字は大丈夫なのか。2点目は「自由に使える財源はどの程度あるのか」。3点目は「借金のできない多重債務になっていないか」にポイントを絞り財政チェックとシュミレーションをしたものである。
その結果、分析作業を通じて見えてきたものは、財政危機の原因が人件費にあるのではなく公債費にあり、今後、財政運営に当たっては建設事業の選択抑制が必要であることが分った。さらには、財政状況分析をレポート化したことにより、団体交渉の時に「人件費が財政を圧迫している」と言われなくなった。
また、地方財政危機の特徴としては、景気の低迷が続き税収が落ち込んだ中で、経済対策の支出を増やし、不足財源を借金に依存してきたため、当然のことながら借入金返済の公債費が増加して、財政悪化の最大の共通要因であることが、学習会を通して分った。
3. 組合と当局がデータを共有化
(1) 村の基本方針と取り組み
市町村合併問題に対する村の基本方針と取り組み内容は、合併問題は歴史的な重大案件であり「住民の意思を尊重する」ことを基本方針としている。村は、地方分権を進めるうえで欠かせない視点は住民へのアカウンタビリティが重要と考え、財政が厳しいから市町村合併が得か損かの合併ありきの議論でなく、将来の地域住民が豊かな暮らしができるかを、住民が主役になって住民自らの議論になるようにしたいとしている。
市町村合併問題を考えるきっかけは、前記したように団体交渉が始まりであり、その後組合がまとめた財政状況検討提言書のデータを共有し、さらに村が職員や住民とともにまとめた「市町村合併問題庁内研究会報告書」「飯舘村村民企画会議報告書」の内容を組合とも共有している。
基本認識としても市町村合併は目的でなく手段のひとつであり、時代が変動するなかで、「将来とも地域住民が豊かな暮らしが営まれる地域社会の建設」が目的であり、市町村合併はこれを実現する手段(選択肢)のひとつとしている。
具体的な取り組み内容は、1つに情報周知活動として、住民に等しく情報を提供し、住民の共通認識に努めていることを目的に勉強会を実施。2つには意見交換活動として、多くの住民が意見交換できる場として、ディベート方式による賛成・反対討論会を開催している。3つ目には意見集約活動として、各地区懇談会と村議会等との協議を実施し、一定の方向性を出す計画である。
(2) 2001年村の取り組み経過
村は、「市町村合併問題に対する村の基本方針と取り組み」内容に従い、多くの情報を住民に分りやすく提供し、住民と情報を共有する取り組みを実施した。昨年1年間の主な取り組み経過は次の通りである。
① 平成13年6月20日 第1回市町村合併と地方自治を考える勉強会。テーマ「市町村合併と地域自立」、講師は(財)地方自治総合研究所 島田恵司氏。
講師の島田さんには、先の組合開催の学習会にきていただいているが、多くの住民に市町村合併の現状を理解していただくために勉強会を開催した。参加者204人。
② 平成13年6月27日 第2回市町村合併と地方自治を考える勉強会。テーマ「市町村合併を考える」、講師は総務省自治行政局行政体制整備室総務事務官 玉井健二郎氏。
国の合併担当者を呼んでの勉強会。すでに出されている資料のとおり合併ありきの話しが主で、住民にとって有効な勉強会になったかは疑問。参加者157人。
③ 平成13年7月10日 第3回市町村合併と地方自治を考える勉強会。テーマ「福島県広域行政推進指針について」、講師は福島県総務部市町村課長 鈴木康雄氏。
第1回勉強会で、全国的に見ても福島県の取り組みが遅れていることは分っていたものの県の一歩引いたスタンスを確認することができた。参加者106人。
④ 平成13年12月2日 市町村合併を考える村民集会。テーマ「飯舘村の現状と将来を見すえて」、講師は福島大学行政社会学部長 松野光伸氏。さらに、「財政状況を分析」「集落機能を考える」を報告。
住民への情報周知活動の一環として、前段に福島大の松野教授の基調講演と、職員からなる市町村合併問題庁内研究会から「財政状況を分析」を、住民からなる村民企画会議からは「集落機能を考える」と題して1年間の研究の集大成が報告された。
(3) 市町村合併問題庁内研究会報告の概要
国は、過疎に悩む自治体は市町村合併や広域行政を進める必要があるとしているが、市町村合併の必要性については財政効率だけに偏った合併ありきの議論が一人歩きしている。このような中、庁内研究会では、単なる行政コスト論だけでなく行政サービスとのかかわりを見ることも重要な視点であり、各分野の洗い出しと財政状況についても検証している。
洗い出しは、分野ごとに「主要課題」と「すぐやるべき課題」と「将来的な課題」を整理している。財政状況の主なものとして、人口減少と高齢化の観点から地方税と地方交付税が減少することが分った。
(4) 村民企画会議報告の概要
村民企画会議は住民の生活視点を第一義として検討をしてきた。合併ありきの議論でなく、今後、地域社会の最小の地域単位である集落機能が維持できるのか、集落ごとの人口推移と高齢化比率の推移をもとに、集落機能を分析している。
その結果、コミュニティの基礎単位である「集落」、つまり「行政区」は少子高齢化が進み行政区の活力が低下していくことが分った。また、高齢化の急激な進行によって、農林業の担い手不足、集落への愛着の減退、伝統芸能の衰退、農村景観である農地や道路の草刈等個人負担の増加や、冠婚葬祭の経済的な負担増大など必然的に集落機能の低下を招いていることが分った。
さらに、主要課題の整理から、村内の3小学校合わせた平成14年度の入学予定者は66人。平成19年度は53人に減少する傾向にあることが分かり、今後は行政区単位の祭りごとの見直しや、小学校区単位の集落機能の再構築など、行政区内最小のコミュニティとなる「組」の再編成を含めた検討が必要であることが分った。
4. ディベートによる討論会を実施
(1) 2002年村の取り組み経過
市町村合併問題を村民向けに分かりやすい討論する場をつくろうということで、「ディベート」の手法を導入することになった。
ここまでそれぞれの立場で学習を深めてきた村民企画会議と市町村合併問題庁内研究会の委員が一緒になり、ディベートとはどんな討論形式なのかを数回学習した。さらに、市町村合併問題の勉強会を住民に呼びかけ、反対・賛成それぞれの論拠による講師を迎えて、2回開催した。1回目は財団法人地方自治総合研究所の高木健二氏による「市町村合併と住民自治」をテーマに開催したが、会場の参加者からも自治体財政に対する質問があり関心の高さを感じた。続く2回目では岩手県立大学総合政策学部の田島平伸助教授による「市町村合併とまちづくり」をテーマに、それぞれ100名の村民が聴講した。
(2) ディベートによる賛成・反対討論会
そして、いよいよディベートによる討論、「市町村合併を考える村民集会」では、賛成立論・合併するメリットと反対立論・合併しないメリットをそれぞれ主張するという手法で、市町村合併の具体的な課題と自治体としての将来像を模索した。150人もの住民を釘付けにした「市町村合併を考える村民集会」におけるディベートの立論は表のとおりである。
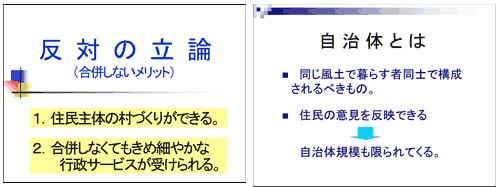
図らずも村民企画会議が独自に調査してまとめていた集落機能の将来像と、合併後の周辺地域のグラフが重なり、合併してもしなくても人口の流出や少子高齢化は避けられないことが明らかになる中で、その速さは合併しない方が緩やかであり自主自立の地域づくりに必要な人的資源を確保できることが裏付けられた。
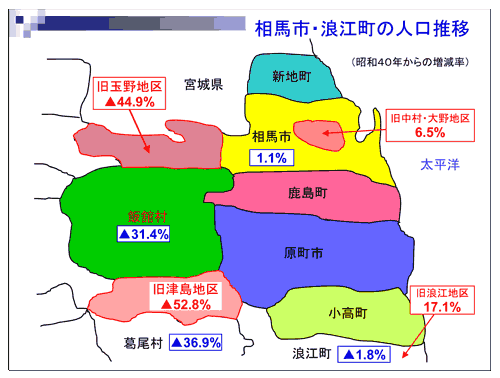
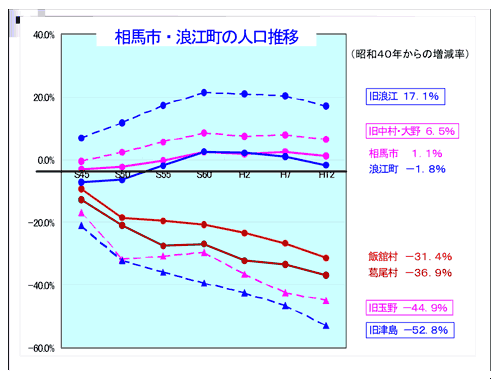
このディベートを通して、組合員(職員)も住民も、これまで断片的であった市町村合併に関する情報や様々な疑問を体系的にそして深く知る機会となり、行政側も持ちうる情報を住民に伝えることができた訳で、結果として市町村合併に関する説明責任を全うしたことになった。
村民集会で情報を得た住民は、10月15日から3回開催予定の地区懇談会の中で自主自立の地域づくりについて活発な意見を交換されるものと期待している。
(3) 合併が市町村を救う?
ディベートの立論に取り上げたのは、合併特例債という地方債の性質である。その分析から分かったことは、合併特例債はやはり借金であり、新たな自治体建設に名を借りたゼネコン型の旧態依然とした自治体再整備の体質から一歩も抜け出していないということである。これでは地方分権の推進どころか、地方財政危機を先送りする手法で、地域の自主自立の土壌や環境を整えることに通じない。合併特例債が地方財政の課題を解決するにほど遠く、ましてや住民自治を自ら確立したいとする地方分権の意思決定はままならないと言える。
5. 地方分権の実践は10年前から
(1) 住民参加型の地区別計画を実践
飯舘村第4次総合振興計画の地区別計画は、10年前から「自分たちの住んでいる地域は自分たちの手で!」を合言葉に、住民主体の地域づくりを推進している。この事業は、ふるさと創生事業費と昨年度まで地方交付税に含まれた国の地域おこし補助金の計2億円を村基金として積み立て、20行政区に各1千万円を助成、一割を地域負担としている。各行政区では地域づくりプランを作成して、地区代表20人で構成する地区計画協議会の審査をパスすると、初めて村に事業申請できるシステムとなっている。
これまでに、村民主体の事業で「農産物直売所」や「創作太鼓」、50年ぶりの「田植え踊り」が復活、ごみ分別の「リサイクルセンター」など、村の助成総額は1億6百万円と約50%の実績。平成14年度実績見込みは約70%で、今後、創意と工夫による地域づくりが16年度の最終年まで続くものである。
6. 今後の取り組み
(1) 地区懇談会を計画
市町村合併問題に対する村の基本方針と取り組みの通り、今年度は合併問題の勉強会とディベート方式による賛成・反対討論会を踏まえて、10月から地区懇談会を開催して住民の意見集約活動を行う。12月議会には、村(自治体)として市町村合併問題の一定の方向性を示すことになっている。
7. まとめ
(1) 学習する組合
地方分権など行政の現場が大きく変わろうとしている今日、わたしたち労組もこれまでと同じ感性でいては時代に流されてしまうという危機意識を持っていたので、2000年11月委員長就任を機に組合運動のあり方について提起した。
それは新しい課題に対応できる柔軟な思考力と難題に挑戦する創造力であり、学習する組合としての組合自らの方向性であった。
こうした動きに村当局が関心を寄せた。それは、合併特例法には期限があるためいかにして住民に情報を提供し、住民の選択に委ねるかという課題を抱えていたからであったと推察している。
(2) 行政の説明責任
行政施策の住民に対するアカンタビリティが求められる時代に、合併問題という課題が迫ったことで当局も一気に住民説明を進めることになった。
この背景には、これまでも組合として団体交渉の場で行政の説明責任のあり方を追求し続けてきたこともあげられるが、もっとも大きな要因として、組合の財政分析や合併問題への取り組みに村当局が理解を示し、共に意見を交感(感じて交わる)して住民に情報を伝えようとしてきたと言える。
(3) 情報の共有化
そうした過程の中で、本組合の学習活動は、財政状況分析をはじめ組合内部に合併問題検討委員会を設置し、職場集会や機関誌で情報の共有化を図り、組合主催の市町村合併に関する学習会も開催してきた。忙しい通常業務を抱える職員にとっても、村の将来を考える合併問題を自分のこととして捉える絶好の機会になった。組合主催の学習会に多くの管理職も参加してくれたことは特筆できる。そのことがやがて住民を巻き込んで、行政主催というかたちの村民集会に発展したことはいうまでもない。
(4) 意思決定する機関を身近に
市町村合併の問題に取り組み、学習会や村民集会を重ねてきたわたしたちはついに真実を見つけた。ディベート2回目の会場で「むらづくりは村民が主体であり、村民は意思決定する機関を身近に置きたいと願っている」と、参加者が発言した言葉に、本来の地方自治のあり様が見えてきた。
8. そして、ここから
(1) 地域とともに
飯舘村第5次総合振興計画(2005-14)の、住民が創る村の将来計画はいよいよ正念場となる。組合も自信をもって住民と一緒に汗することで、住んで良かったといえる魅力ある自治体に近づくことができる。わたしたちは常に、誰のための自治かを問い続けながら、地域とともに、住民とともに歩んできたい。
http://www.vill.iitate.fukushima.jp
住民協働の視点