【代表レポート】
|
「出石町人権尊重のまちづくり条例」について 兵庫県本部/出石町職員労働組合 |
1. はじめに
兵庫県出石町では2002年(平成14年)3月7日、出石町議会において「出石町人権尊重のまちづくり条例」制定の採決が行われた。本会議では、教育福祉常任委員会の「原案のとおり可決すべきものと決定」との審査報告を受け、議長を除く15人の町議会議員のうち5人が賛成(3人)・反対(2人)それぞれの立場で討論。採決の結果、同条例案は賛成多数により可決され、翌3月8日付をもって兵庫県下で4例目となる人権条例を公布・制定するところとなった。
条例案は、2001年(平成13年)12月10日付で議会に提案、閉会中の審査として教育福祉常任委員会に付託されていたもの。委員会では、県下における条例制定の先進地でもある香住町、三木市への行政視察を含む延べ6日間の審議の結果、上記のとおりの審査報告となったものである。
条例制定のきっかけとなったのは、部落解放同盟出石支部をはじめとする障害者・女性・教育福祉・労働・人権擁護等11団体による町議会への請願行動。直後から始まった全解連の妨害工作のなか、請願からまる3年の歳月を費やしてようやく条例制定へとこぎつけた。
以下、請願から条例制定までの経緯を中心に出石町における取り組みの状況を報告する。
2. 出石町の概要
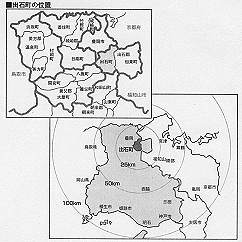 出石町は、兵庫県の北東部に位置し、東は但東町に、西は八鹿町と日高町、南は養父町と和田山町に、そして北は豊岡市と京都府久美浜町にそれぞれ境を接している。
出石町は、兵庫県の北東部に位置し、東は但東町に、西は八鹿町と日高町、南は養父町と和田山町に、そして北は豊岡市と京都府久美浜町にそれぞれ境を接している。
町の歴史は古く「古事記」「日本書紀」にもその名が登場する。室町時代には山名氏の居城が築かれ、全国にその勢力を伸ばす拠点として発展。山名氏滅亡後は小出・松平・仙石と領主がかわる中で出石藩5万8千石の城下町として栄えたが、明治期に入ると、鉄道の敷設に反対したこともあって徐々に衰退の一途を辿ることになった。
しかし、このことで城下町としての町割や近世の町並みが良好な状態で保存されることになり、仙石氏が信州上田からその手法を伝えたとされる「出石そば」とも相まって、近年では年間約100万人の観光客が訪れるところとなった。
なお、現在の出石町は1957年(昭和32年)9月、神美村(現豊岡市)穴見地区を除く1町3村が合併して誕生したものである。
<出石町の概略データ>
・面 積 89.13k㎡(東西約11㎞ 南北約14㎞)
・人 口 11,537人(男5,610人 女5,927人)
・世 帯 数 3,589世帯
・高齢化率 2,823人(男1,146人 女1,677人)24.55%
=いずれも平成14年8月1日現在=
・産業別就業割合
平成7年 第1次産業 10.0% 第2次産業 41.0% 第3次産業 49.0%
昭和50年 第1次産業 26.7% 第2次産業 37.7% 第3次産業 35.6%
3. 出石町における同和(人権)対策事業の実施状況
出石町では、1969年(昭和44年)の同和対策事業特別措置法の施行以来、ハード面においては対象地域の生活・住環境の改善対策に併せて混住化や交流促進等に重点を置いた事業を展開。また、ソフト面においては、町民全体の意識改革を重点目標とした取り組みを今もなお継続して実施している。とりわけ、町内全区を対象とした学習会「心ふれあう区民のつどい」では、係長級以上の全職員が町内学識経験者とチームを編成、1年間で出石町内51集落すべてを巡回するという手法を採用(1チーム当たり3集落程度を担当)。各集落ごとの参加者は平均19~20名程度と決して多くはないものの、住民の生の声を聞く機会を持つことは、職員の人権意識の高揚に少なからず寄与しているものと思われる。
また、住民リーダーの育成を目的とした「人権啓発推進員養成講座」には例年70~80名程度が参加、こうした人達を中心に前記「つどい」等での意見交換も徐々にではあるが活発化しつつある。
<出石町における主な実施事業>
① ハード事業
・1971年(昭和46年) 町立隣保館開館
・1972年(昭和47年) 北部開発事業(町営住宅・県営住宅・分譲宅地造成)
・1974年(昭和49年) 出石愛育園(私立保育園)設置
・1975年(昭和50年) 町立児童館開館
・1981年(昭和56年)~1985年(昭和60年) 小集落地区改良事業(不良住宅除去・改良住宅建設等)
・1983年(昭和58年) 町立出石幼稚園建設(移転新築)
・1990年(平成2年)~1991年(平成3年) 町立弘道小学校建設(移転新築)
② ソフト事業
・1980年(昭和55年)~ 人権啓発紙「たがやし」の発行(年4回、うち1回は人権作文・標語・ポスターコンクールの入賞作品を掲載した人権週間特集号)
・1988年(平成元年)~ 町内全区学習会「心ふれあう区民のつどい」の開催
・1995年(平成7年)~ 「人権啓発推進員養成講座」の開催(年6回)
・そ の 他 差別をなくそう県民運動推進強調月間(8月)に「人権を考える町民集会」、12月の人権週間に「心をつなぐ町民集会」を開催。1985年(昭和60年)以降ほぼ5年に1回の割合で「同和(人権)教育に関する全世帯アンケート」を実施し、意識啓発等の進捗状況等を検証。
4. 条例制定に至るまでの経過
(1) 請願採択までの経緯
1999年(平成11年)3月17日付で、出石町議会に対して部落解放同盟出石支部を筆頭にした11団体の連署により「出石町人権啓発推進条例」の制定を求める請願がなされた。
町議会では教育福祉常任委員会に審査を付託、委員会には共産党(全解連)議員が所属していたこともあって審査は難航したが、請願団体代表者の意見聴取等も踏まえて延べ5日間に渡って審議。この間、全解連は「条例は思想・信条の自由を奪うもの」といったチラシを数回に渡って新聞に折込、共産党街宣車まで繰り出して請願採択の反対キャンペーンを展開。兵庫県からも「地方公共団体が国に先行して条例を制定することは疑問である」「心の問題を条例で規制するのはなじまない」といった旨の“行政指導”もなされた。
しかし、委員会では、賛成3人、反対2人という僅差ながらも“1993年に制定された「人権尊重の町宣言」の理念を踏まえ、21世紀に差別を持ち越さない強い信念をもってこの際「啓発推進条例」を制定すべき”と決定。続く同年6月22日の議会最終日には、委員会報告に基づく無記名による投票の結果、議長(当時)の請願採択に向けた強力な根回しもあって、賛成10、反対5、無効1(議員定数18、欠員1、=議長除く=)の賛成多数での採択となった。
(2) 出石町地域改善対策協議会でも紛糾
町議会での請願採択を受けて町は、出石町地域改善対策協議会に対して「条例制定をも含めた今後の人権啓発の推進について」を諮問。1年4ヵ月後に、同協議会から「人権尊重の理念を根幹におき、町民の相互理解を深め、人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進策を示し、あらゆる差別の撤廃と人権擁護を基本とした条例の制定が必要」との答申がなされた。
しかし、ここでも議会委員会の構成変更に伴い議会側委員として共産党議員が就任したことから紛糾。当時の議事録によると、少数意見として否決されたものの、協議会会長(町同和教育協議会選出委員)に対し「請願者は諮問機関の委員として参加すべきではない」との発言により審議の攪乱を図る場面等もあったという。
(3) 条例制定へ向けて
答申を受けた町では、2000年6月定例町議会での条例提案を決定、条例案の練り直し作業等の準備を進めていた。同年9月の町議会議員選挙を前に、10対5で請願採択となった現有勢力のもとで提案・即決を企図したものだった。
しかし、この計画は共産党議員の画策ともとれる抵抗により頓挫、最終日を前に町長は「今議会での提案を見送る」と言い出す始末。背景には請願採択時の議長の死亡により求心力が失われ、議会会派の構成が混沌とした状態にあったことも一因であった。
(4) 選挙により形勢逆転
2000年9月、出石町では任期満了に伴う町議会議員選挙が行われた。議員定数が16人に削減されて初めての選挙ともあって、現職11人、新人7人が立候補するという近年にない激戦のなか、新人候補者全員が当選。なかには町職と解放同盟が推薦する議員が1名ずつ、両議員を中心に勉強会と称する新人中心の会派が誕生し、議会勢力が塗り替えられることに
― 。
新生議会では、議運ポストこそ共産党に押さえられたものの、議長をはじめ各委員会の主要ポストを新会派がほぼ独占。12月議会での条例提案後の委員会審査も円滑に運び、3月議会冒頭での採決も最初に記したように賛成多数により可決という結果となった。
この間、全解連の抵抗はほとんどなく、議会採決直前の3月6日になって「町民の皆様に緊急の訴え」と題した反対チラシを新聞折込する程度にとどまった。
<出石町人権尊重のまちづくり条例制定までの経過>
① 人権啓発推進条例制定に関する請願提出まで
・1991年9月26日 出石町議会「同和対策の充実・強化及び部落解放基本法制定に対する請願」を採択。「部落解放基本法の制定を求める意見書」を採択し、内閣総理大臣ほか関係大臣へ提出。
・1993年6月24日 「人権尊重都市宣言に関する請願」を議会で採択。
12月10日 「『人権尊重の町宣言』の制定について」を町議会が可決、制定
② 人権啓発推進条例に関する請願提出後
・1999年3月17日 「『出石町人権啓発推進条例』制定に関する請願が議会へ提出される。
3月23日 紹介議員により議会本会議にて請願提案→教育福祉常任委員会に閉会中の審査として付託。
6月3日 教育福祉常任委員会にて評決の結果「採択すべし」と可決。
6月11日 兵庫県より地域改善対策担当課長等が来庁「条例制定は好ましくない」との行政指導を受ける。
6月22日 出石町議会本会議にて委員会報告の後、質疑応答、採決の結果、可決。
6月25日 町議会より町長あてに採決通知と併せ条例制定の要請あり。
8月10日 出石町地域改善対策協議会に対し、町長から「条例制定をも含めた今後の人権啓発推進について」を諮問。
・2000年12月18日 出石町地域改善対策協議会から町長へ「あらゆる差別の撤廃と人権擁護を基本とした条例の制定が必要」との答申がなされる。→条例案を検討。
・2001年6月4日 出石町法制審議会を開催。6月定例町議会への「人権尊重のまちづくり条例」提案を決定。
6月8日 町幹部会議にて条例案の議会初日提案を決定。同日、共産党議員団から町長に対し「担当課長が議員に対して不適切な発言をした」との申し入れ。
6月12日 議案書から「人権条例案」が外され議会初日提案が消える。当局は「追加議案として提案する」と説明。
6月25日 担当課長、議会全員協議会の場で謝罪。直後、町長が不祥事を理由に「今議会での提案を断念する」と発言し、条例案の提案は見送りに。
・2001年9月 出石町議会議員選挙(定数16、出石町職推薦候補・解放同盟出石支部推薦候補共に当選、新人議員7名誕生。議長選挙にて新人会派が推薦する議員が議長に就任)
・2001年12月10日 出石町議会へ「出石町人権尊重のまちづくり条例」を提案。→教育福祉常任委員会へ閉会中の委員会審査として付託される。
2月26日 委員会にて出席委員全員一致で「可決すべし」と決定。
3月7日 議会本会議にて委員会報告、質疑・賛否討論の後、採決の結果、賛成多数にて可決。→翌3月8日付で条例・規則を公布・施行。
5. おわりに(今後のまちづくりに向けて)
出石町における人権条例の制定は、難産とはいえども県下他市町に比べると比較的スムーズに運んだように思われる。これは、①請願書が障害者・女性団体等を含む11もの団体の連署で提出されたこと、②10年以上に及ぶ「心ふれあう区民のつどい」をはじめとする啓発活動により、町民の人権に対する意識が向上してきたこと、などが背景にあるものと考えている。とりわけ今年で14年目を迎える「つどい」には、年平均1,000人が参加。延べ人数にすると町人口を上回る数の人々が参加したことになる。
このことは、これまでの部落解放運動とそれに呼応した同和行政がもたらした一定の成果だと考える。もちろん、同和地区に対する心理的差別はまだまだ根強いものがあり、一方で、障害者・高齢者等社会的弱者に対する偏見や差別が顕在化する現状もある。しかし「自分がされていやなことを他人にしないことが“人権”を尊重すること」。「つどい」のなかで出されたこうした意見に代表されるように、出石町における人権感覚は着実に向上しつつある。
今後、条例に基づく「人権尊重のまちづくり審議会」の答申を踏まえ、「まちづくり基本計画」を策定することになるが、この計画のなかで従来の取り組みにさらに磨きをかけ、それをどう展開して行けるかー。地方の分権化が進むなか、出石町はこれまでの同和行政をさらに発展させるための取り組みを始めようとしている。
|
【資料-1】 出石町人権尊重のまちづくり条例 平成14年3月8日 (目 的) |
|
【資料-2】 出石町人権尊重のまちづくり条例施行規則 平成14年3月8日 (目 的) |
|
【資料-3】 出石町人権尊重の町宣言 平成5年12月10日 人は、生まれながらにして自由であり、かつ人間の尊厳と権利とについて平等である。 |