【自主レポート】
|
福井発 地球環境と人に優しい電車を求めて 福井県本部/福井市職員労働組合・福井市総合交通課・ |
1. 最悪のタイミング
福井県北部を走る京福越前線は、9つの市町村を貫く全長59.2kmにもおよぶ地方私鉄で、福井市を起点に、東尋坊のある三国町、スキージャムのある勝山市、大本山永平寺のある永平寺町を終着地に3つの路線が伸びています。
 大正3年より様々な変遷を経て現在の路線に至っていますが、平成12年12月、ブレーキの故障による正面衝突事故に続き、わずか半年後の平成13年6月には信号見落としによる2度目の正面衝突事故を引き起し、全国紙を騒がす結果となりました。
大正3年より様々な変遷を経て現在の路線に至っていますが、平成12年12月、ブレーキの故障による正面衝突事故に続き、わずか半年後の平成13年6月には信号見落としによる2度目の正面衝突事故を引き起し、全国紙を騒がす結果となりました。
折しも、2度目の事故の前日には、勝山駅構内で大規模な電車存続決起大会が開催されており、死者こそ出なかったものの、事故は最悪のタイミングで起こったのです。
前代未聞の事故に対し、前例のない行政処分が下り、平成13年7月から電車は止まったままで、現在は、線路に沿うルートで代行バスが走っています。
一方、京福線を存続するか、廃線にしてバス転換にするかの議論は、事故を契機ににわかに始まった訳ではなく、平成4年頃より水面下での比較検討が始まっていたようで、県と沿線市町村は、平成10、11、12年度の3年間の行政支援と利用促進策の成果を検証して、毎年3億円強の赤字を出してしまうこの鉄道の未来を、どのようにするかを協議していた矢先に事故が起きてしまい、急転直下の激しい議論に発展したのでした。
2. 崖ップチからの生還
京福電鉄側は、国の改善命令による多額の費用負担を目の前にして、早急な行政判断(3セク化)を求めていましたが、9月議会での県知事の判断は、京福電鉄側の廃線手続きを容認し、存続か廃止かの結論は12月議会で決着するというものでありました。
これを受けて京福電鉄は廃線手続きに入り、その後、鉄道部の職員は配置転換されてしまったのです。
これにより、たとえ新会社(3セク)で鉄道を存続しようとしても、電車を動かしながら運行技術を継承したり、マンパワーの移行をシームレスに行うことができなくなり、富山県の万葉線のようなソフトランディングは期待できなくなってしまいました。
多くの課題を残しながら、現在、新会社(3セク)設立の準備室がようやく飛び立ち、京福電車はまさに、崖ップチからの生還を果たしたのでした。
しかしながら、開業当初には部分的な運行再開を余儀なくされたり、まちづくり計画によって経路が制約されるなど、かなりのハードランディングも予想されるため、県と沿線市町村は一丸となって難題に取り組んでいるところです。
3. 京福電車と地球を愛する会
ところで、京福電車には「京福電車と地球を愛する会」というサポーターズクラブが沿線都市ごとに結成されており、命名の由来は言うまでもなく、地球環境の保全には電車は必要不可欠であるというアピールであります。
 しかしながら、エネルギー効率の面から京福電車を診断すると、決して地球に優しい乗り物とは言えないのが実感であります。
しかしながら、エネルギー効率の面から京福電車を診断すると、決して地球に優しい乗り物とは言えないのが実感であります。
現場の努力には深く敬意を表するものの、会社の経営方針により設備投資がほとんど行われなかったため、昭和30年代に製造された老いぼれ車両がゴロゴロしており、電車はガタガタ、線路はデコボコという状態にあります。当然、相当な送電ロスが見込まれており、人1人を1㎞運ぶエネルギー効率は、都会を走る電車に比べ格段に低くなっていると思われます。
いくら電車は環境にやさしい…、二酸化炭素を出さない原発の電気を使うのだから…。と言われても、地球環境へのトータル的な貢献度には疑問を感じてしまいます。
4. 今どきの電車
21世紀にふさわしい電車は、快適・安全に加え、コストダウン・バリアフリー・エコロジーなど多種多様な機能が求められ、全国的にも、斬新で思い切った決断が見受けられます。
過去の例によれば、くりはら田園鉄道(宮城県)のように電化を取りやめ、ランニングコストの安いディーゼル列車に転換する方法も考えられますが、環境重視型の社会情勢では、ディーゼルに対するアレルギーは強いはずで、今どき、新規導入することは困難と考えています。
一方、最近の例では、東急世田谷線が、たった一夜にして20ものホームを嵩上げし、新型電車の対応を瞬時に行い、バリアフリー化を実現した事例があります。また、鹿児島、高知、松山市では、純国産の超低床車両が相次いで投入され、日本におけるLRTの潮流を確実に呼び寄せています。先陣を切った熊本、広島市に比べ、車両価格は2億円を切っており、車両価格がどんどん下がる中、多くの地方都市で導入ラッシュが続き、質の悪い鉄道はどんどん淘汰され、姿を消して行くと思われます。
また、JR東日本は、更新をむかえる管内のディーゼル列車に対して、ハイブリッド列車を投入する意向を表明し、新たな鉄道技術の扉が開こうとしています。
5. 耳慣れない電車
ハイブリッド列車とは耳慣れない言葉でしょうが、お馴染みトヨタのプリウスとは、多少動力システムが異なります。プリウスは、電気で走る場面とエンジンで走る2つの場面があり、これをパラレル方式と呼ぶのに対し、ハイブリッド列車は、発電を専門に行う内燃機関を搭載し、蓄電池やコンデンサーの補助電源を借りて、終始、モーターを回し続ける仕組みで、これをシリーズ方式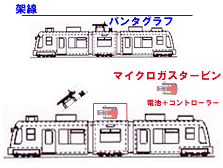 といいます。
といいます。
すなわち、ハイブリッド列車は、内燃機関を搭載した自家発電型の電車ということになり、内燃機関の選択については、ディーゼルエンジンやマイクロタービン等が考えられます。
マイクロタービンを搭載したバスについては、東京電力が海外から輸入した実績がありますが、旅客鉄道については国内事例がなく、工事用機関車の開発に止まっています。
マイクロタービンとは、小さな壷をイメージしていただければよく、その中ではどんな燃料も燃やせることが特徴です。天然ガスに転換しつつある福井市においては、圧縮天然ガス(CNG)を使用するのが最適であると考え、その可能性を模索しています。
もちろん、内燃機関である以上、二酸化炭素を放出する訳ですから、将来的には、燃料電池を搭載した燃料電池列車に再転換することが究極の目標となります。
分散型の電源開発により送電ロスをなくし、自家発電によるコストダウン、古い電車の総入れ替えによるバリアフリー化、天然ガス使用によるエコロジー化が実現できるのであれば、京福電車の未来はムチャクチャ明るくなると信じています。
6. 地球への思いやり
自家発電型列車へのアプローチは、高い専門性や開発費用がネックとなり、関係者に照会状を送付している状況に止まっていますが、何とか車両メーカー、専門家を巻き込んだ実証実験が実施され、市場にマイクロガスタービン搭載の電車が登場することを強く願っています。
自動車メーカーは、燃料電池車を市場に出すことにしのぎを削っており、燃料電池車が普及した時点では、環境対策という大義名分に包まれた地方ローカル鉄道のベールは一挙に剥ぎ取られ、存在意義すら失ってしまうでしょう。
鉄道だって早い段階から技術革新に取り組むべきであり、全世界を走り回るディーゼル列車や非効率なローカル電車を、とりあえず自家発電型のマイクロタービン列車に転換し、将来は燃料電池列車に再転換することが、地球に対する思いやりではないでしょうか?
7. 人への思いやり
また、人への思いやりも大切であり、東急世田谷線が歩んだ道は、京福線のリニューアルにとっての大切な道しるべになると思います。
同社は、旧型車両を一掃し、新型電車の全車両入れ替えを決断する際、超低床車両を導入するのか、先に導入した少々床の高い300系の新型車両を大量更新するか、社運を掛けた岐路に立ったそうですが、高い鉄道技術とポリシーにより、1つの英断を行っています。また、バリアフリー化については、「社会的貢献」などとは位置づけず、お客様本位の「人への貢献である。」と言い切っておられる点は実に新鮮であり、実際には利用者の心をつかみ、利用者増に成功しています。
ICカードの導入や地域住民と一丸となった沿線の花いっぱい運動など、学ぶべき点が数多く見受けられ、その鉄道魂と人への思いやりについては是非とも参考にしていただきたいと思います。
8. プラス思考で見切り発車
京福線を短期的にどこまで運行再開させるのか、あるいは、中長期的にどのような鉄道にリニューアルさせ、将来ビジョンをどうするのかという点については、残念ながら現段階でのベクトルの一致はなく、信じられないくらい曖昧になっています。
「問題の先送りである」とか「行政の怠慢である」とのお叱りも受けましょうが、私は次のような考え方をヒントにしてこの問題を受け止めています。
最近、医療の分野で心療内科というカテゴリーがあり、ある先生によれば、人間は2つに分類できるとおっしゃっています。
それはマイナス思考型の人間とプラス思考型の人間で、マイナス思考型の人間は1つの答えを出さなければ先に進めず、有りとあらゆることについて考え込んでしまう人間だそうです。また、プラス思考の人間は、複数の答えに満足し、答えの出ない問題については、その時点ではそれ以上考えないという人間であります。もちろん、心の病気になり易い方は、前者のマイナス思考型の人間ということになります。
京福線についても、マイナス思考型の人間で臨むのか、プラス思考型の人間で臨むかで、問題の捉え方が大きく変わってくるのでしょうが、答えが出ない問題はその時その時で必ずある訳で、少なくとも私自身はプラス思考でこの問題に携わって行きたいと思っています。
9. こころざしは高く
とは言っても、京福電車とまちづくりに絡む問題は、容赦なく押し寄せており、高いレベルでの判断が次々に求められる状況になっています。こうした状況下では、トップと事務方、市民と行政における情報の共有化と認識の一致が極めて重要となりますが、誰もが高いこころざしを持たなければ、前には進めないと思っています。
衝突事故以前の電車に復元させるだけでは、京福電車の未来は絶対に来ないし、中途半端な対策では再び廃線の危機に陥ってしまいます。
地球環境に優しく、人に優しい電車に大変身することが生き残る道であり、福井発の斬新な電車が1日も早く、福井の街を走り回ることを夢見てペンを置かせて、いや、パソコンの電源を切らせていただきます。