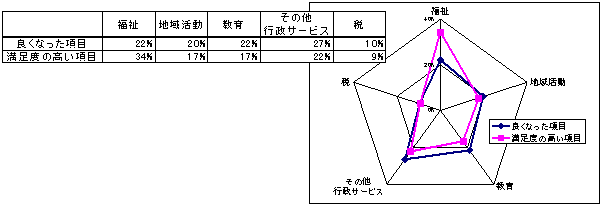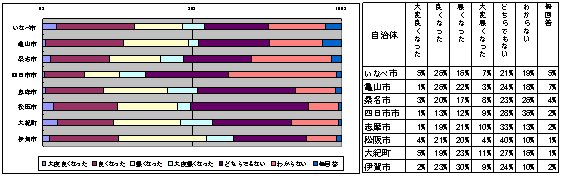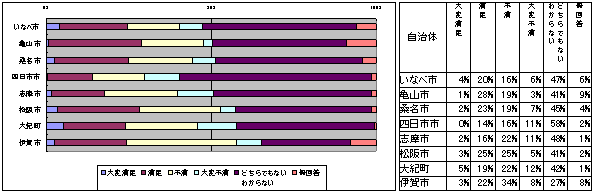【自主レポート】
|
市町村合併の検証 三重県本部/「市町村合併の検証」ワーキンググループ |
1. はじめに
三重県内の「平成の大合併」は、2003年12月1日の「いなべ市」市制施行を皮切りに、それまでの69市町村であった自治体数が14市15町となって一定の区切りを迎えた。
この間、総務省では2005年11月から「市町村の合併に関する研究会」を開催し、「市町村の合併の特例に関する法律」の下で実施された市町村合併の状況を踏まえ、市町村の合併に関する課題について有識者による研究を行い、国民・市町村・都道府県及び国からみた効果についての報告がなされている。
地方分権の一層の推進、少子高齢化社会及び広域行政の対応など、厳しい財政状況の下で行財政基盤の強化が喫緊の課題であるとし、国の施策として推し進められてきた今回の市町村合併が、住民サービスや自治体の職員の意識に与えた影響を考察することで、国のいうところの合併効果をあらためて検証するものである。
2. 自治研「市町村合併の検証」ワーキンググループ体制
| 酒井 幸久 | 自治労三重県本部自治研推進委員長 自治労三重県本部副委員長 |
|
| 和田 義美 | 自治労三重県本部中執 | |
|
|
橋本 寛 | 自治労三重県本部自治研推進副委員長 三重県地方自治研究センター |
|
|
駒井 克也 | 三重県職労 |
|
|
長澤 和也 | 伊勢市職労 |
|
|
福山 朋宏 | 伊賀市職労 |
|
|
福山 桂 | 松阪市職 |
|
|
西 喜久也 | 熊野市職労 |
|
|
中出 賢一 | 多気町職 |
|
|
世古口哲哉 | 明和町職労 |
|
|
岡本 元 | 紀宝町職労 |
| 内堀 剛 | 自治労三重県本部書記 |
3. 自治研「市町村合併の検証」ワーキンググループ開催状況
第1回
と き 2006年3月23日(木)15:00~
ところ 津市・(財)三重地方自治労働文化センター4F
第2回
と き 2006年4月12日(水)15:00~
ところ 津市・(財)三重地方自治労働文化センター4F
第3回
と き 2006年4月27日(木)14:00~
ところ 津市・(財)三重地方自治労働文化センター3F
4. 市町村合併の目的と県内の合併状況について
(1) 市町村合併の目的
国は市町村合併について、①地方分権による市町村の役割の重要性、②少子高齢化社会への対応、③広域的な行政需要の増加、④構造改革の推進への対処の4点をかかげた上で、基礎自治体としての市町村の規模・能力を充実し、行財政基盤を強化することが喫緊の課題であるとし、そのための手段として市町村合併を推進してきた。
「市町村の合併に関する研究会」2005年度報告書によると、市町村合併の具体的な効果としては、市町村運営の効率化による職員数の削減や行政運営の効率化により、それが経費削減として、あるいは住民サービスの維持・向上など、様々な形で発現するとされている。
また、住民、市町村、都道府県、及び国からみた市町村合併の効果としては、概ね次のようなものがあるとされている。
① 住民からみた効果
ア 住民サービスの維持・向上
イ 利便性の向上
ウ 地域コミュニティ、地域間交流の活性化
エ 地域の知名度向上、イメージアップ
オ 行政経費への理解向上(財政支出の縮減による行政コストに対する理解)
カ 産業活動の円滑化
キ 防災力の向上
② 市町村からみた効果
ア 専門的できめ細かい施策の推進
イ 都道府県からの権限委譲による自立性の向上
ウ 広域的なまちづくりの充実
エ 行財政基盤の強化(規模の拡大に伴う財政支出の縮減など)
オ 歳入の確保
③ 都道府県からみた効果
ア 市町村への権限委譲の進展
イ 権限委譲に伴う出先機関の再編等、都道府県組織の簡素化
ウ 市町村との調整事務の効率化
エ 上記に伴う財政支出の縮減
④ 国からみた効果
ア 地方分権の推進、構造改革の推進
イ 市町村数の減少に伴う支部分部局と都道府県との間の調整事務の負担の軽減
ウ 上記に伴う財政支出の縮減
概略は以上であるが、各々の効果は密接に関連し、また、全ての効果が同時期に現れるものではなく、施策の比重などにより異なって発現するものであり、中長期的な視点から把握する必要があるとされている。
(2) 三重県内の合併状況
市町村合併の効果を検証するにあたっては、合併後一定の期間を経た自治体でなければ、自治体職員の意識や住民サービスの変化を考察することは困難である。したがって、本ワーキンググループでは、合併後1年以上を経た市町を対象に考察することとした。具体的には2005年2月までに合併を終えた「いなべ市」「志摩市」「伊賀市」「桑名市」「松阪市」「亀山市」「四日市市」「大紀町」を対象に、市町村合併の考察を行った。
それぞれの合併後の市町概況は下表のとおりである。合併の形式としては、四日市市のみ編入合併で、他は全て対等合併(新設)となっている。
年月日 |
世帯数* |
一般会計予算 |
(一般行政部門) |
|||
12月1日 |
219.58km2
|
13,750世帯 |
17,570,000千円 |
342人 |
4町対等合併分庁舎方式 | |
10月1日 |
179.6km2
|
22,149世帯 |
22,221,000千円 |
598人 |
5町対等合併支所方式 | |
11月1日 |
558.17km2
|
38,430世帯 |
44,570,837千円 |
859人 |
6市町村対等合併支所方式 | |
12月6日 |
136.7km2
|
51,103世帯 |
46,885,407千円 |
693人 |
3市町対等合併支所方式 | |
1月1日 |
623.8km2
|
65,012世帯 |
53,632,582千円 |
1,114人 |
5市町対等合併地域振興局 | |
1月11日 |
190.91km2
|
18,446世帯 |
18,429,700千円 |
302人 |
2市町対等合併支所方式 | |
2月5日 |
205.12km2
|
121,132世帯 |
95,400,000千円 |
1,341人 |
2市町編入合併支所方式 | |
2月14日 |
233.53km2
|
4,090世帯 |
6,605,000千円 |
187人 |
3町村対等合併支所方式 |
| (注1) 人口・世帯数は各市町のホームページより確認しました。最新情報に比べて若干の相違があります。 (注2) 定数は地方公共団体給与情報等公表システムの2005年度データを参照しました。 |
5. 市町村合併に伴う住民サービスの変化
先に述べたように、国(市町村の合併に関する研究会)は、住民から見た様々な市町村合併の効果について報告している。本ワーキンググループでは、はたして福祉サービスや地域活動など様々な観点から、住民がどのように市町村合併を受け止めているのかを調査することで市町村合併の検証を行うこととした。
具体的には、調査対象のそれぞれの自治体別に、NTT電話帳による無作為抽出した住民に対して、郵送によるアンケート調査を行った。
アンケート項目及び特徴的なものは次のとおりである。
(1) 福祉サービスについて
① 保育所や子育て支援施策について
② 介護サービス全般について
③ 高齢者福祉サービス全般について
④ 障害者福祉サービス全般について
⑤ その他、福祉サービス全般について
(2) 地域活動について
① 地元の祭りなど諸行事について
② 地域の文化遺産・歴史などの保全について
③ 集会所や公民館、あるいは自治会への支援などについて
④ その他、地域活動全般について
(3) 教育について
① 小中学校の通学について
② 幼稚園や学校など教育サービス全般について
③ 子どもたちの交流について
④ 図書館、体育館など学校の施設について
⑤ 人権啓発、文化事業、スポーツ事業など教育施策全般について
⑥ その他、教育全般について
(4) その他、行政サービス全般について
① 年金や農業・商工業の相談、あるいは住民票発行手続などについて
② 広報誌や情報公開制度などについて
③ 各種公共施設の利用について
④ 道路や下水道など生活基盤の整備について
⑤ ゴミ収集など廃棄物対策全般について
⑥ 地域の活性化に対する合併後の「まちづくり」について
⑦ 新しい自治体名になったことについて
⑧ 防災・防犯対策や交通安全対策について
⑨ まちづくり全般にかかる様々な施策について
⑩
市町村合併について
(5) 公共料金について
① 税負担について
② 公共施設の利用料について
③ 保育園、幼稚園の保育料について
④ 水道料金について
⑤ その他、各種料金や税について
アンケート内容は、それぞれの項目において、住民が実感として「大変良くなった」「良くなった」「悪くなった」「大変悪くなった」「どちらでもない」「わからない」のいずれの感覚に近いかを選択するとともに、各項目に対する満足度として「大変満足」「満足」「不満」「大変不満」「どちらでもない・わからない」を選択する方法とした。
項目毎の詳細集計結果は資料「住民アンケート集計結果」を参照されたいが、市町村合併に対する住民の評価の傾向を把握するため、アンケート回答数を全項目について単純合計し、その割合を確認したところ、いなべ市の「大変良くなった」「良くなった」の合計比率が30%を超え、かつ「悪くなった」「非常に悪くなった」の合計比率とほぼ等しい自治体であった。(図1)。
このことは、三重県内の自治体の中でもっとも早い時期に合併したことで、合併後の具体的な施策が住民サービスに対する効果として現れたものであると考えられる。
また、旧自治体人口の比較的多い市が含まれる状況で合併した四日市市や桑名市などは、今回のアンケートが電話帳による無作為抽出であることから、旧市の住民の回答数が多いことが要因のひとつとなって、市町村合併による施策が実感されにくい、すなわち合併による変化を受けにくい傾向にあると考えられる。
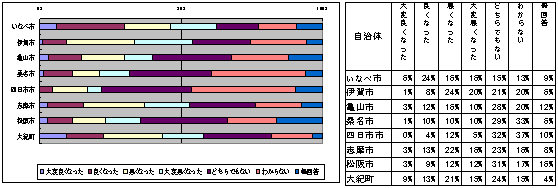 |
市町村合併に対する住民の満足度についても全体的には同様の傾向ではある(図2)。このことは、いなべ市の場合は合併後の施策が住民の満足度につながっている好例であると考えられる。
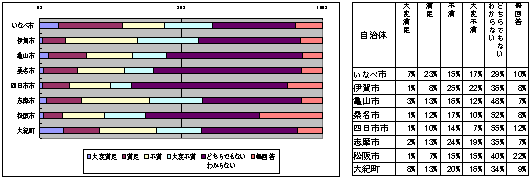 |
続いて、市町村合併による効果が他の自治体に比べて顕著に発現していると考えられる、いなべ市についてさらに詳しく調査をしてみることとする。
アンケート項目の「福祉」「地域活動」「教育」「その他行政サービス」「公共料金」について、細項目の回答数を合計することで、各々のカテゴリーの何が効果をもたらしているか、あるいは合併に対する満足度向上の要因となっているかを検証する。
それぞれの項目で、合併による効果をプラスとして評価している項目「大変良くなった」「良くなった」の回答数を細項目数で平均し、それら項目ごとの比率をチャートグラフに表したものが(図3)である。