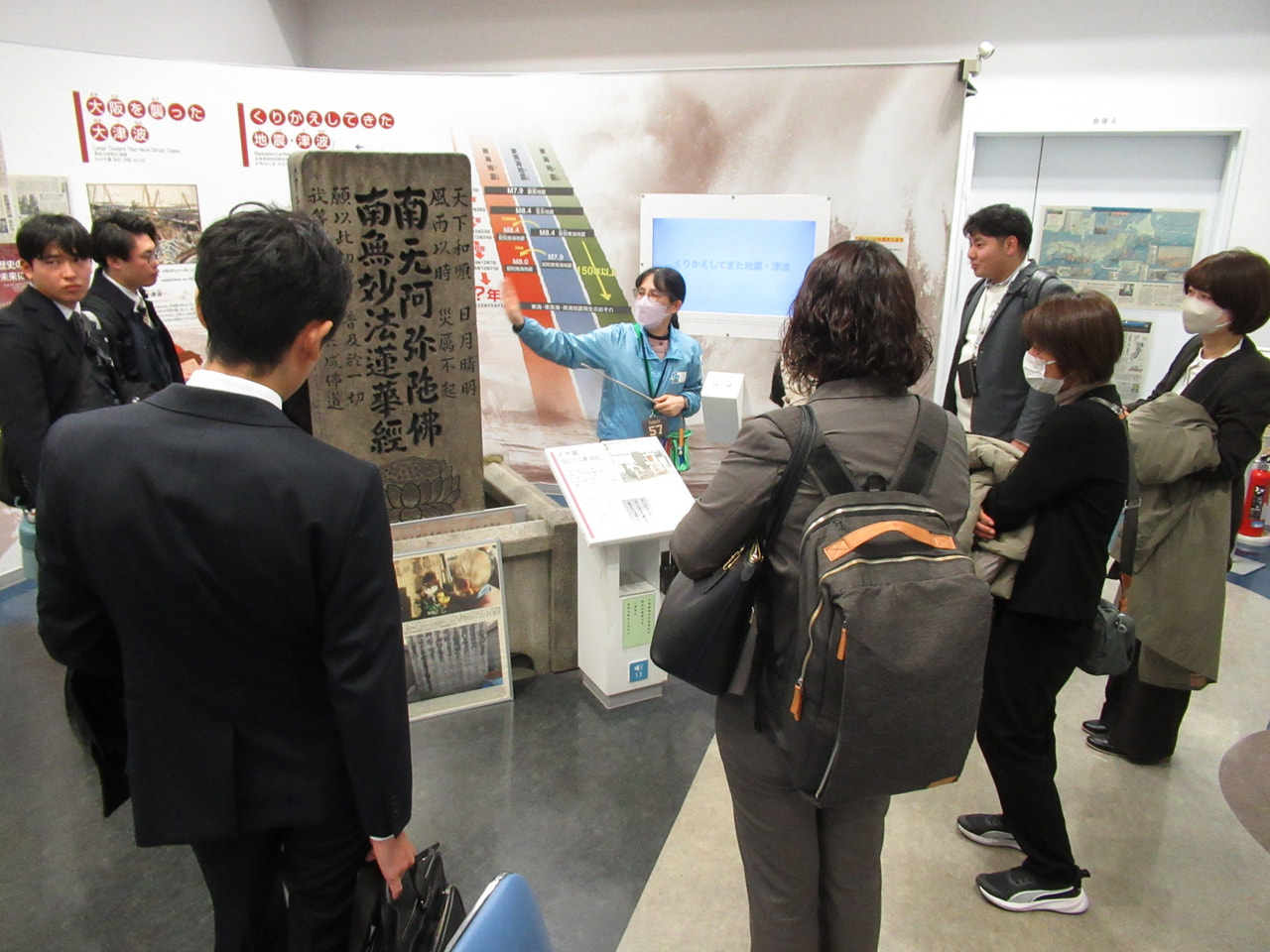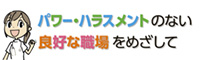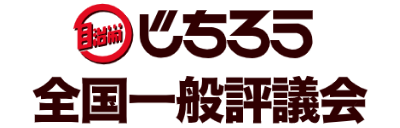2025/08/18

都市公共交通評議会は7月31~8月1日の2日間、仙台市内で第3回鉄軌道部会を開催。同市の地下鉄施設を視察するとともに、各都市が抱える地下鉄・路面電車事業の課題、2026年度政府予算編成に関する要請内容を協議した。
【1日目】富沢車両基地を訪問、最新車両を見学
1日目は、仙台市交通局富沢車両基地を訪問し、地下鉄南北線で2024年10月より営業運転を開始した3000系の車両の特徴、利便性等の説明を受けた。3000系車両は、1987年の開業時から運行している1000N系が耐用年数を迎えたことから、2030年までに最大22編成が置き換えられる。南北線の車両は4両編成で中間車両は20m、先頭車両は中間車両に乗務員室を溶接により後付けしているため21.75mと他の地下鉄車両とは異なっており、3000系車両もこれを引き継ぐ形状となっている。
また、車両デザインには長く親しまれてきた「杜の都」をイメージした「グリーン」が受け継がれラインカラーに取り入れられている。最新の車両だけにLED照明、車内カメラ、乗降口上部の液晶表示器による多言語案内表示はもちろん、バリアフリー化を推進するため、幾度となく障害をもつ利用者とも対話を行い改良が重ねられ、車いすスペースの2段手すりの高さや向き、車いす利用者からみた乗降口上部の液晶表示器が見易い角度になっていること、女性にも利用しやすい高さの網棚、日本一低いつり革など細部までこだわりが感じられた。また、座席には2席毎に立ち上りや着席の補助として縦手すりが設けられている。
質疑の中で説明を担当した仙台市交通局鉄道技術部車両課・大橋基樹課長からは、「こちらの車両は乗客が出入口付近に滞留するようになった」との説明があり、その理由が参加者に問いかけられた。参加者からは、「縦手すりの形状では(下部が張り出している)、床シートの張り合わせの為のラインが心理的に作用しているのではないか」などの意見があり、それぞれ持ち帰って報告・検証することとした。

その後、車両基地に併設されている「仙台市電保存館」を訪れ1926年から1976年までの50年間にわたり、仙台市民の足として暮らしを支えた車両や展示品、写真に触れ思いを馳せた。なお、函館市や熊本市、鹿児島市では一部ではあるが同世代の車両が現役で活躍していることも報告された。

【2日目】部会で各単組の報告と意見交換
2日目は部会を開催し、中央交運労協の鉄・軌道部会、政府の2026年度予算公共交通関係予算の概算要求に関わる報告を受けた。それを踏まえ、都市交評で8月に実施する国土交通省への2026年度予算編成に関する要請書の内容を協議、確認した。
引き続き、各単組より直面する事業効率化や人員不足問題等の課題について報告を受けた。
多くの単組において、2025年度の事業計画が提案されたことを受け、計画の状況や課題について報告を受けた。5か年、10か年の経営計画が策定される中、いまだに残る新型コロナウィルス感染症の影響や昨今の物価上昇による燃料費などの諸経費高騰により計画の改定や見直しが実施されている。そのような中で「駅施設の改良工事」や「バリアフリー施策の増強」「路線の延伸」など前向きな提案を受ける一方、「人員不足を補う対策としてのAIの活用」やDX推進、MaaSの推進など、従来の駅務業務を超えた新しい技術への対応も求められている。