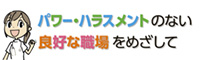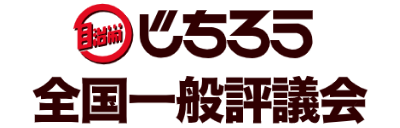2025/03/05

地域での孤立対策の活動を報告する、福山市社会福祉協議会の小野裕之さん
社会福祉評議会は2月22~23日、2025年度くらしとこどもの福祉を考える全国集会を東京・連合会館で開催し、全国から約130人が参加した。
集会は初日に全体会、2日目に分科会の形式で開催した。
全体会では基調提起と2つの講演で構成。まず、講演「こどもたちを孤立させない地域づくりに向けて~貧困の連鎖を断ち切るために~」では、広島県・福山市社会福祉協議会の小野裕之常務理事兼事務局長にお話しいただいた。
小野さんは生活困窮者の支援をしてきた経験から、生活保護世帯や生活困窮者に対して単に経済的支援を行うだけでは貧困の連鎖は解消できないとして、社会人や学生ボランティアによるマンツーマンでの学習支援の場を作り出し、「基礎学力の定着」と「安心できる居場所づくり」に力を入れてきた(福山市の子どもの健全育成支援事業を社会福祉協議会へ委託。ケースワーカーが世帯の状況を踏まえて随時支援が必要な場合を抽出し学習支援につないでいる)。その取り組みをさまざまな事例を交えながら紹介した。
小野さんは「より実効性あるものとするためには横のつながりが必要だが、それはある個人の才能抜きにでき得ないことでは決してなく、どの自治体でも可能である」として、さらなる広がりを呼び掛けた。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇
2つ目の講演「こどもまんなか社会の到来と子育て支援~相談支援を円滑に行うための地域支援機関の連携・協働のあり方について~」では、井上登生日本子ども虐待防止学会理事にお話しいただいた。
井上さんは小児科医として大分県中津市の子ども虐待予防や社会的養護などに関わってきた経験をもとに、幅広い視点から事例・知見を紹介。とくに、2024年施行の改正児童福祉法を実効性のあるものとするために、連携・協働に際し、法などの「知識」と交渉(話の持っていき方や合意形成を含む)の「技術」を背景に、つながりを紡いでいくことの必要性を説いた。
また井上さんは、「現在の児童相談所や児童養護施設などでは、新人に最初からケースを担当させるため、知識が不十分で困難に直面することが多く、やりたがらない職種となっている。職員の定着が課題だ」と指摘。ケースワークするための知識自体を積み上げることと同時に、ケースワーカー等自身の状態(健康や困っているとき助けを求めることができる、など)についての知識も重要であると強調した。そのうえで、研修体制の見直し・刷新を提案しながら、時間的空間的制約を受けづらいYouTubeを活用した学習として、ご自身が現在準備中の「naripyチャンネル」(誰でも無料で視聴可能)も紹介した。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
2日目の分科会で参加者は、「生活保護・生活困窮者自立支援」と「児童相談・社会的養育」の2分科会に分かれ、グループワークを中心に現場の事例や課題意識を互いに投げかけあいながら議論を行った。